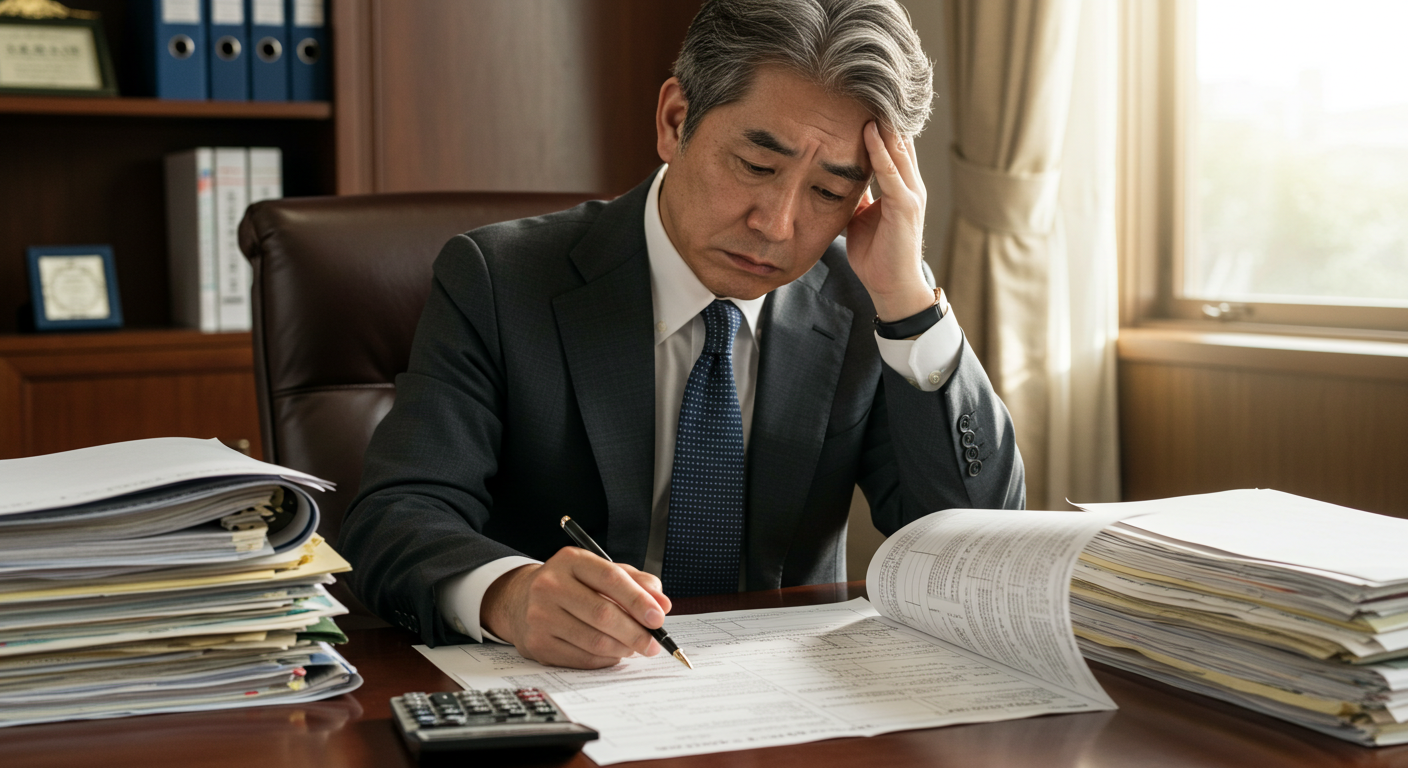目次 1 準確定申告の基本的な注意点 2 所得控除に関する注意点 3 特定の所得に関する重要な注意点 4 個人事業主の場合の特別な注意点 5 相続税との関連 6 生前からの準備の重要性 こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 大切な方が亡くなられた後、悲しみの中で様々な手続きに追われることになります。そんな中、ほとんどのケースで、初めに期限が訪れる税務手続きが「準確定申告」です。これは、亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告で、相続人が代わりに行う必要があります。 今回は、準確定申告で特に気をつけたいポイントを分かりやすく解説します。 リンク 国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) https://iinotax.com/blog/7873/ 1 準確定申告の基本的な注意点…