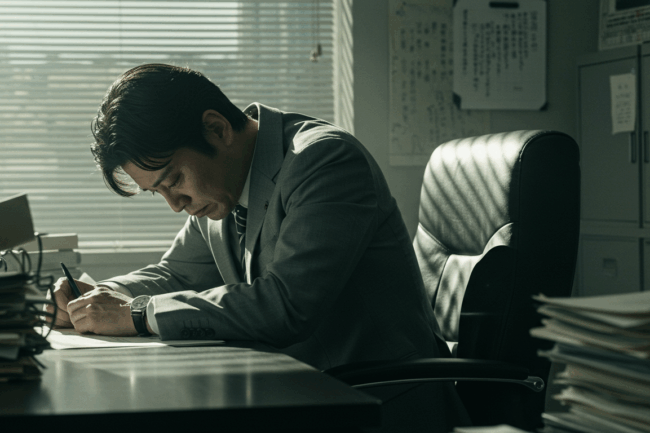はじめに|税理士変更を真剣に考えはじめたあなたへ
「税理士を変えたいけれど、どうしたらいいかわからない」
「今の税理士と合わないけれど、契約を切るのは気が引ける」
「良い税理士を探す方法が知りたい」
そう感じたことはありませんか?
私たちのもとにも、富士市・富士宮市をはじめ多くの経営者の方から、顧問税理士の見直しに関する相談が寄せられています。
税理士の変更は、一見すると煩雑で勇気の要る行為に思えるかもしれません。しかし、あなたの事業の成長と安定を支えるパートナーを見直すことは、経営判断として非常に合理的であり、必要なステップでもあります。
本記事では、税理士変更の実務から心理的なハードル、変更後の注意点、そして新しい税理士の探し方まで、整理しました。
1 税理士を変更したいと感じる主な理由とは?
顧問税理士の不満が多い背景には、日常業務の中で感じる“違和感”の蓄積があります。
下記のような悩みが代表例です。
| よくある不満 | 背景・理由 |
|---|---|
| 相談しづらい・質問がしにくい | 忙しそうにしていて、経営相談ができない |
| レスポンスが遅い | メールや電話の返答が数日かかる |
| 節税提案がない | 申告書は出してくれるが、将来を見据えた提案がない |
| 営業ばかりされる | 税務と関係のない投資の話が多い |
| 人間的に合わない | 言葉遣いや態度が高圧的、無愛想 など |
これらは、税理士を変更したくなる“兆し”であり、本当に必要な支援を受けられていない証拠ともいえます。
2 税理士の変更をためらう心理的ハードルとその克服法
「不満はある。でも今さら契約を切るのは気まずい…」
多くの方がこのような心理的ブレーキを感じています。
税理士は契約でつながっているビジネスパートナーです。
長年の付き合いであっても、「経営にプラスにならない」と判断した場合には、見直すのが合理的な経営判断です。
よくある懸念とその対応策
| 心配ごと | 解決策 |
|---|---|
| 一から説明するのが面倒 | 新しい税理士が初期面談で業務フローや過去の数字を整理してくれます |
| 税務調査への影響が心配 | 税務調査には新税理士が同席可能。過去の対応資料は旧税理士から取り寄せられます |
変更のタイミングや手続きさえ押さえれば、トラブルなくスムーズに移行することが可能です。
3 税理士変更のベストタイミングはいつ?
税理士変更 のタイミングにおける悩みのひとつに、契約解除や顧問料の重複リスクを避けたいという悩みがあります。
最も理想的なタイミングは「決算・申告完了直後」
理由は以下のとおりです。
決算が終われば、その期の作業は一段落する
新しい税理士は次期の初めから引き継げる
顧問料が旧税理士と新税理士で重複しにくい
伝えるタイミングは「申告完了直後」がベター
決算の途中で伝えると、税理士の士気に影響が出る可能性があります。
そのため、「来期からの変更を予定している」ことを、穏やかに伝えるのが最善です。
4 税理士を変更する前にやるべき3つのステップ
税理士変更は一大決断ですが、感情や勢いだけで進めると後悔する可能性もあります。
変更前には以下のステップをしっかりと踏むことが重要です。
ステップ①:不満を明確化する
「なぜ変えたいのか」を自分の言葉で整理することから始めましょう。
下記のように、具体的な出来事と気持ちをセットで書き出すのが効果的です。
例:「節税の相談をしたが、『それはやめておいた方がいい』とだけ言われ、代替案も提示されなかった」
→「提案型のサポートが欲しい」
このように、「求める税理士像」を明確化することが、新たな出会いの精度を高める第一歩になります。
ステップ②:一度、要望を伝えてみる
変更を考える前に、今の税理士に不満や要望を率直に伝えることも選択肢の一つです。
特に税理士法人のように複数スタッフがいる事務所では、担当者の変更だけで関係性が改善する場合もあります。
ステップ③:新しい税理士が見つかるまで解約しない
「次が決まるまで、今の税理士を解約しない」——これは極めて重要な原則です。
すぐに解約してしまうと、税務署対応・決算準備など、緊急時に手が打てなくなるリスクがあります。
また、複数の税理士と面談してみることで、意外にも「今の税理士の良さ」に気づくケースもあります。
5 税理士変更の伝え方は「感謝+前向きな理由」が基本
税理士変更を円滑に進めるには、「伝え方」が最重要です。
✔ 結論:
関係を壊さず、前向きな理由で伝えることが鍵です。
✔ 理由:
税務調査や過去資料の確認など、変更後も旧税理士に依頼する場面があるためです。
✔ 伝え方の一例:
「これまで大変お世話になりました。今後の事業展開を見据え、別の視点を持つ税理士の方と取り組んでみたいと考えております。今後ご相談させていただく場面もあるかと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。」
相手の貢献に感謝しつつ、経営判断としての変更であることを明確にしましょう。
6 税務調査があった場合、変更前の税理士は関与する?
税理士変更後に税務署から連絡があった場合、「今の税理士がすべて対応してくれるのか?」と不安になる経営者も少なくありません。
基本的には「新しい税理士が対応」
税務調査は、あくまで「現在の納税者(=あなた)」に対して行われるものであり、顧問税理士は代理人として同席・対応します。
したがって、変更後であっても、新しい税理士がすべての窓口となり、立ち会いや交渉を担当するのが一般的です。
過去の処理に関して聞かれることもある
ただし、調査対象が変更前の決算期間にかかる場合、過去の処理内容について税務署から質問されることがあります。
このとき、旧税理士がどのような説明を行っていたか、またはどのような根拠資料があったかを把握する必要があります。
そのため、税理士変更の際には、旧税理士との関係を悪化させないことが非常に重要です。
7 顧問契約時に確認すべき5つのポイント
税理士を変更したあとは、新たな契約条件の確認が欠かせません。
✔ 結論:
顧問料・業務範囲・契約条件を曖昧にしないことが、後悔を防ぐポイントです。
① 顧問料:サービス内容とのバランスが重要
訪問頻度、月次報告、経営分析などの有無で金額は大きく変わります。
② 決算料・申告報酬:一式の中身を必ず確認
地方税や消費税、電子申告の費用が含まれているかをチェック。
③ 会計入力(記帳):原則、自社対応が基本
当事務所では、経営者自身が数字を把握する体制を推奨しています。
そのため記帳代行は行わず、クラウド会計の活用とレビュー支援に特化しています。
④ 税務調査・節税相談の対応範囲
調査の立ち会いや経費処理アドバイス、融資支援、相続税相談など、
どこまでが顧問契約に含まれるかを明確にしましょう。
⑤ 解約・更新条件:後トラブルの火種に注意
通知期限、自動更新の有無、データ引き継ぎ条件など、契約書で必ず確認。
「確認しづらい雰囲気」のある税理士は要注意。
内容を明確に説明し、質問にしっかり答えてくれる税理士こそ信頼できます。
8 税理士を変えて、経営が息を吹き返した話
ここでは、実際に税理士を変更された富士市のある小売業者の事例をご紹介します。
「売上は伸びているのに、利益が残らない」──見えない課題に悩んでいた日々
創業から10年目を迎えていた小川さん(仮名)は、売上は年々伸びているにもかかわらず、資金繰りに追われ、利益がほとんど残らない状態に悩まされていました。
顧問税理士に相談しても、「節税はしていますよ」「この調子でいきましょう」と曖昧な返答が続き、経営の視界が開けることはありませんでした。
そんなとき、異業種交流会で出会った経営者仲間から「税理士を変えてから資金繰りが劇的に改善した」という話を聞き、小川さんは一歩を踏み出します。
税理士変更後、「利益構造の再設計」が始まった
新しい税理士は、まず月次の粗利率の変動に着目し、売上構成・固定費の比率・仕入先の単価交渉余地を丁寧に洗い出しました。
また、今まで曖昧だった会計処理を精査し、原価と販管費の区別を明確化。クラウド会計でデータ共有を行いながら、翌月のキャッシュ残高予測を経営者とともに確認する体制が整いました。
結果的に、小川さんの会社では、1年で黒字転換・手元資金2.5倍という成果を実現できました。
まとめ|税理士を変えるという決断は、経営の未来を変える第一歩
税理士の変更には、確かに労力も勇気も必要です。
しかし、もし現在の税理士との関係に不安や不満を感じているなら、それは事業の再点検を促す“経営上のシグナル”かもしれません。
税理士は、単なる「申告代行者」ではなく、「経営の伴走者」です。
共に未来を見据え、数字の裏にある課題や可能性に気づき、前に進むパートナーでなければなりません。










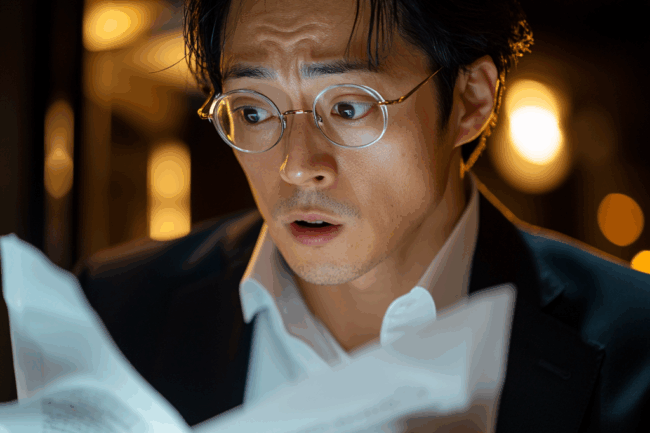

 横領行為はあってはならないものですが、発生してしまった場合には、損失の処理や損害賠償請求権の扱いなど、税務処理が非常に複雑です。事例を交えながら、どのような会計・税務対応が求められるかを見ていきましょう。
横領行為はあってはならないものですが、発生してしまった場合には、損失の処理や損害賠償請求権の扱いなど、税務処理が非常に複雑です。事例を交えながら、どのような会計・税務対応が求められるかを見ていきましょう。