こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
「まだ生まれていない子ども=胎児には相続権があるのか?」
胎児にも相続人としての権利が認められるケースがあります。本記事では、胎児の相続権について、実務上の注意点や税務処理も交えながらわかりやすく解説します。
1 民法第886条が定める胎児の相続権とは?
民法には以下のように定められています。
第一項:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第二項:前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児は生まれた場合に限り、相続開始時に「既に生まれていた」とみなされて、相続人として取り扱われます。出生が条件となるため、「停止条件付き相続権」とも呼ばれます。
胎児の権利が認められる3つの場面
民法では、胎児の権利能力が例外的に認められるのは以下の3つの場面に限定されています:
– 相続(民法第886条)
– 遺贈(民法第965条)
– 不法行為による損害賠償請求(民法第721条)
これら以外の法律行為については、胎児は権利能力を有しないため注意が必要です。
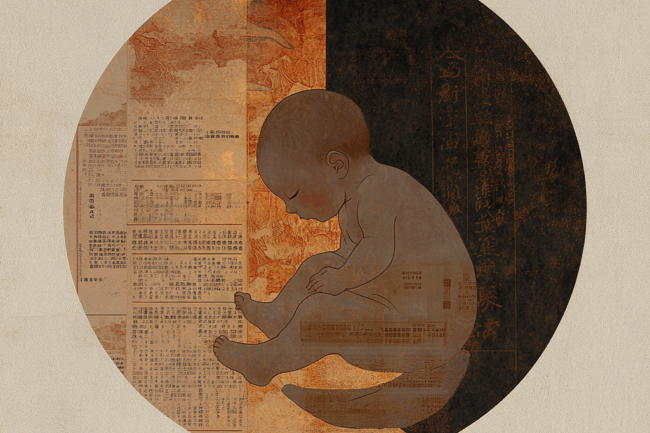
2 胎児がいる場合の遺産分割と実務上の注意点
胎児が相続人になる場合、遺産分割や名義変更の実務にも配慮が必要です。
出生前に遺産分割はできない
胎児は出生をもって相続権を取得します。出生前の遺産分割協議は無効となるため、協議は原則として出生後に行うのが実務の通例です。
特別代理人の選任が必要になることも
母親も相続人であり、かつ胎児(出生後の子)と利益が相反する場合には、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になります。
胎児が複数(双子など)の場合の注意点
胎児が双子など複数の場合、実際に何人生まれるかが確定するまで相続人の数が決まらないため、遺産分割協議はさらに慎重な対応が求められます。また、一部が死産となった場合、生存した胎児のみが相続人となります。
遺産分割協議書の作成タイミング
胎児の出生前に特別代理人を選任して遺産分割協議を行うことも法的には可能ですが、死産となった場合は協議が無効となるリスクがあるため、実務上は出生後の手続きが推奨されます。
3 胎児がいる場合の相続税申告の扱い
胎児がいると、法定相続人の数に影響が出るため、相続税の基礎控除額も変わります。
● 申告期限内に出生した場合
胎児が申告期限内(被相続人の死亡から10か月以内)に生まれた場合は、正式に相続人としてカウントし、申告に含めます。
● 出生が申告期限後になった場合
胎児の出生によって基礎控除内に収まる場合は、税務署に申請すれば「申告期限延長(出生から2か月以内まで)」が可能です。
一方、胎児がいても課税が発生する場合は、胎児を含めずに申告し、出生後に「更正の請求」によって税額を修正・還付申請します。
申告期限延長の詳細条件
胎児の出生による申告期限延長は、以下の条件を満たす場合に認められます:
– 胎児の出生により相続人に異動が生じること
– その結果、他の相続人の取得財産額に変動があること
– 延長を求めるのは胎児以外の相続人であること
– 延長期間は最大2ヶ月間
基礎控除額の計算例
胎児がいる場合の基礎控除額の変化:
– 出生前:3,000万円 + 600万円 × 既存相続人数
– 出生後:3,000万円 + 600万円 × (既存相続人数 + 1)

4 胎児が代襲相続人になるケースもある
胎児は、通常の法定相続人だけでなく、「代襲相続人」になることもあります。たとえば、胎児の父がすでに死亡している場合に、祖父が亡くなれば、胎児は父に代わって祖父の相続人になる可能性があります。
5 まとめ:胎児がいる相続は、慎重な対応がカギ
胎児に相続権があるとはいえ、出生しなければ権利が確定しないため、相続手続きや税務申告には慎重な対応が求められます。
■出生前の協議は避ける
■出生後に特別代理人の選任が必要か判断する
■申告期限や延長の可否を確認する
■更正の請求による還付申請を視野に入れる







