こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
最近、「子ども以外に孫に財産を遺したい」というご相談が増えています。「孫の教育資金の足しにしてほしい」「子には十分与えたので、次は孫に」「老後の安心材料として遺しておきたい」──そんなお気持ちを持つ方にとって、孫への遺産相続は重要なテーマです。
しかし、注意すべきは、孫は原則として法定相続人ではないということです。対策をしないままでは、孫に財産が渡らない可能性があるのです。
本記事では、孫に財産を引き継がせるための具体的な方法と、それぞれの税務上の注意点について、富士市・富士宮市を中心に相続税申告を行う税理士として、現場で得たリアルな知見も盛り込みました。
ぜひご自身やご家族の将来設計にお役立てください。

1. 孫は相続人になれるのか?民法上の基本ルール
民法では、おおよそ、次のように法定相続人の順位が定められています。
- 第1順位:子(または代襲相続人)
- 第2順位:直系尊属(親、祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子がいる場合、その子が法定相続人となり、孫は相続人にはなりません。孫が相続人となるのは、次の2つのケースに限られます。
- 子が亡くなっている(代襲相続)
- 孫を養子にしている
そのため、子が存命中に孫に財産を相続させたい場合は、特別な手続きが必要となります。
2. 孫に財産を渡す3つの方法
2-1. 遺言書を使って遺贈する
遺言書を作成することで、孫に財産を「遺贈」することが可能です。遺贈とは、法定相続人以外の人へ財産を渡す方法で、遺言によってその意志を明確に示します。
おすすめは「公正証書遺言」です。公証人が関与し、法的な不備が起こりにくく、家庭裁判所での検認も不要です。
ただし、注意すべきは「遺留分」です。相続人(子や配偶者など)には、最低限相続できる権利があります。孫に多く遺贈しすぎると、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
また、不動産の遺贈では「不動産取得税」や「登録免許税(通常の5倍)」がかかることも、意外な落とし穴です。
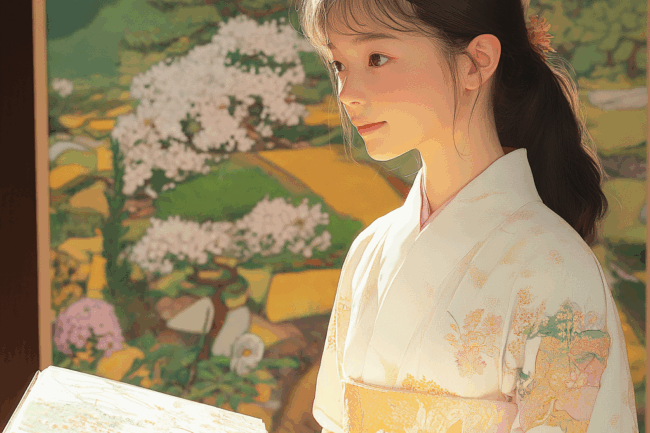
2-2. 養子縁組で法定相続人にする
孫と養子縁組を行うことで、その孫を法定相続人にすることができます。これにより、遺産分割協議に参加させたり、遺留分を確保したりすることができます。
養子縁組には、実子がいる場合は「養子1人」、いない場合は「養子2人」までという税務上のカウント制限があります。
また、孫を養子にすることで「基礎控除」が増加し、相続税が軽減されるというメリットもあります。
注意点としては、養子であっても孫である場合は「2割加算対象」となるケースがある点です(後述)。
2-3. 代襲相続で孫が相続人になるケース
子がすでに亡くなっている場合、その子(つまり孫)が「代襲相続人」として相続することが可能です。この場合、孫は法定相続人と同じ扱いになり、相続税の2割加算も適用されません。
代襲相続が発生する主なケース:
- 子が相続開始前に死亡
- 子が相続欠格・廃除された
なお、相続放棄した場合は代襲相続は発生しません。
3. 相続以外の方法で孫に資産を承継する
3-1. 暦年贈与と非課税制度
孫に対して毎年少額ずつ贈与する「暦年贈与」は、相続税対策として古くから活用されています。贈与税には年間110万円までの非課税枠(基礎控除)があり、この範囲内であれば申告も税金も不要です。
毎回、贈与契約書を作成しておきましょう。
さらに、2024年の法改正により、暦年贈与であっても相続開始前7年以内の贈与は加算対象となります(従来は3年)。相続税対策としては、早めの計画と記録の保管が重要です。
3-2. 相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母が18歳以上の孫に対して贈与する場合、「相続時精算課税制度」を選択することができます。この制度では、累計2,500万円までの贈与について贈与税が非課税になります(超えた分には20%の贈与税が課税)。
また、2024年以降の改正で、年間110万円の非課税枠が追加で設けられました。つまり、相続時精算課税を選択しても、110万円までの贈与は贈与税の申告不要で贈ることができます。
注意点として、一度この制度を選択すると、暦年課税方式には戻れません。また、贈与者の死亡時には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
3-3. 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与
孫の教育資金や結婚・子育て資金を目的とした贈与については、特例として非課税となる制度があります。
- 教育資金一括贈与:最大1,500万円まで非課税
- 結婚・子育て資金一括贈与:最大1,000万円まで非課税
いずれも金融機関を通じて信託契約を結び、領収書などで支出の使途を証明する必要があります。余った資金については、一定年齢に達すると課税対象となることに注意しましょう。
3-4. 生命保険の活用
被相続人が孫を生命保険の受取人に指定しておけば、死亡後すぐに保険金を受け取らせることができます。
生命保険の非課税枠は、法定相続人1人につき500万円です。相続人としてカウントされる孫(養子や代襲相続人)であれば、その分非課税枠が増えることになります。
ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税・贈与税・所得税と課税区分が変わります。契約内容の設計には十分な注意が必要です。

4. 税務上の注意点と落とし穴
4-1. 相続税の2割加算ルール
相続人ではない孫が相続・遺贈により財産を取得した場合、原則として相続税額が2割増しになります(相続税法第18条)。
ただし、以下のケースは加算対象外となります:
- 代襲相続により相続した孫
- 養子縁組により法定相続人となった孫(要件による)
遺言で遺贈した場合などは2割加算が避けられないと思っておいてください。
4-2. 生前贈与の7年以内加算と例外
2024年の税制改正で、生前贈与の加算期間が「相続開始前3年以内」から「7年以内」に拡大されました。相続税対策として贈与を行う場合は、早めの開始が肝心です。
もちろん、この場合は、祖父母が長生きすることが一番の相続対策となります。
一方で、贈与先が法定相続人でない孫である場合、原則としてこの加算対象とはなりません。つまり、子を飛ばして孫に早めに贈与すれば、加算を回避できる可能性があります。
ただし、孫を養子にした場合や代襲相続人となった場合は、加算対象になります。孫が「法定相続人」となると、加算対象に引き込まれる点に注意が必要です。
この点は非常にややこしいので、祖父母が高齢の場合の孫への贈与は、税理士とよく相談のうえ実行しましょう。
4-3. 養子縁組の基礎控除と税務リスク
養子を加えることで相続税の基礎控除が増加しますが、税務署は「節税目的の養子縁組」を否認するケースもあります。
- 被相続人が高齢・認知症
- 養子縁組の意思が不明確
- 実態のない戸籍上の養子縁組
こうした事情がある場合、課税庁側から「無効」と主張されることも。慎重な対応が必要です。
5. 富士市・富士宮市の相続事情と当事務所の支援体制
富士市・富士宮市では、農地や自宅を所有している高齢者が多く、「不動産の承継」が相続対策の主な課題となります。特に二世帯同居・三世代家族が多い地域では、「孫への承継ニーズ」も高くなっています。
また、近年の地価上昇や固定資産税評価額の見直しにより、思った以上に相続税がかかるケースもあります。
地域密着型の税理士事務所として、富士地域の不動産・家族構成に応じたオーダーメイドの相続税対策をご提案しています。

6. まとめとアドバイス
孫に財産を遺すには、事前の準備が欠かせません。
- 遺言書の作成による「遺贈」
- 養子縁組による「法定相続人化」
- 子の死去を前提とした「代襲相続」
- 生前贈与や保険など「相続以外の方法」
それぞれの方法にメリットと注意点があり、どれが最適かはご家庭の状況によって異なります。また、税制は毎年のように変わるため、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
「孫に資産を遺したい」「今のうちに贈与しておきたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。富士市・富士宮市の皆さまにとって、最適な相続の準備をご一緒に考えてまいります。






