こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。
今回は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」について解説します。特に、「孫が相続人になるケース」「甥・姪が相続人になる場合」「相続税における取り扱い」など、実際の相続に関係する具体的な論点もお伝えします。
1.代襲相続とは?よくある誤解と基本の整理
「孫が相続人になることはありますか?」
この問いは、民法に規定された「代襲相続」という制度と深く関係しています。
「代襲相続」とは、本来相続人になるべき人が既に死亡していたり、法律上の理由で相続権を失っていた場合に、その人の子や孫が代わって相続人となる制度です。
この制度があることで、家族のつながりや世代を超えた財産の承継が、ある程度スムーズに行われるよう法律的に整備されています。
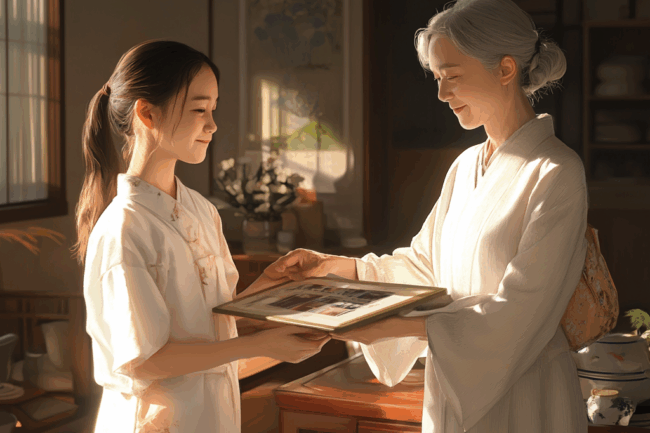
2.子が死亡した場合の代襲相続|直系卑属の継承
子が死亡している場合、孫が相続人に?
代襲相続の典型的な例が、「被相続人の子が既に亡くなっている場合」です。この場合、その亡くなった子の子、つまり孫が「代襲相続人」として財産を相続することになります。
代襲相続が発生するケースと発生しないケース
| ケース | 代襲相続の有無 | 代襲相続人 |
|---|---|---|
| 子が死亡している | ○ | 孫(子の子) |
| 子が相続欠格 | ○ | 孫 |
| 子が廃除されている | ○ | 孫 |
| 子が相続放棄している | × | なし(放棄は代襲の対象外) |
ポイントは、「相続放棄」は代襲相続を発生させないということです。放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされ、子ども(孫)にも権利は引き継がれません。
また、子の子(孫)でもさらに亡くなっていた場合には、その次の代(ひ孫)へと代襲が続く「再代襲」も直系卑属には認められています。
3.兄弟姉妹の代襲相続|甥や姪が相続人になる場合
被相続人に子や親(直系尊属)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。そして、その兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人になります。
ただし、ここで注意が必要です。
兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」です。つまり、甥・姪の子ども(被相続人から見れば大甥・大姪)は相続人になれません。
まとめると:
兄弟姉妹が死亡していた場合 → 甥・姪が代襲相続人になる
甥・姪が死亡していた場合 → その子には代襲相続権はない(再代襲なし)
この制限は、直系(子→孫→ひ孫)とは大きく異なる点です。
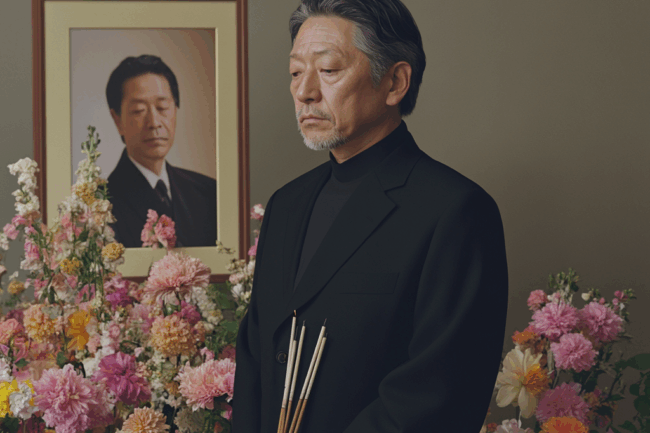
4.代襲相続人の相続分はどう決まるのか?
代襲相続人が取得する相続分は、基本的に「被代襲者(本来の相続人)」の法定相続分をそのまま引き継ぐ形になります。
具体例でみてみましょう
被相続人に2人の子がいたとします。長男が相続開始前に死亡しており、長男には子(孫)が2人います。
次男 → 相続分1/2
孫2人 → 1/2を等分 → 1/4ずつ
つまり、被代襲者に複数の子(孫)がいる場合、その法定相続分をさらに均等に分ける仕組みです。
この計算方法は、実際の遺産分割協議や相続税の申告において非常に重要になります。
5.代襲相続人と遺留分の関係
「代襲相続人にも遺留分があるのか?」という疑問を持たれる方も少なくありません。
① 直系卑属(孫・ひ孫)の場合
孫やひ孫が代襲相続人となるケースでは、民法上の遺留分権利者とされており、一定の最低限度の相続分が保障されています。
例えば、被相続人が遺言によってすべての財産を第三者に遺贈したとしても、孫が代襲相続人であれば、遺留分侵害額請求を行うことができます。
② 甥・姪の場合
一方で、甥や姪が代襲相続人になった場合には、遺留分の権利は認められていません。つまり、被相続人がすべての財産を他人に遺贈していても、遺留分侵害額請求はできないということです。
6.相続税の2割加算|代襲相続人にも適用される?
相続税法では、相続人のうち特定の者に対して、相続税額に2割を加算する制度があります。
どんな人が2割加算の対象になる?
原則として、相続人が次のどちらにも該当しない場合に、2割加算の対象になります。
被相続人の一親等の血族
被相続人の配偶者
代襲相続人の取り扱いは?
| 代襲相続人 | 相続税の2割加算の有無 |
|---|---|
| 孫(子の子) | なし |
| 孫養子 | あり(実子ではないため) |
| 甥・姪 | あり(親等が離れているため) |
たとえば、孫が被相続人の養子となっている場合には、一親等の血族には該当しないとされ、2割加算の対象となってしまいますので要注意です。
7.代襲相続は「つながり」を守る制度
代襲相続は、世代を超えて家族の財産を承継していくための大切な仕組みです。
一方で、制度の理解が不十分なまま相続を進めてしまうと、「本当は相続できたはずの人が漏れてしまった」「想定外の税負担が発生した」といった事態にもなりかねません。
富士市・富士宮市をはじめとする地域の皆さまが、安心して相続を迎えられるよう、正確な知識と丁寧なサポートを提供してまいります。






