こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
親や祖父母から財産を譲り受ける「贈与」。お金や土地、不動産をもらったとき、「税金はかかるの?」「申告は必要?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、贈与税の基本的なしくみから、課税の方法、税率の計算、非課税となる特例制度まで、贈与税に関する知識をわかりやすく解説します。
1 贈与税とは?誰に、いつ課されるの?
贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で渡したときに、財産を「もらった側」が負担する税金です。
課税されるのは誰?
贈与税の納税義務者:財産をもらった「受贈者」
課税対象:個人から個人への贈与(法人は対象外)
たとえば、親から子へ、祖父母から孫へ不動産や現金を贈与した場合、もらった側に贈与税がかかる可能性があります。
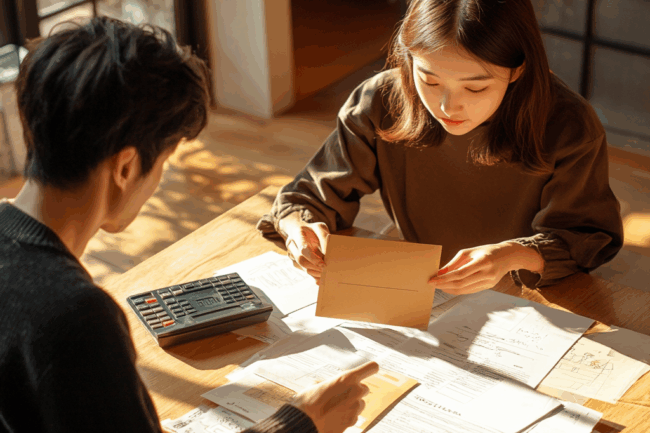
2 贈与税の課税方式と基礎控除
贈与税は、原則として「暦年課税方式」により課税されます。
暦年課税方式とは?
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額に応じて、贈与税を計算します。
基礎控除額(非課税枠)
贈与税には年間110万円の「基礎控除」があります。つまり、1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
3 贈与税の計算方法と税率
贈与税は、「基礎控除後の課税価格」に対して累進税率が適用されます。
特例税率 vs 一般税率
受贈者の年齢と贈与者との関係によって、適用される税率が異なります。
| 適用条件 | 税率 | 適用されるケース |
|---|---|---|
| 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与 | 下掲の表(特例税率) | 特例税率が適用される |
| 上記以外(兄弟姉妹間、配偶者間、未成年への贈与など) | 下掲の表(一般税率) | 一般税率が適用される |
🔵 特例税率(直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
🔴 一般税率(上記以外の贈与すべて)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
計算例:特例税率が適用されるケース
贈与額:600万円
基礎控除:110万円
課税価格:490万円
税率:20%、控除額:30万円
4 非課税となる贈与とは?
贈与税がかからないケースもあります。次のような贈与は、条件を満たせば非課税となります。
1. 生活費や教育費
必要な都度、生活費や学費を贈与した場合、贈与税はかかりません。ただし、まとめて一括で渡すと課税対象となることがあるため注意が必要です。
2. 教育資金一括贈与の特例(最大1,500万円非課税)
30歳未満の子や孫の教育資金を一括贈与する場合、専用口座と手続きによって最大1,500万円まで非課税にできます。
3. 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円非課税)※期限終了に注意
5 贈与税の申告・納付はいつまで?
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の 2月1日から3月15日 までです。
贈与税の申告が必要な場合:110万円を超える贈与を受けたとき
贈与税の納付期限も申告期限と同じ
期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生するため、早めの準備が肝心です。
6 贈与税を巡るトラブルを防ぐには?
名義預金とみなされるケースに注意!
「孫名義の通帳に入金したけど、通帳・印鑑は祖父母が管理していた」などの場合、贈与とは認められず、相続税の対象となる恐れがあります。
贈与契約書を作成しましょう
贈与は「契約」です。贈与者と受贈者の意思確認を記録するためにも、贈与契約書を作っておくことをおすすめします。







