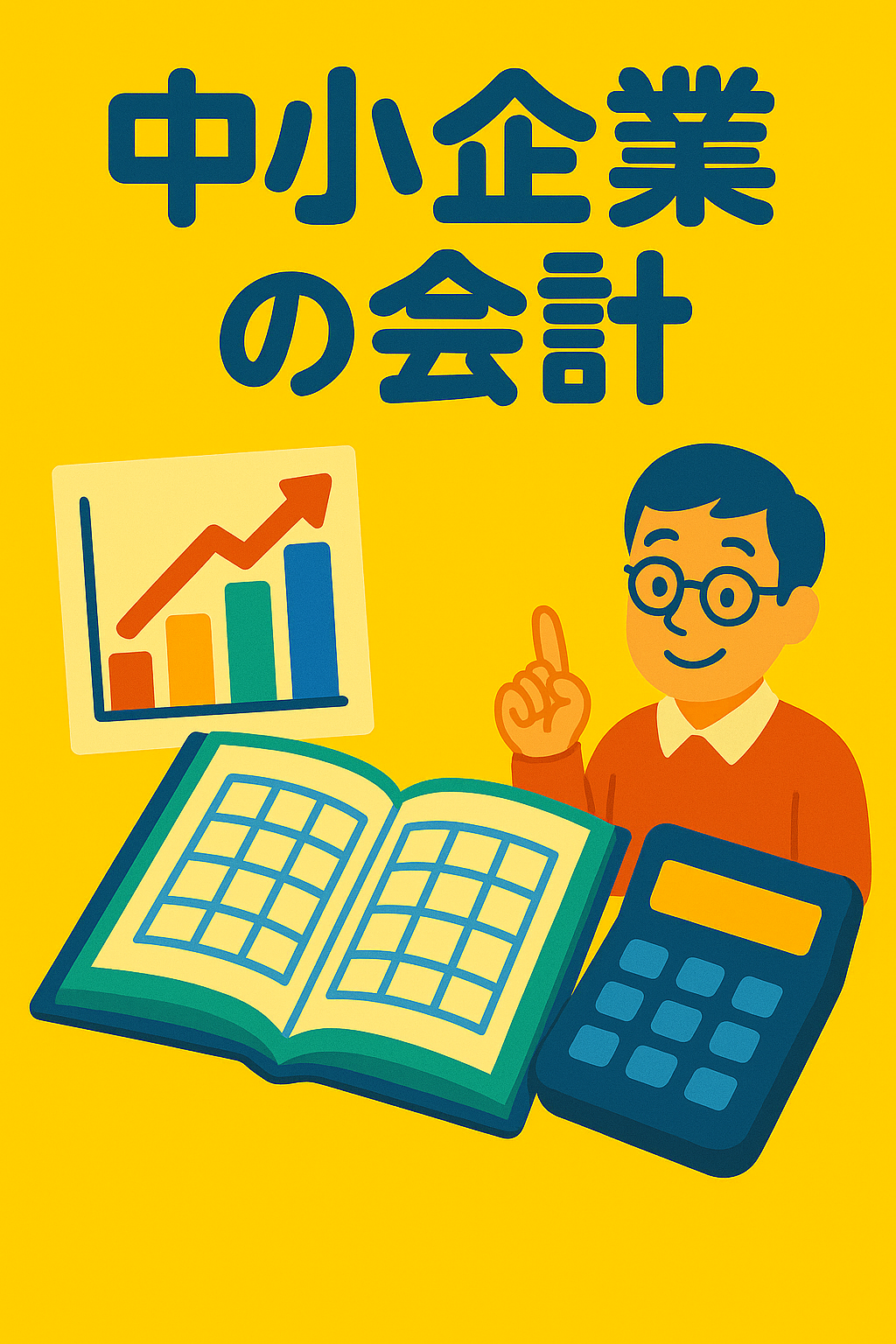目次 1. 源泉所得税とは? 2. 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 3. 実際の源泉徴収税額の計算方法 4. 消費税の取り扱い 5. 納付手続きと期限 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。報酬や謝礼を支払う際、「源泉徴収って必要?」「計算方法は?」といった疑問を抱える経理担当者の方も多いのではないでしょうか? 本記事では、報酬・料金に関する源泉徴収の対象・計算方法・納付手続きまで解説します。 1 源泉所得税とは? 源泉所得税とは、特定の支払(報酬、給与など)から所得税等をあらかじめ差し引いて、支払者が国に納める制度です。税収の安定確保と、納税者の税負担の平準化が目的とされています。 2 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 源泉徴収が必要かどうかは、支払を受ける側が個人か法人かで異なります。 今回は個人の場合について解説します。…