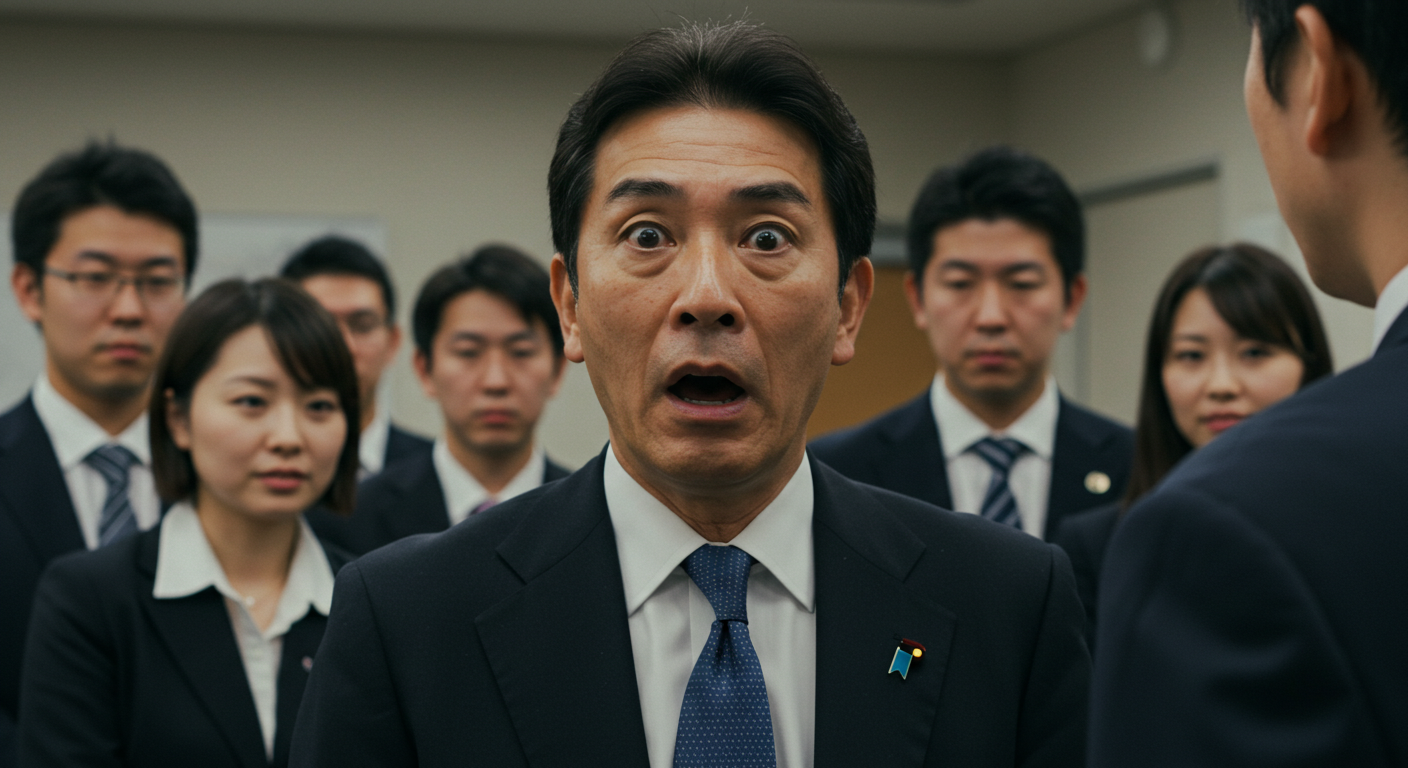こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 個人で事業を営んでいる方で、事業が軌道に乗ってくると「法人成り(ほうじんなり)」、つまり会社を設立して個人事業から法人へ切り替えることを検討される方も多いのではないでしょうか。法人化を検討する大きな理由の一つに「節税」が挙げられます。 では、なぜ法人化が節税に繋がると言われるのでしょうか?それは、個人が納める「所得税」と法人が納める「法人税」では、その税率の仕組みが大きく異なるためです。 今回は、個人の所得税率と普通法人の法人税率を比較し、法人化による税負担への影響について解説します。 📌 目次 第1章|個人の所得税率は「超過累進課税制度」 第2章|法人税は比例税率が基本 第3章|どこからが節税になるライン? 第4章|法人化のその他の影響 第5章|まとめ:法人化は総合的な視点で判断を 第1章|個人の所得税率は「超過累進課税制度」 日本の所得税は、"超過累進課税制度" を採用しています。これは、所得金額が増えるほど税率が高くなる仕組みです。 課税所得金額 税率 195万円以下 5% 195万円超330万円以下 10%…