こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
「副業収入って雑所得?それとも事業所得?どっちで申告すればいいの?」
というものです。
この問題に関連して、かつて話題となったのが、「副業300万円問題」。
実際に国税庁が方針を出したあと、大幅な修正が加えられました。
本記事では、その背景と最新のルール(帳簿の作成の有無による判定)を、解説します。
1 副業収入の区分がなぜ重要なのか?
副業収入が「事業所得」になるのか「雑所得」になるのかで、適用される税制や節税の余地が大きく異なります。
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 事業所得 | ・青色申告が可能 ・赤字は他の所得と損益通算・繰越控除が可能 ・帳簿や届け出が必要(開業届・青色申告承認申請書など) |
| 雑所得 | ・原則として白色申告 ・赤字は他の所得と通算できない(損益通算不可) ・収入が臨時的・副業的な性質の場合に分類されやすい |
この「区分」の判断が曖昧だったため、国税庁が一定のルールを設けようとしたのが「300万円問題」の始まりです。
2 かつて物議を醸した「300万円基準案」
2022年8月、国税庁は以下のような改正案を公表しました。「副業収入が300万円以下かつ主たる所得でない場合、原則として雑所得とする」
この案は、多くの反発を受けました。
その結果、国税庁はわずか2ヶ月後の2022年10月に方針を大きく修正することとなります。
3 改正後の新ルール|ポイントは「帳簿の有無」
現在の判断基準では、収入金額ではなく、「帳簿書類の保存の有無」が重要となります。
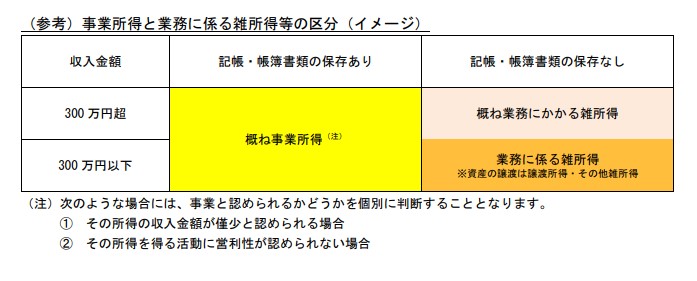
(出典:国税庁)
改正後の新ルール|ポイントは「帳簿の有無」と「その他の要素」
帳簿ありの場合:
・原則として「事業所得」として取り扱い
・ただし、以下の場合は雑所得とされる可能性:
① その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合
② 収入金額が僅少と認められる場合(概ね300万円以下の年が3年程度続き、かつ、その所得がその者の主たる所得でない場合)
③ その所得を得る活動に営利性が認められない場合(例:収支相償の状況が続いている場合)
帳簿なしの場合:
・原則として「雑所得」
・ただし、その所得を得る活動が事業と認められる場合(例:収入金額が高額である場合)は事業所得
重要な注意点:
帳簿があることは事業所得の必要条件であって、十分条件ではありません。帳簿があっても上記②③に該当すれば雑所得となる可能性があります。
具体的な判定例:
事業所得と認められやすいケース:
- ■継続的・反復的な収入がある
- ■相当の時間・労力を費やしている
- ■営利性・有償性が認められる
- ■社会的地位として事業を行っている
- ■帳簿書類を適切に保存している
雑所得と判定されやすいケース:
- ■一時的・偶発的な収入
- ■片手間・趣味の延長的な活動
- ■営利性に欠ける(継続的な赤字)
- ■帳簿書類の保存がない
- ■主たる所得に比べて収入が僅少
4 なぜ事業所得にしたい人が多いのか?
事業所得として申告する最大の理由は、税制上のメリットが多いからです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 正規の帳簿付けと期限内申告により、 最大65万円(電子申告等)の所得控除が可能 ※簡易帳簿・紙提出でも10万円控除あり |
| 赤字の繰越控除 | 事業の赤字が出た場合、 翌年以降3年間の黒字と相殺可能(繰越控除) |
| 損益通算 | 赤字が出た年でも、 給与所得や不動産所得などと相殺できる(節税効果あり) |
このような制度を不正利用して、あえて赤字事業を装い損益通算を行うケースも多かったため、今回の見直しが行われたといえます。
【参考コラム】
5 副業収入を事業所得で申告したい場合の対策
副業収入を事業所得で申告したい場合の総合的な対策:
基本的な準備:
1. 適切な帳簿の作成と保存
2. 開業届・青色申告承認申請書の提出
3. 売上・経費の根拠資料の整備
4. 継続的・反復的な取引の実態作り
営利性の向上:
- ■赤字が続く場合は改善計画の策定
- ■広告・宣伝活動の記録
- ■スキルアップ・設備投資の実行
- ■市場調査・営業活動の記録
注意点:
- ■形式だけでなく実質的な事業性が重要
- ■税務調査で説明できる体制の構築
- ■専門家による定期的なチェック
結論:
単に帳簿をつければ事業所得になるわけではありません。継続性、営利性、社会的地位等を総合的に満たし、適切な記録を残すことが重要です。







