こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
事業で使用するパソコンや什器などの資産を購入した際、一定額以上であれば通常は「減価償却」によって数年かけて経費化します。しかし、取得価額が比較的少額の固定資産については、購入した年に全額を経費にできる特例制度が用意されています。
本記事では、中小企業や個人事業主が活用できる3つの少額減価償却資産の特例について、それぞれの制度概要、適用条件、メリット・デメリットを解説します。
1 10万円未満の少額減価償却資産:誰でも使える基本の特例
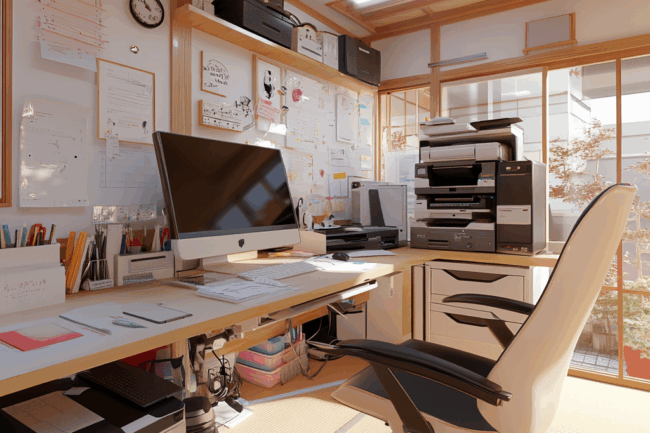
制度の概要
取得価額が10万円未満の資産は、購入年度に全額を即時に経費計上できます。
特徴
10万円未満の少額減価償却資産の税務上の取扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業・大企業問わずすべての事業者 |
| 経理処理 | 消耗品費または減価償却費で処理 |
| 年間限度額 | なし(件数制限なし) |
| 添付書類 | 申告書等への添付不要 |
| 償却資産税 | 非課税(固定資産税の対象外) |
| 貸付資産 | 原則除外(ただし、事業の主要目的に供する場合は対象) |
2 30万円未満の特例:中小企業向けの強力な即時償却制度
 制度の概要
制度の概要
30万円未満(※)の資産は、購入した年度に全額を損金算入できます。中小企業支援のための制度です。
※30万円未満という金額に消費税が含まれるかどうかは、経理処理の方法によって変わります。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 青色申告をしている中小企業者・個人事業主 (資本金1億円以下などの要件あり) |
| 年間限度額 | 300万円(12ヶ月の事業年度基準) ※期首取得・合計で判定 |
| 添付書類 |
|
| 償却資産税 | 課税対象(固定資産税として申告必要) |
| 貸付資産 | 原則除外 ただし、事業の主たる目的で使用するリース資産等は例外 |
ポイント
■即時償却により、利益が出ている年度の節税に有効
■年間限度超過分は減価償却で処理が必要
3 20万円未満の一括償却資産:費用を3年間で分割
制度の概要
20万円未満の資産をまとめて取得し、3年間で均等償却する制度です。全額を初年度に落とす必要はなく、費用を分散できます。
特徴
一括償却資産の税務上の取扱い(10万円以上20万円未満)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | すべての法人・個人事業主が対象(中小企業に限られない) |
| 償却方法 | 取得価額 ×(事業年度の月数 ÷ 36) を毎年償却(3年均等償却) |
| 添付書類 | 法人税申告書別表十六(八)などへの記載が必要 |
| 償却資産税 | 非課税(固定資産税の対象外) |
| 貸付資産 | 原則除外(例外なく対象外) |
ポイント
■個別管理不要、資産を合計して一括処理
■償却資産税回避を重視する場合に有利
4 中小企業が選ぶべき特例はこれ!
取得価額ごとに最適な選択肢を選ぶことで、節税効果を最大化できます。
取得価額ごとのおすすめ減価償却特例と選定理由
| 取得価額 | おすすめの特例 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 10万円未満の即時償却 | 制限なし・書類不要・その年に全額費用化が可能 |
| 10万~20万円未満 | 状況に応じて選択 | 利益があるなら30万円未満特例 赤字なら一括償却資産による分散処理が有利 |
| 20万~30万円未満 | 30万円未満の特例 | 中小企業限定/年間300万円まで即時償却が可能で節税効果大 |
5 制度選択の注意点と申告の実務
■特例の要件を満たさないと税務調査で否認リスク
■貸付資産の扱いや消費税の計算方法に注意
■正確な台帳管理・申告書添付が必須
■繰越欠損金がある場合は即時償却の節税効果が薄れる可能性も







