こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
今回は、令和元年の民法改正により新設された「特別寄与料」と、その支払いに伴う相続税の課税関係について詳しく解説します。
1 そもそも「特別寄与料」とは?
被相続人の介護や看護など、無償で長年にわたって尽力した親族がいた場合、その労務提供に見合う財産的な対価を「特別寄与料」として請求できる制度が、令和元年7月1日より施行されました。
これにより、相続人でない親族(例:長男の妻など)であっても、相続において金銭請求ができるようになった点が大きなポイントです。
特別寄与料の金額はどう決まる?
特別寄与料の金額は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます:
- 労務提供の期間・頻度・内容
- 被相続人の介護度や必要性の程度
- 専門業者に依頼した場合の費用相当額
- 相続財産の総額に対する割合
実際の金額算定では、介護期間×日当×寄与度といった計算式が用いられることが多く、日当は地域の介護報酬単価(時給1,000円程度)を参考にするケースが一般的です。
請求期限に注意
特別寄与料の請求は、相続開始を知った時から1年以内に行う必要があります。この期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、該当する方は早めの行動が重要です。
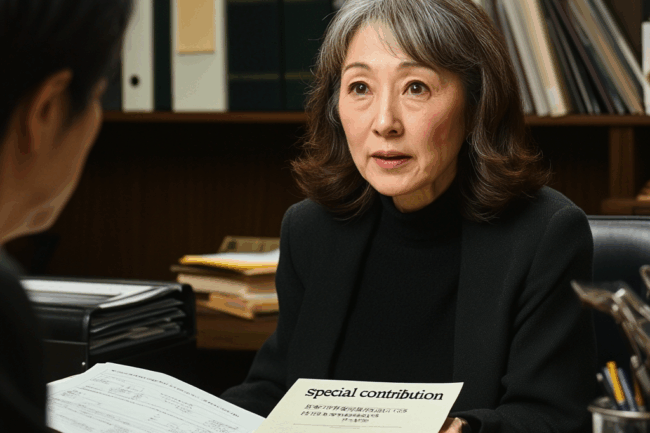
特別寄与料が認められる要件
- ■被相続人の親族であること(民法第1050条)
- ■被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務提供を行っていたこと
- ■相続人との間で協議が成立するか、家庭裁判所の審判で認定されること
2 特別寄与料と相続税の課税関係
特別寄与料は「遺贈」とみなされる
特別寄与者が相続人から金銭を受け取る場合、その金額は「遺贈により取得したもの」として扱われます(相法4条2号)。したがって、相続税の課税対象となります。
ただし、以下のように税務上の取り扱いには独自の論点があります。
① 特別寄与料の支払者と取得者の関係
■相続人が負担して支払った場合 → 特別寄与者が被相続人から遺贈を受けたとみなす
■被相続人の遺産分割の一環で支払われた場合 → 各相続人の取得財産が減額される形で調整
② 課税対象の金額
■特別寄与料の額が確定すると、その金額は特別寄与者が「遺贈により取得した金額」として、相続税申告書に記載する必要があります。
③ 具体的な計算例
【設例】
被相続人:父(相続財産5,000万円)
相続人:長男、次男
特別寄与者:長男の妻(特別寄与料300万円を取得)
この場合の相続税計算:
- ■長男の妻:300万円を遺贈により取得→相続税の課税対象
- ■長男・次男:各自の相続分から特別寄与料分を控除した金額が課税対象
税額軽減の特例について
特別寄与者が被相続人の配偶者や一親等の血族でない場合、相続税額が2割加算される点にご注意ください。長男の妻などは通常この対象となります。
3 課税時期と申告期限の注意点
特別寄与料の支払額が協議または審判で確定した場合には、確定日から10ヶ月以内に申告する必要があります(相法29条、基通29-1)。
特例:相続税申告後に確定した場合
■更正の請求や修正申告により、税務処理をやり直す必要があります(相基通32-1)。
実務上よくあるトラブル
- ■協議がまとまらず調停・審判に移行するケース
- ■特別寄与料の支払いが分割払いになる場合の税務処理
- ■他の相続人が支払いを拒否する場合の対応策
これらの問題を避けるためには、生前から家族間での話し合いや、遺言書での明記を検討することが効果的です。
まとめ
特別寄与料は、家族による献身的な介護や労務に正当な評価を与える仕組みです。ただし、相続税の課税関係が発生するため、専門的な税務判断が不可欠です。







