こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
相続が発生した際、「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決めることを遺産分割協議といいます。そして、その結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。
この協議書は、預金の解約や不動産の相続登記、相続税申告などに必要不可欠な書類です。この記事では、遺産分割協議書の基礎から作成手順、注意点、やり直しのリスクまでを詳しく解説します。
1 遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。
被相続人に遺言書がない場合や、遺言に書かれていない遺産がある場合には、法定相続人全員の合意によって協議を行う必要があります。
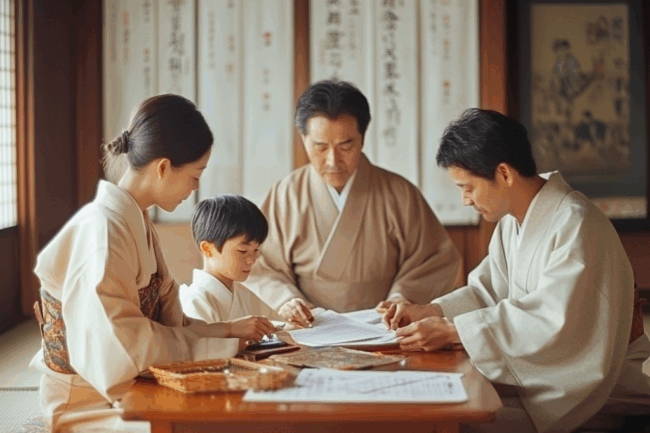
協議が必要となる主なケース
- 遺言がない
- 遺言書が無効、または内容を変更したい
- 遺言に記載されていない遺産が見つかった
- 法定相続分とは異なる分け方をしたい 等
協議を始める前の必須準備
遺産分割協議を開始する前に、以下の準備が不可欠です:
相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人を漏れなく確定します。隠し子や養子縁組の存在が後で判明すると、協議が無効になる可能性があります。
相続財産の調査:
– 不動産:登記事項証明書、固定資産税納税通知書で確認
– 預貯金:通帳、キャッシュカード、郵便物等から全口座を特定
– 有価証券:証券会社からの郵便物、電子交付サービス等で確認
– 負債:信用情報機関への照会、借用書、契約書等で確認
相続財産の評価:不動産は固定資産税評価額や路線価、動産は時価で評価し、分割の基準を明確にします。
2 遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、協議の結果を文書化した「法的証拠」として機能します。これを作成することで、相続人全員の合意内容が明確になり、後々のトラブル防止に役立ちます。
3 遺産分割協議書の記載方法と構成
法定様式はありませんが、正確性と客観性が重要です。
記載すべき主な項目
被相続人と相続人の情報(氏名、続柄、住所、生年月日)
分割対象の遺産の内容と承継先
不動産:登記事項証明書の内容を正確に記載
預貯金:金融機関名、支店、口座番号など
有価証券:銘柄名、保有口数、証券会社など
負債:債権者名、契約内容、残高など
財産の特定方法
各財産は以下のように正確に特定して記載する必要があります:
不動産:「所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積」を登記事項証明書と完全一致させる
預貯金:「金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人」を通帳等で確認して正確に記載
有価証券:「銘柄名、保有口数、証券会社名、口座番号」を具体的に記載
曖昧な記載は金融機関や法務局で手続きが受け付けられない可能性があります。
分割方法の種類と記載例
現物分割:各財産をそのまま各相続人が取得(最も一般的)
代償分割:一人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う
換価分割:財産を売却して代金を分割
共有分割:複数の相続人で共有(将来のトラブルリスクがあるため推奨しない)
特別受益・寄与分がある場合
生前贈与を受けた相続人がいる場合(特別受益)や、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合(寄与分)は、その内容も明記する必要があります。
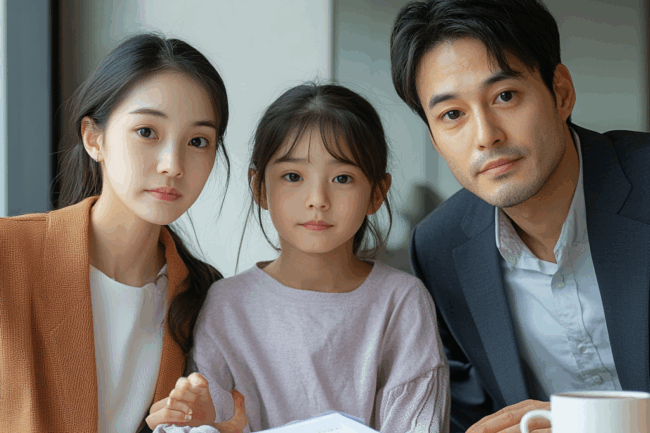
4 署名・実印・印鑑証明書の重要性
協議書の信頼性を高めるため、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
あわせて、印鑑証明書の添付も求められます。
実印:本人確認力が高く、不動産登記や預貯金解約に必須
印鑑証明書:協議書の正当性を証明する書類
複数ページの場合の注意点
協議書が複数ページになる場合は、各ページの継ぎ目に契印(割印)を押印し、文書の連続性と改ざん防止を図ります。
特別な場合の対応
未成年者がいる場合:家庭裁判所で特別代理人の選任が必要
認知症等で判断能力に問題がある場合:成年後見人の選任を検討
相続人が海外在住の場合:在外公館での証明書取得やサイン証明書が必要
印鑑証明書の有効期限
金融機関や法務局での手続きでは、印鑑証明書の発行から3ヶ月以内という期限があることが多いため、手続き直前に取得することをお勧めします。
5 遺産分割協議書の3つの効力
証拠力
→ 相続人全員の合意を証明し、将来の紛争を予防財産の承継手続きに使用
→ 銀行、不動産登記、自動車名義変更などに必要相続税申告に活用
→ 税務署に提出し、遺産の分割内容を明示する
6 遺産分割協議のやり直しはできる?
原則として、一度成立した遺産分割協議はやり直せません。ただし、以下のケースでは可能です。
相続人全員の同意が再び得られる場合
協議の無効・取消(詐欺・錯誤・一部除外など)が認められる場合
後から新たな遺産が発見された場合
やり直しの注意点
贈与税や譲渡所得税が発生する可能性あり
不動産の再登記で費用と手間がかかる
税務上の評価や申告内容も変更になる可能性がある
実務上のやり直し事例
新たな財産の発見:協議後に預金口座や不動産が見つかった場合、その部分についてのみ追加の協議が可能
相続人の除外:協議に参加しなかった相続人が後で判明した場合、協議は無効となり全面的なやり直しが必要
錯誤による協議:財産評価を大幅に間違えて協議した場合、錯誤として取り消せる可能性
やり直しを避けるための対策
– 相続人調査は必ず専門家に依頼し、漏れを防ぐ
– 財産調査は時間をかけて徹底的に行う
– 協議書作成前に相続人全員で内容を十分に確認
– 不明な点は税理士・司法書士等の専門家に相談
8 協議書作成時によくある間違いと対策
よくある記載ミス
不動産の表示誤り:登記簿謄本と一字一句違わずに記載する必要があります
預金口座の番号間違い:解約手続きで受け付けられなくなります
相続人の住所・氏名の誤記:印鑑証明書と完全一致させる必要があります
協議成立前の注意事項
協議書に署名・押印する前に相続財産を処分すると、法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。特に借金が多い場合は要注意です。
協議書の保管方法
原本は各相続人が1通ずつ保管し、コピーは必要に応じて金融機関等に提出します。紛失に備えて複数箇所での保管をお勧めします。
9 まとめ
遺産分割協議書の作成で最も重要なのは「正確性」と「完全性」です。
正確性:財産の表示、相続人情報、分割内容に一切の誤りがないこと
完全性:相続人・相続財産の調査に漏れがなく、全ての関係者が協議に参加していること
一度作成した協議書の修正は困難で、費用と時間がかかります。作成前の準備を丁寧に行い、不安な点は専門家に相談することで、円滑な相続手続きを実現できます。







