1 税務調査とは何か?その本質と種類を知る
こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
税務調査とは、税務署が申告された税額の適正性を確認するために実施する調査のことです。税目は法人税、所得税、消費税、そして相続税など多岐にわたります。
通常は任意調査であり、きちんと申告していても対象になることがあります。
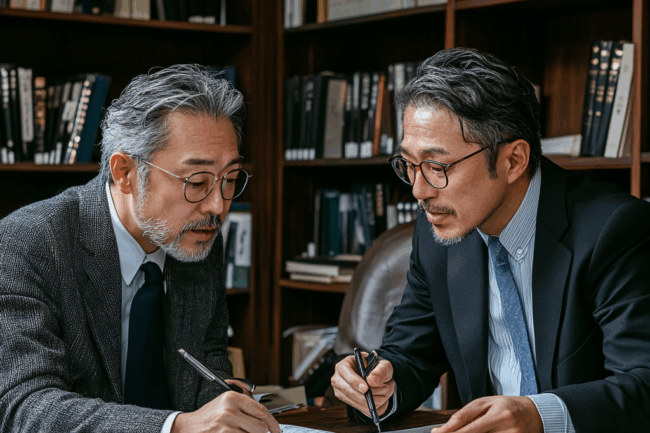
2 相続税における税務調査の特徴
相続税の申告は、複雑で金額が大きくなることが多いため、他の税目に比べて調査が入りやすい傾向にあります。
2-1. 調査の発端は「死亡届」
被相続人の死亡届は、市区町村から法務局を通じて国税庁に通知されます。その後、国税庁が運用するKSK(国税総合管理)システムにより、死亡日、資産状況、過去の申告履歴、固定資産税評価情報などが連携され、税務署は相続税の申告対象者を効率的に把握・分析しています。
2-2. 調査の確率は?
2-2. 調査の確率と最新動向
国税庁が公表した「令和4事務年度における相続税の調査の状況」によると、相続税の申告件数は約13.4万件、そのうち実地調査が行われたのは約1.0万件でした。これは、申告件数のうち約7.5%(およそ13件に1件)が調査対象となったことを意味します。
平成30年度の9.1%と比較すると調査率は低下していますが、これはコロナ禍の影響と、AIを活用した効率的な調査対象選定により、より精度の高い調査が実施されているためです。調査1件当たりの申告漏れ金額は増加傾向にあり、調査の質が向上していることがわかります。
2-3. 相続税調査の重点ポイント
税務署が相続税調査で特に重視する項目は以下の通りです:
財産の計上漏れ
- ■名義預金(配偶者や子の名義だが実質的に被相続人の財産)
- ■現金・タンス預金の把握漏れ
- ■生前贈与の認定(贈与の実態がない場合)
- ■海外財産の申告漏れ
評価額の適正性
- ■不動産の評価(路線価と時価の乖離が大きい物件)
- ■非上場株式の評価
- ■美術品・骨董品などの動産評価
債務控除の妥当性
- ■借入金の実態確認
- ■未払費用の計上根拠
- ■葬式費用の範囲
3 税務調査が来る前にできる事前準備
税務調査は突然やってくるようで、実は準備できるタイミングがあります。
3-1. 調査対象になりやすいパターン
- ■高額な財産(不動産、預貯金、有価証券など)を保有している
- ■現金取引が多い業種
- ■申告内容と第三者資料(不動産評価、銀行データなど)の齟齬
3-2. 生前からできる準備
相続税調査に備えて、生前から以下の準備をしておくことが重要です:
財産管理の明確化
- ■財産目録の作成と定期的な更新
- ■預貯金の入出金履歴の保管
- ■不動産の取得経緯や改良履歴の記録
- ■有価証券の取得価額と取得時期の記録
贈与の適正な実行
- ■贈与契約書の作成と保管
- ■贈与税申告書の確実な提出
- ■受贈者による財産の管理実態の確保
- ■振込記録などの客観的証拠の保存
事業承継対策
- ■非上場株式の評価根拠資料の整備
- ■事業用資産の区分管理
- ■役員報酬や配当政策の合理性確保
3-3. 申告時の注意点
相続税申告では以下の点に特に注意が必要です:
財産評価の根拠資料
- ■不動産鑑定評価書(必要に応じて)
- ■非上場株式の株価算定書
- ■動産の鑑定書や評価証明書
- ■海外財産の評価根拠資料
特例適用の要件確認
- ■小規模宅地等の特例の適用要件
- ■配偶者の税額軽減の適用条件
- ■事業承継税制の適用要件
添付書類の完備
- ■戸籍謄本等の相続関係書類
- ■固定資産税評価証明書
- ■預貯金の残高証明書
- ■保険証券や契約内容確認書
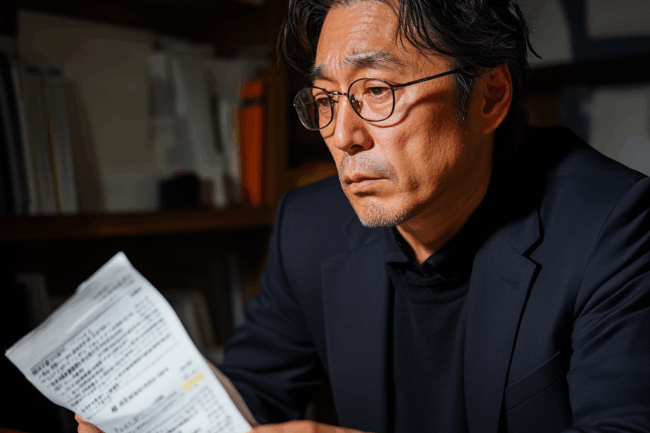
4 税務調査を受けたときの対応のコツ
4-1. 税理士の立会いは必須
調査官とのやりとりは税理士を通じて行うことがトラブル防止の鉄則です。
4-2. 素直な対応+証拠書類の整理
質問に対しては事実を簡潔に答えることが重要です。書類は調査官がスムーズに確認できるように分類しておきましょう。
4-3. 指摘内容に納得がいかない場合
税務署から更正処分を受けた場合、不服申立(異議申立・審査請求)も可能です。税理士とよく相談し、方針を決定しましょう。
4-4. 調査で問題となりやすい事例
実際の相続税調査でよく問題となる事例をご紹介します:
名義預金の認定
子や孫名義の預金でも、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合、相続財産として認定されることがあります。贈与の実態を示す証拠の保存が重要です。
生前贈与の否認
形式的な贈与契約書があっても、受贈者が財産を自由に使えない状況では贈与として認められません。贈与後の管理状況が調査されます。
現金の出所不明
被相続人の手元現金が過去の所得に比べて過大な場合、その出所について詳細な説明を求められます。現金の動きを説明できる資料の保存が必要です。
不動産評価の見直し
路線価評価と実際の取引価格に大きな乖離がある場合、財産評価基本通達6項の適用により評価額の見直しを求められることがあります。
5 まとめ 相続税の税務調査は事前対策が鍵
税務調査は「罰するため」のものではなく、「正しい納税を促す」ための制度です。調査をきっかけに、記帳や管理体制を見直すことができれば、資産管理の健全性を高めるきっかけになります。
相続税申告では、「普段の備え」と「専門家との連携」が最大の防御策です。






