こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
今回は、「退職手当金(退職金)」が相続税の課税対象になる場合と、非課税になるポイントについて、実務経験をもとにわかりやすく解説します。
「父の退職金が支払われたのですが、これも相続税に含まれるんですか?」といったご相談も多くいただいています。大切なご家族を亡くされた後の手続きで混乱しないために、正確な知識を身につけておきましょう。
1 退職手当金とは?相続税との関係
退職手当金とは、従業員が会社を退職する際に支給される金銭で、長年の勤務に対する功労の意味を持っています。
税務上、以下の2つで取り扱いが大きく異なります。
| 受け取り時期 | 相続税の取り扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 生前に受け取った退職金 | 相続税の対象外 | 被相続人の財産として計上不要 |
| 死亡後に遺族が受け取る退職金 | 相続税の対象 | 「死亡退職金」として課税 |
つまり、被相続人の死亡後に会社から支給される退職金・功労金は、「死亡退職金」として相続税の課税対象となります。
死亡退職金の範囲
以下のような支給が死亡退職金に該当します:
✅ 会社からの退職金・功労金 ✅ 役員退職慰労金 ✅ 厚生年金基金からの一時金 ✅ 企業年金の一時金 ✅ 弔慰金(一定額を超える部分)
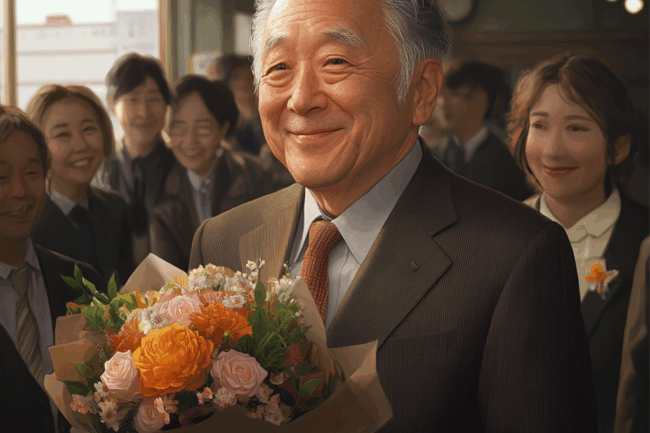
2 死亡退職金は「みなし相続財産」
死亡退職金とは、被相続人が在職中に亡くなったことにより、会社が遺族に支給する退職金や功労金等のことです。
この死亡退職金は、法律上は「相続や遺贈によって取得したもの」ではありませんが、相続税法上では「みなし相続財産」として課税対象になります
。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって生じた経済的利益のうち、一定の要件を満たすと相続税が課される財産のことです。死亡保険金や死亡退職金などがこれに該当します。
3 退職金に適用される非課税限度額
退職金にも一定の非課税限度額が設けられています。これにより、すべての退職金に相続税が課されるわけではありません。
非課税限度額は、次の計算式で算出されます。
たとえば、相続人が3人であれば、
500万円 × 3人 = 1,500万円
この1,500万円までは非課税扱いとなり、それを超えた部分のみが相続税の課税対象になります。
法定相続人の数え方
| 相続人の構成 | 法定相続人の数 | 非課税限度額 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子1人 | 2人 | 1,000万円 |
| 配偶者 + 子2人 | 3人 | 1,500万円 |
| 配偶者 + 子3人 | 4人 | 2,000万円 |
| 子2人のみ(配偶者なし) | 2人 | 1,000万円 |
重要なポイント
⚠️ 相続放棄をした人も法定相続人の数に含める ⚠️ 養子の数には制限がある(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで) ⚠️ 死亡保険金と退職金で別々に非課税枠を使える
事例1
相談者の状況:
- 富士市在住の奥様
- ご主人が地元企業に35年勤務後に死亡
- 勤務先から1,200万円の死亡退職金が支給予定
- 相続人:奥様と子2人(合計3人)
非課税限度額の計算:
500万円 × 3人 = 1,500万円結果: 支給される退職金1,200万円 < 非課税限度額1,500万円 → 全額非課税で相続税の課税対象にならない
事例2:高額退職金のケース
相談者の状況:
- 富士宮市在住の役員
- 会社から3,000万円の役員退職慰労金
- 相続人:配偶者と子1人(合計2人)
非課税限度額の計算:
500万円 × 2人 = 1,000万円課税対象額の計算:
3,000万円 - 1,000万円 = 2,000万円結果: 2,000万円が相続税の課税対象となる
事例3:複数の退職金がある場合
相談者の状況:
- 本業の会社から1,500万円
- 役員を務めていた子会社から500万円
- 合計2,000万円の退職金
- 相続人:配偶者のみ(1人)
非課税限度額の計算:
500万円 × 1人 = 500万円課税対象額の計算:
2,000万円 - 500万円 = 1,500万円

4 非課税枠を活用した相続税対策【具体例】
相談者:富士市在住の奥様
状況:ご主人が亡くなり、勤務先から1,200万円の死亡退職金が支給される予定
相続人:奥様と子2人(合計3人)
この場合の非課税限度額は以下のとおりです。
500万円 × 3人 = 1,500万円
支給される退職金が1,200万円であるため、全額が非課税となり、相続税の課税対象にはなりません。
相続税申告書には記載が必要ですが、実際の税額計算には含まれず、申告負担や納税額を軽減できます。
5 申告時に注意すべきポイント
死亡退職金が相続税の課税対象となるためには、一定の要件を満たす必要があります。その主なポイントは「支給が確定する時期」です。
相続税の対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金に限られます。
もし支給が3年を超えて確定された場合、その退職金は「相続財産」ではなく、相続人個人の「一時所得」として課税されることになります。
会社からの支給時期や通知書の発行日をしっかりと確認することが重要です。
弔慰金との区別
弔慰金にも一定の非課税限度額があります:
| 死亡の原因 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 普通給与の3年分(36ヶ月分) |
| 業務外の死亡 | 普通給与の半年分(6ヶ月分) |
超過分は退職金として課税対象になります。
申告書への記載
死亡退職金は、非課税であっても相続税申告書への記載が必要です:
- 第11表「相続税がかからない財産の明細書」に記載
- 支給金額と非課税額を明記
- 支給者の名称と住所を記載
Q1. 退職金の受給者が相続人でない場合は?
A. 相続税の対象になりますが、2割加算の適用があります。
具体例:
- 被相続人が内縁の妻を退職金受給者に指定
- 内縁の妻は法定相続人ではないため2割加算
- ただし、非課税枠は適用される
Q2. 生前に退職金の一部を受け取っていた場合は?
A. 生前受給分は相続税の対象外、死亡後受給分のみが対象となります。
注意点:
- 就業規則で退職金の分割支給が定められている場合
- 生前受給分と死亡後受給分を明確に区別する必要
Q3. 中小企業退職金共済(中退共)からの退職金は?
A. 死亡退職金として相続税の対象になります。
特徴:
- 通常、死亡後1〜2ヶ月で支給
- 3年以内の支給確定に該当
- 非課税枠の適用あり
指摘されやすい項目
1. 弔慰金の過大計上
よくあるミス:
- 弔慰金の非課税限度額を超過した部分の未計上
- 役員と一般従業員の限度額の混同
対策:
- 普通給与月額の正確な把握
- 弔慰金と退職金の区分の明確化
2. 支給時期の誤認
よくあるミス:
- 3年経過後の支給を相続税で申告
- 支給確定日の判定誤り
対策:
- 会社の決議録等の確認
- 支給通知書の日付確認
3. 複数の退職金の見落とし
よくあるミス:
- 子会社からの役員退職慰労金の未計上
- 厚生年金基金等からの一時金の見落とし
対策:
- 全ての勤務先・役員就任先の確認
- 年金制度の加入状況調査
6 まとめ:退職金の取り扱いは相続税対策の要に
死亡退職金の取り扱いは、相続財産の中でも特に見落としやすいポイントです。非課税限度額の活用や支給時期の確認など、正しい知識と適切な対応が求められます。
特に、富士市・富士宮市のように家族経営や自営業、地域企業に勤める方が多い地域では、退職金が相続財産の中で重要な位置を占めることもあります。
退職金が相続税の対象となるか、どこまでが非課税かを事前に理解し、専門家のサポートを受けながら申告準備を進めていきましょう。






