こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
今回は、遺産の中に「不動産」が含まれる場合に、特に活用される代償分割(だいしょうぶんかつ)について、実務上のポイントや他の分割方法との違いを含めて解説します。
1 代償分割とは?相続実務での基本的な位置づけ
相続では、現金や不動産、預貯金などの財産をどう分けるかが大きな問題になります。
とくに、遺産の多くが不動産で占められているケースでは、現物での分割が困難なためトラブルの原因になりがちです。こうした状況でよく利用される方法が「代償分割」です。
代償分割の定義
代償分割とは、ある相続人が特定の財産(たとえば不動産)を取得し、他の相続人には代わりに現金などで“代償”を支払う遺産分割方法です。
現物で分けられない財産を、金銭による調整で公平に分け合う点が特徴です。

2 代償分割が選ばれる理由とは?
代償分割は、次のような実務的な理由からよく選ばれています。
1. 不動産の共有を避けたい
富士市・富士宮市を含む地方部では、相続財産の中心が自宅などの不動産であることが多くあります。
不動産を複数人で共有すると、売却やリフォームなどの意思決定が煩雑になり、後々の紛争につながりやすくなります。
代償分割を用いることで、不動産は1人が単独で取得し、他の相続人は金銭で補填されるため、スムーズな管理・処分が可能になります。
2. 事業や農地を守りたい
事業用資産や農地などは、分割してしまうと経営や運用に支障をきたす場合があります。
このようなケースでは、後継者となる相続人が一括して相続し、他の相続人には代償金を支払うことで、事業承継と公平性の両立が図れます。
3. 遺言がない場合の柔軟な解決策になる
遺言書がない場合、すべての財産は遺産分割協議によって決める必要があります。
代償分割を選ぶことで、現物分割や換価分割が難しい場面でも、代償金によりスムーズな合意形成が可能となります。
3 代償分割の具体例:よくある実務パターン
たとえば、以下のようなケースです。
相続財産:自宅(土地・建物)2,000万円、預貯金100万円
相続人:長男・長女の2名
遺言:なし(平等に分けたい)
不動産を半分に物理的に分けることは現実的でないため、共有にする、売却して現金化するなどの方法も考えられます。
ここで代償分割を選択し、長男が不動産をすべて取得し、その代わりに長女へ950万円の代償金を支払うことで、法定相続分(50%)の公平を保つことが可能になります。
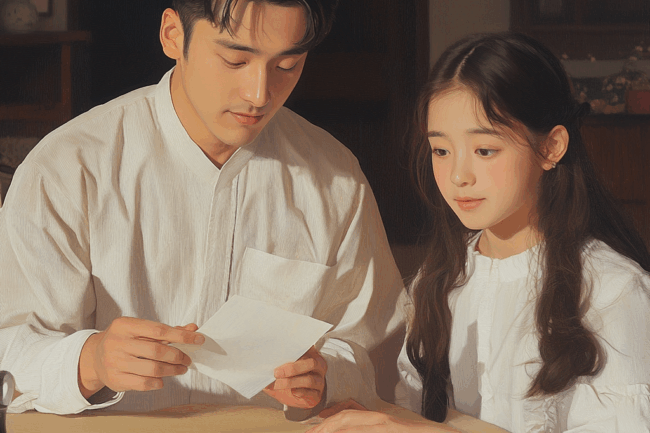
4 他の遺産分割方法との違い
代償分割は、次のような他の分割方法と比較されることがあります。
| 分割方法 | 内容 | 特徴・問題点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産を現物で分ける | 預貯金など分けやすい財産には有効だが、 不動産には不向きな場合が多い |
| 換価分割 | 財産を売却して、代金を分ける | 売却価格が市場に左右されるため、 金銭的・感情的なトラブルの原因になりやすい |
| 共有分割 | 複数人で共有名義にする | 将来的な使用や売却で意思統一が難しく、 管理負担や紛争リスクが高くなる |
| 代償分割 | 一人が取得し、他に代償金を支払う | 公平性を確保できる柔軟な方法だが、 代償金の調達に課題があることも |
まとめ|代償分割は「実務と公平」を両立させる相続方法
代償分割は、不動産や事業資産が中心となる相続において、法定相続分の公平性を守りつつ、実務的な運用も考慮した分割方法です。
不動産をめぐる相続争いを避けるためにも、遺産の構成に応じて最適な分割方法を検討することが大切です。
「共有にしたら後々面倒かも」「長男が住み続ける方が自然かも」といった実情をふまえ、代償分割を取り入れることで、円満な相続を実現できます。






