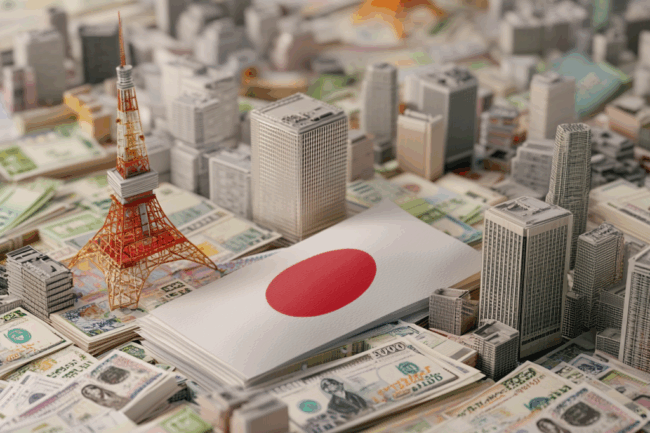こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
国債は有価証券の一種であり、お亡くなりになった方が国債をお持ちだった場合、相続財産に含まれます。有価証券や不動産など、現預金以外の相続財産は、遺産分割協議や相続税の計算をする際に、相続発生時点の時価を算定する必要があります。
今回は、国債の種類と、相続税評価額の計算方法について解説します。
1 国債とは?その基本的な仕組みと種類
国債は、国が発行している債券です。償還期限と利率が設定されており、国が償還(元本の支払い)と利子の支払いを行います。有価証券に分類されますが、株式とは異なり、償還期限まで保有すれば元本が保証されるのが特徴です。一方で、途中解約すると元本割れする可能性があります。
主な国債の種類は以下の通りです。
- ■利付国債:半年ごとに利子が支払われ、満期に元本が返ってきます。
- ■割引国債:額面より安い価格で購入し、満期に額面で償還されるため利子の支払いはありません。
- ■個人向け国債:個人が購入できる利付国債で、発行1年後から中途換金可能。相続が発生した場合は1年未満でも中途換金できます。
2 相続財産としての国債の取り扱い
国債は、相続財産の一部として遺産分割と相続税の課税対象となります。遺言がある場合はそれに従って、ない場合は相続人同士で協議し、誰が国債を取得するかを決めます。
取得方法は次の2通りです。
1 国債の名義を相続人に変更して引き継ぐ方法
2 中途換金して現金で相続する方法
3 国債の相続税評価額の計算方法
国債の評価額は種類によって計算方法が異なります。
評価基準日について
国債の相続税評価を行う際は、評価基準日の設定が極めて重要です。相続税法では、相続開始日(被相続人の死亡日)時点での時価による評価が原則となります。
死亡日が土日祝日や年末年始など市場が閉まっている日の場合でも、評価基準日は死亡日となり、その日の価格を取得する必要があります。金融商品取引所が休場の場合は、直前の営業日の最終価格を用いて評価を行います。
また、既経過利息についても死亡日までの日割り計算となるため、正確な死亡日時の確認が評価額算定の前提となります。
利付国債の場合
評価額は「相続開始日時点の最終価格 + 既経過利息の額」です。
- ■上場されているものは、金融商品取引所の公表する価格+既経過利息で評価
- ■統計値があるものは、売買参考統計値の平均値+既経過利息
- ■統計値のないものは、発行価額+既経過利息
※既経過利息は前回の利払い日から相続日までの利息です(税引後)。
割引国債の場合
- ■上場されているもの:相続開始日の最終価格
- ■統計値があるもの:平均値
- ■統計値がないもの:発行価額+日割計算した償還差益
個人向け国債の場合
評価額は「額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額」で算定されます。
■経過利子相当額:前回利払い日から相続日までの利子
■中途換金調整額:中途換金により差し引かれるペナルティ相当額
□1年以上経過:利子2回分相当
□1年未満:利子や経過利子全体が調整対象
この評価方法は通達には載っていませんが、国税庁の質疑応答事例で明確に認められています。
計算に不安がある場合は、財務省の「中途換金シミュレーション」を活用しましょう。
4 相続手続きと分割時の注意点
国債は購入単位ごとの分割のみ可能です。法律で定められた単位未満での分割はできません。
また、有価証券を相続する場合、証券口座が必要になるため、相続人は新たに口座を開設する必要があるケースがあります。事前に証券会社と連絡を取って準備しておくと安心です。