こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
被相続人が自由に財産を遺せるとはいえ、相続人には生活保障の観点から「最低限の取り分」が法律で保障されています。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
本記事では、遺留分の基本から放棄の方法、家庭裁判所の許可、相続税や負債のリスク、未成年の扱いまでを解説いたします。
1 遺留分とは?〜法定相続人に認められた最低限の取り分
遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に法律で保障された「最低限の相続分」のことです。
たとえ遺言で「財産はすべて他人に渡す」と記されていても、以下の相続人は一定割合を請求する権利があります:
- ■配偶者
- ■子(または代襲相続人)
- ■直系尊属(父母など)
ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

2 遺留分の割合はどれくらい?
相続人の構成により、遺留分の割合は次のように異なります。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者・子がいる場合 | 法定相続分の 1/2 |
| 配偶者のみ・親のみなど直系尊属だけ | 法定相続分の 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
3 遺留分を主張するには?|遺留分侵害額請求権
以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、現在は「遺留分侵害額請求権」とされています。
この権利は、
- ■相続の開始および侵害を知った日から1年
- ■相続開始から10年
のいずれか早い方までに行使しなければ、時効により消滅します。
4 遺留分の放棄とは?|相続放棄とは別の制度
「遺留分放棄」とは、遺留分のみを請求しないことを明確にする手続きです。
これは「相続放棄(遺産全体の放棄)」とは別制度で、次の点に注意が必要です。
| 項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 放棄対象 | 遺留分のみ | 遺産全体 |
| タイミング | 生前 or 死後 | 相続開始後のみ |
| 手続き | 生前放棄は家庭裁判所の許可が必要 死後放棄は意思表示のみで可 | 相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 借金相続の扱い | 放棄しても借金相続の可能性あり(相続権は残るため) | 一切相続せず、借金も引き継がない |
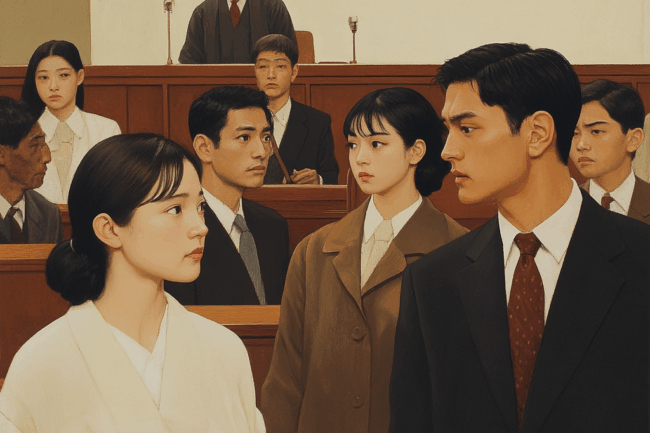
5 生前に遺留分を放棄する方法と要件
被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、無理な強要や不当な誘導を防ぐためです。
手続きの流れ
■遺留分権利者が申立て(家庭裁判所)
■必要書類:申立書・戸籍謄本など
■家庭裁判所が審査(放棄の理由・代償の有無など)
■許可されると「許可審判書」が送付
※許可には合理性が必要で、必ず通るとは限りません。
6 相続開始後の遺留分放棄とその注意点
被相続人の死亡後(相続開始後)に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
■放棄する人が、請求先に対し意思表示すれば成立
■口頭でも可能だが、念書などの書面作成が推奨されます
ただし、書面があっても一律に法的効力があるとは限らず、争いの可能性もあるため、慎重に行う必要があります。
7 遺留分放棄のメリット・デメリット
メリット
- ■紛争の予防に役立つ
- ■相続関係の整理がしやすくなる
- ■相続開始後の放棄は手続きが簡便
デメリット
- ■生前の放棄は家庭裁判所の判断が必要で見通しが立ちにくい
- ■一度許可された放棄は原則として簡単には撤回できない
- ■放棄すると最低限の取り分も失うため、「代償」がないと損になる可能性がある
8 放棄を検討する際のチェックポイント
■なぜ放棄してほしいのか、理由に納得できるか
■放棄の見返り(代償)はあるか、証拠として残せるか
■感情的な判断ではないか
■未成年者が放棄する場合は特別代理人の選任が必要か
9 相続税や負債との関係にも注意
遺留分を放棄しても、法定相続分による相続権は残ります。
そのため、以下の点に注意が必要です:
■相続財産に負債があると、借金も引き継ぐリスク
■借金を放棄したい場合は、別途「相続放棄」が必要
■相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内







