はじめに|事業承継の選択肢は一つではない
事業承継というと、かつては「息子に継がせる」という親族内承継が主流でしたが、近年では従業員承継や第三者承継(M&A)といった選択肢も一般化しています。
それぞれにメリット・デメリットがあり、経営者の意向や会社の状況、後継者の有無などにより、最適な類型は異なります。
本記事では、事業承継の3類型の特徴と注意点をわかりやすく解説します。
1 親族内承継:家族に引き継ぐ伝統的な形
特徴
■現経営者の子・兄弟姉妹・孫などに承継
■所有と経営の一体化がしやすく、経営理念や価値観の継承にも適している
最近の傾向
■若年層の多様な価値観、業種への不安などから親族内承継は減少傾向
■それでも地域密着型企業では今も有力な選択肢
主な課題と対策
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 税負担(贈与税・相続税) | 事業承継税制の活用(納税猶予・免除制度) |
| 株式の分散 | 遺言・種類株式・信託の活用、民法特例による調整 |
| 後継者の同意・育成 | 家族会議、計画的な育成プランの設計 |
| 親族間の調整 | 早期に意向を共有し、協力体制を築く |
| 債務・保証の問題 | 債務整理、経営改善、保証解除交渉 |

2 従業員承継:社内の人材に託す
特徴
■役員や従業員など、社内の信頼できる人材に承継
■経営方針の継続が可能で、現場をよく知る後継者によるスムーズな移行が期待される
最近の傾向
■親族内承継の減少を受けて増加傾向
■種類株式や持株会社の活用により、資金的ハードルも下がってきている
主な課題と対策
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 他の従業員・役員の理解 | 社内説明会、段階的なリーダーシップ移譲 |
| 親族株主の承認 | 株主構成の調整、合意形成の支援 |
| 経営知識の不足 | 外部研修、OJT、専門家との連携 |
| 個人保証の承継 | 債務圧縮、金融機関との保証解除交渉 |
| 所有と経営の分離 | 株式移転も含めた中長期の承継設計が必要 |
3 社外承継(M&A):第三者に売却・引継ぎ
特徴
■親族・従業員に後継者がいない場合の選択肢
■会社の存続と従業員の雇用維持が可能で、引退後の資金確保にもつながる
最近の傾向
■M&A市場が活性化。中小企業の「スモールM&A」も増加
■事業承継としてのM&Aは社会的にも注目されている
主な課題と対策
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 手続きの煩雑さ | M&A仲介業者・FAの活用で効率的に進行 |
| 許認可の承継 | 事業譲渡・合併のスキーム選択に注意 |
| 関係者への説明 | 金融機関・取引先・従業員への丁寧なコミュニケーション |
| 企業価値の適正把握 | バリュエーション・デューデリジェンスの実施 |
| 社風・文化の違い | 引継ぎ期間の確保、事前のマッチング精度向上 |
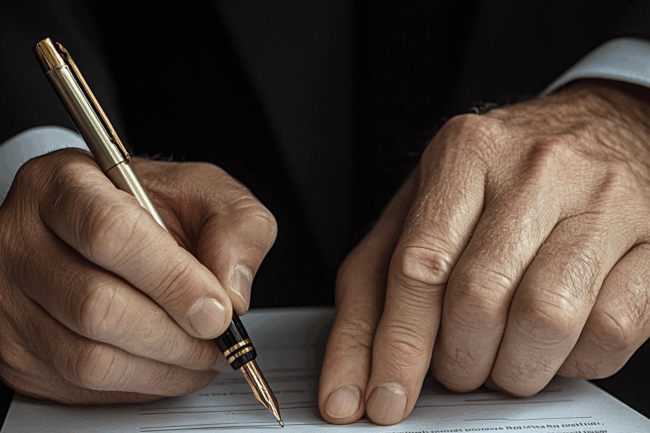
4 どの承継方法を選ぶか?判断のポイント
どの類型を選ぶかは、以下の要素をバランスよく判断することが大切です。
| 判断基準 | チェックポイント |
|---|---|
| 後継者の有無 | 家族に承継意思があるか?社内に適任者がいるか? |
| 経営者の希望 | 株を残したいか?引退後の資金を重視するか? |
| 社員・取引先との関係 | 承継方法によって信頼関係に影響が出ないか? |
| 時間的余裕 | 準備期間が十分にあるか? |
まとめ 自社に合った承継形態を見極め、早めの準備を
事業承継は、企業の未来を左右する重大な経営課題です。以下の3つの類型にはそれぞれ異なる特徴とハードルがあり、最適解は企業ごとに異なります。
■親族内承継:理念や文化の継承に強み。家族調整・税務対策がカギ
■従業員承継:社内理解が得られればスムーズ。株式・保証の整理を要検討
■M&A(第三者承継):後継者不在でも事業存続が可能。交渉力と専門支援が成功の鍵
事業承継は「ある日突然」できるものではありません。 健康なうちに、関係者と十分な話し合いを重ね、数年単位で計画的に準備を進めていくことが成功の秘訣です。




