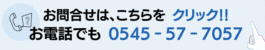こんにちは。富士市・富士宮市の相続税専門、飯野明宏税理士事務所です。
今回は、「相続したけど使い道がない土地」を抱えている方にとって朗報とも言える新制度、「相続土地国庫帰属制度」について、わかりやすく解説します。
第1章|制度の概要と開始日
相続や遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した方は、一定の条件を満たすことで、その土地を国に引き取ってもらうことができる制度が始まりました。
制度名:相続土地国庫帰属制度
開始日:令和5年(2023年)4月27日
この制度は、法務省の民事局が公表したパンフレット『所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。』に基づいて導入されたものです。
第2章|制度の活用が期待されるケース
富士市・富士宮市の相続案件において、特に市街地以外の土地や山林、農地などにおいて、
「持っていても使い道がない。固定資産税だけがかかって困っている。」
といったご相談を多くいただきます。
このような「誰も買い取ってくれない」「相続したけど維持管理に困っている」土地に対して、この制度は非常に有効です。
第3章|国庫帰属までの手続きの流れ
国に土地を引き取ってもらうには、次のような手続きが必要です。
ステップ①|承認申請を行う
土地を管轄する法務局に対して申請します。
相続や遺贈によって土地を取得した人が申請者となります。
ステップ②|審査と承認
法務局により書類審査・実地調査が行われます(※実地調査は省略されることもあります)。
書類段階で不適格と判断される場合は、却下されることもあります。
ステップ③|審査手数料の支払い
申請時に審査手数料がかかります(法務省が定める額)。
ステップ④|負担金の納付
国が引き取ることを承認した後、土地管理にかかる負担金を納付する必要があります。
負担金の金額は土地の種別・管理コストにより異なります。
第4章|注意点と制限事項
✔ 対象外となる土地がある
次のような土地は、制度の対象外となる可能性があります:
建物が存在する土地
土壌汚染や管理困難な形状の土地
他人の権利(地上権・賃借権等)が設定されている土地
他の所有者との共有状態にある土地(ただし、持分すべてを取得すれば可)
✔ 書類不備や条件未満で却下も
全ての申請に対して実地調査が行われるわけではありません。
書類の段階で却下される場合もあります。
第5章|まとめ:不要な土地は「相続放棄」だけではない選択肢を
相続税の申告手続きの現場では、「この土地だけ不要なんだよね……」という声をよく伺います。
そうしたケースにおいて、相続土地国庫帰属制度は“土地の処分”という新たな選択肢を提供してくれます。
負担金や手続きはありますが、維持し続ける固定資産税や管理リスクを考慮すると、メリットのある制度といえるでしょう