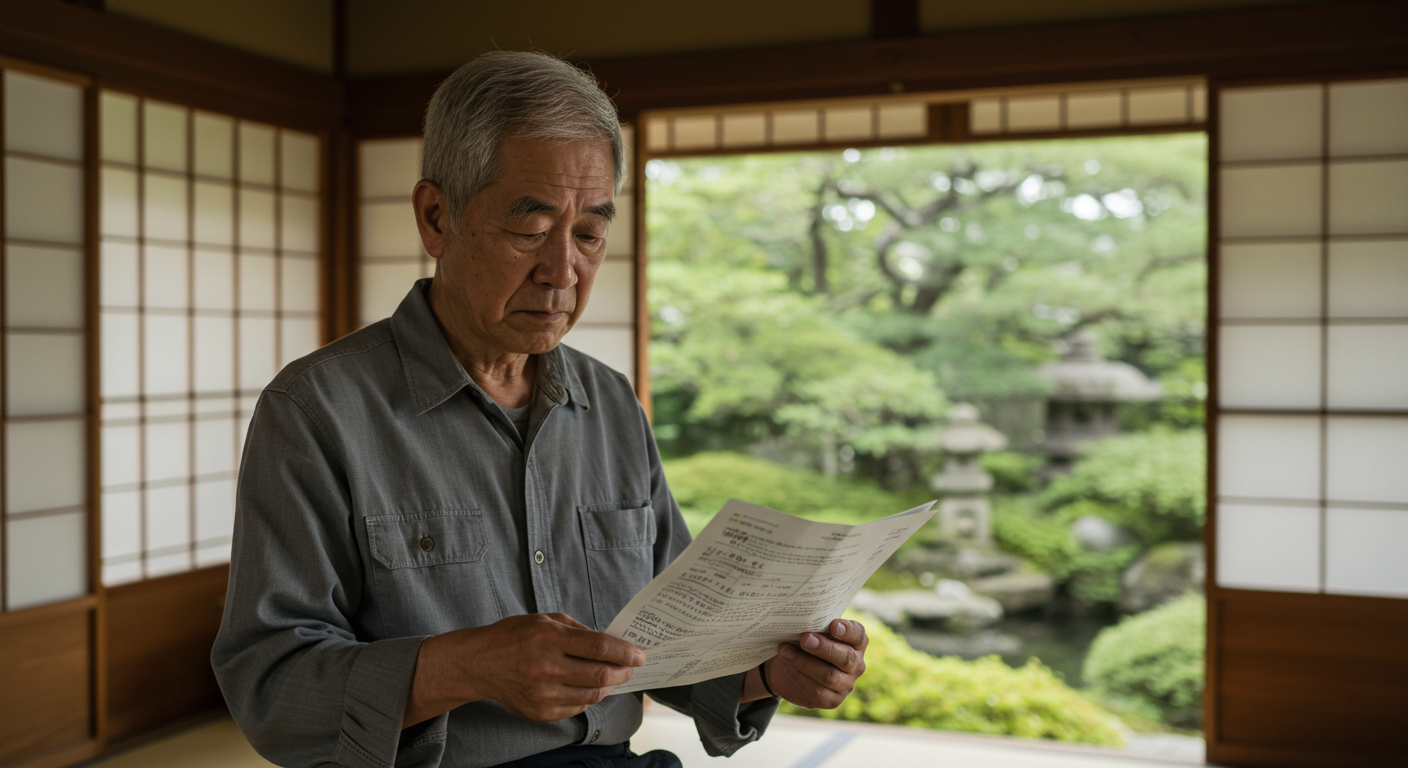目次 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? 2 家庭用財産の評価単位と方法 3 種類別に見る家庭用財産の評価ポイント 4 電話加入権の取扱いはどう変わった? 5 申告時の注意点とリスク 1 家庭用財産とは?相続税の対象になる? こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 家庭用財産とは、家具や家電、衣類、自動車、貴金属、書画骨董、そして電話加入権などの「動産全般」を指します。これらは被相続人の所有する財産として、相続税の対象に含まれます。 2 家庭用財産の評価単位と方法 家庭用財産は原則として「一般動産」として個別に評価されますが、実務上の負担を考慮して、1点あたり5万円以下の動産については「家財一式」として一括評価することが認められています。 評価方法の原則は、売買実例価額、精通者意見価格、類似財産の実例価額などを参考にします。評価が困難な場合は、未償却残高による評価も可能です。 家財一式の評価額の相場…