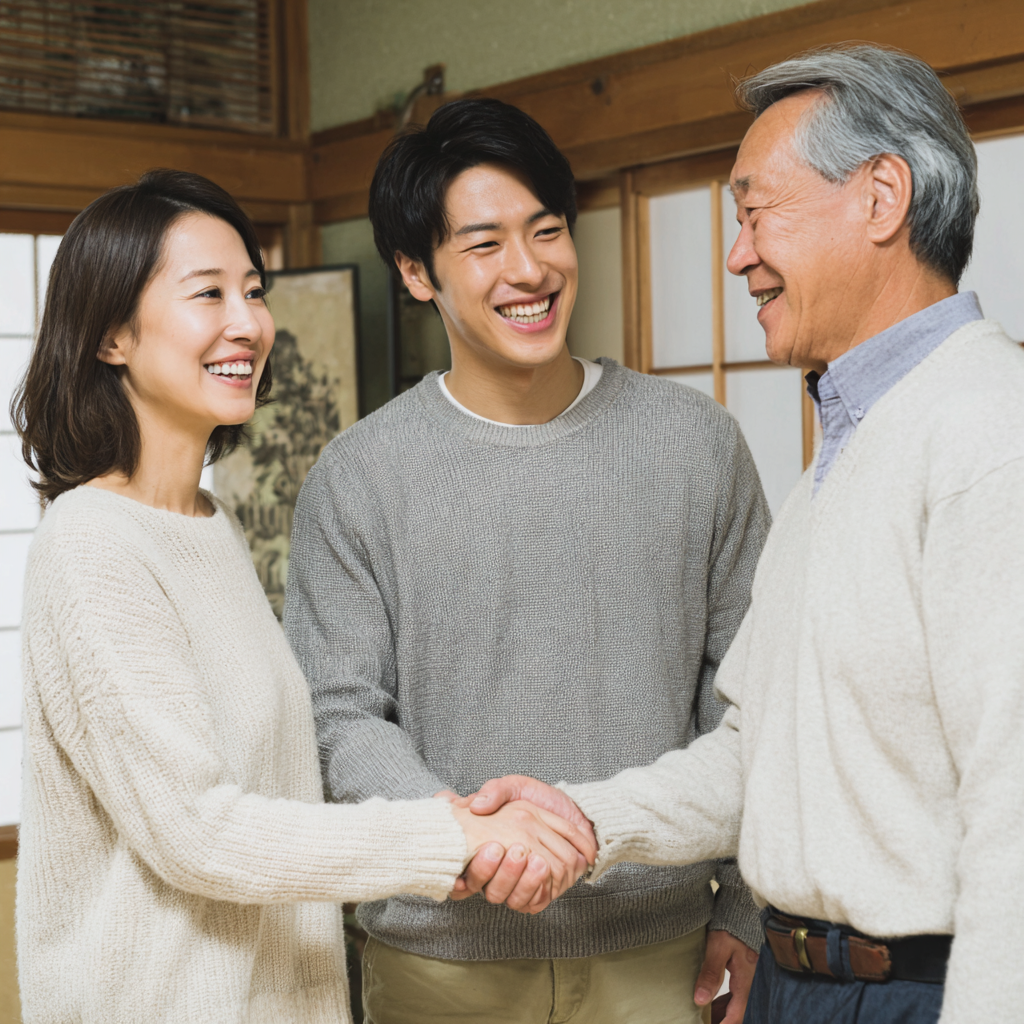こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「相続税はどのくらいかかるのか?」 この質問に答えるためには、「相続税の税率」を正しく理解する必要があります。 相続税は一律の税率ではなく、課税価格に応じて税率が上がっていく「超過累進課税制度」を採用しています。また、税率だけでなく「控除」や「特例」なども複雑に絡んでおり、全体像を把握するにはある程度の知識が求められます。 本記事では、相続税の税率とその計算方法を、税理士の視点からわかりやすく解説します。これを読めば、自分や家族に相続税がどれだけかかるのか、具体的にイメージできるようになるはずです。 目次 1. 相続税の税率は「超過累進課税」 2. 相続税の計算ステップ 3. 具体的な計算例 4. 税率に関わる各種控除と特例 5. 税率を意識した考え方 6. 相続税の税率に関するよくある質問(FAQ) まとめ|相続税の税率は正しく理解すれば怖くない 1.相続税の税率は「超過累進課税」…