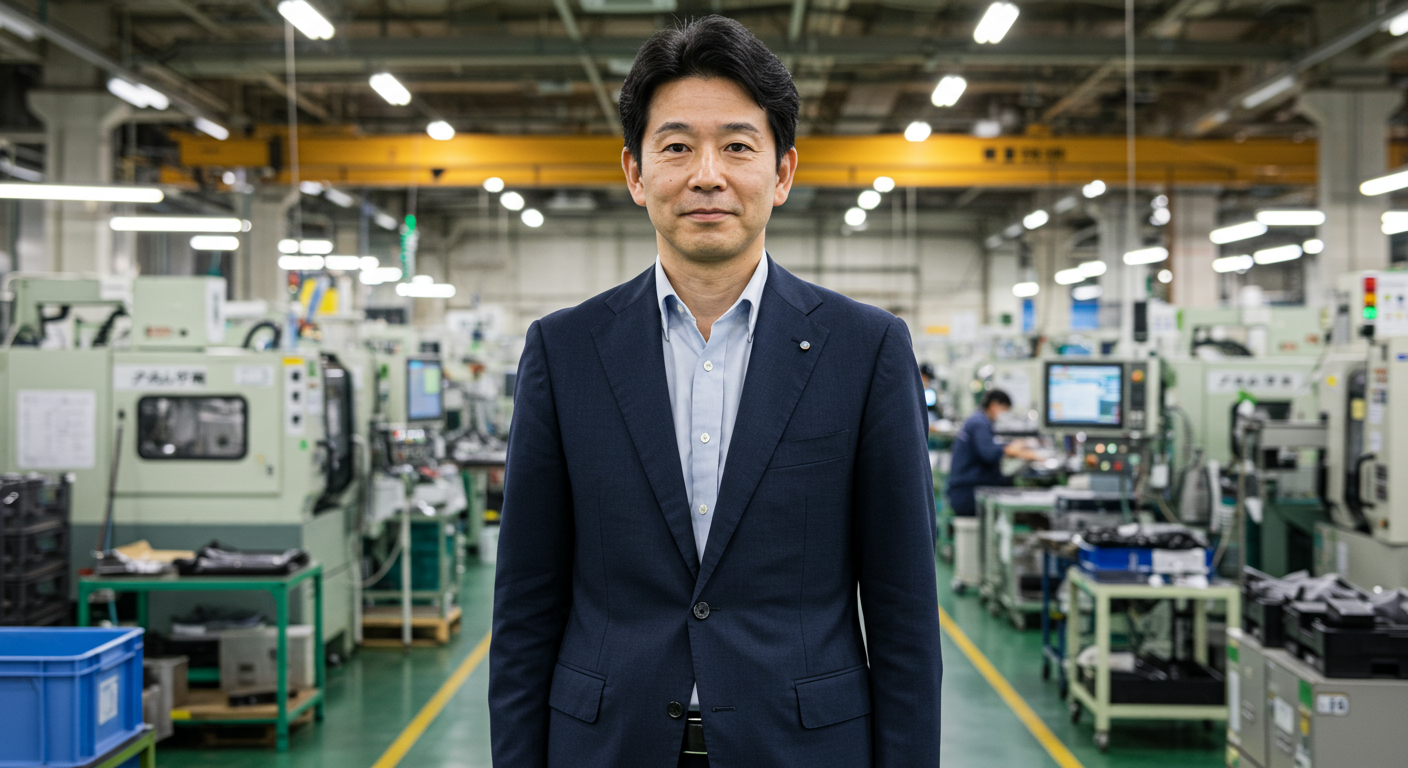こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 事業で使用するパソコンや什器などの資産を購入した際、一定額以上であれば通常は「減価償却」によって数年かけて経費化します。しかし、取得価額が比較的少額の固定資産については、購入した年に全額を経費にできる特例制度が用意されています。 本記事では、中小企業や個人事業主が活用できる3つの少額減価償却資産の特例について、それぞれの制度概要、適用条件、メリット・デメリットを解説します。 1 10万円未満の少額減価償却資産:誰でも使える基本の特例 制度の概要 取得価額が10万円未満の資産は、購入年度に全額を即時に経費計上できます。 特徴 10万円未満の少額減価償却資産の税務上の取扱い 項目 内容 対象者 中小企業・大企業問わずすべての事業者 経理処理 消耗品費または減価償却費で処理 年間限度額 なし(件数制限なし) 添付書類 申告書等への添付不要 償却資産税…