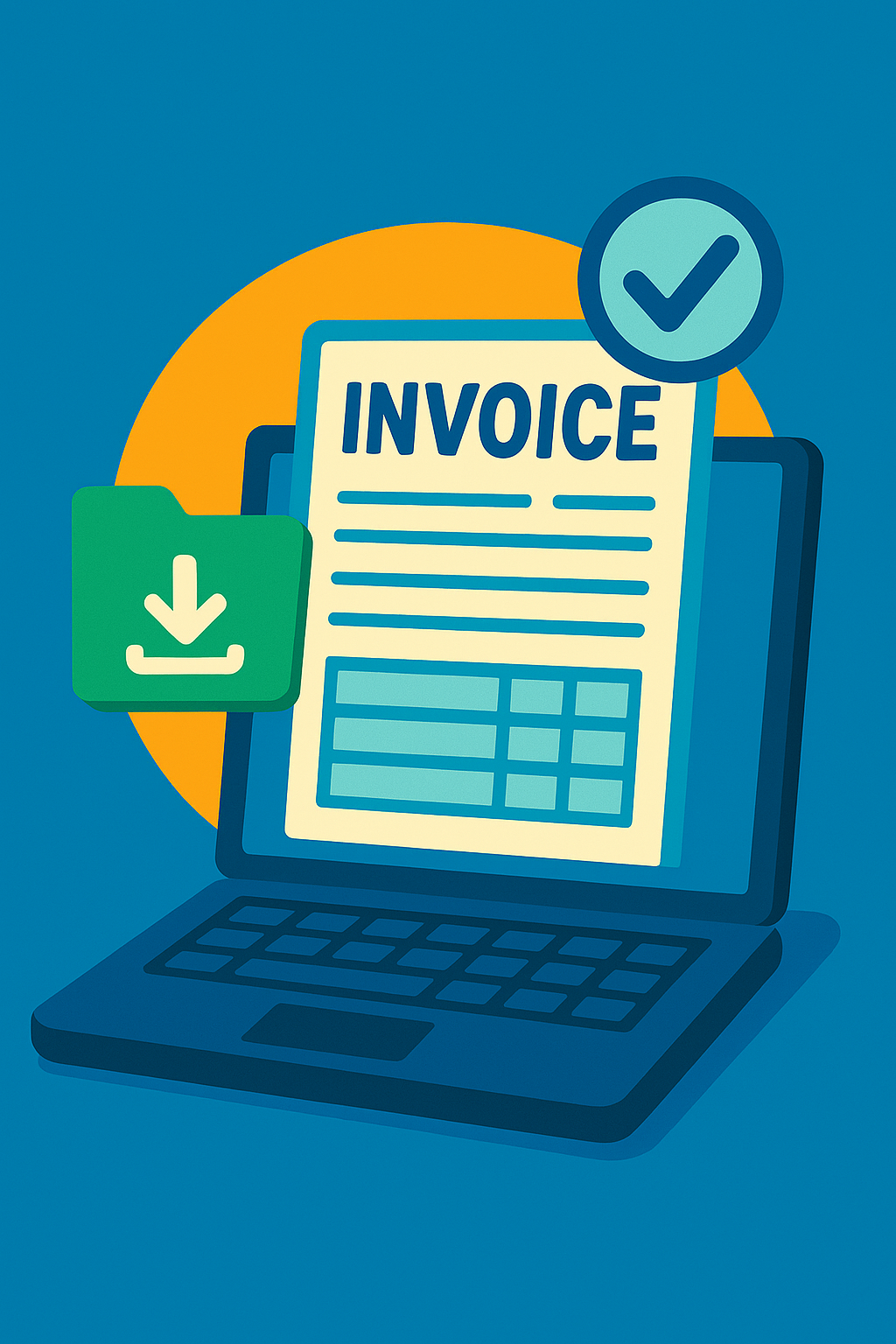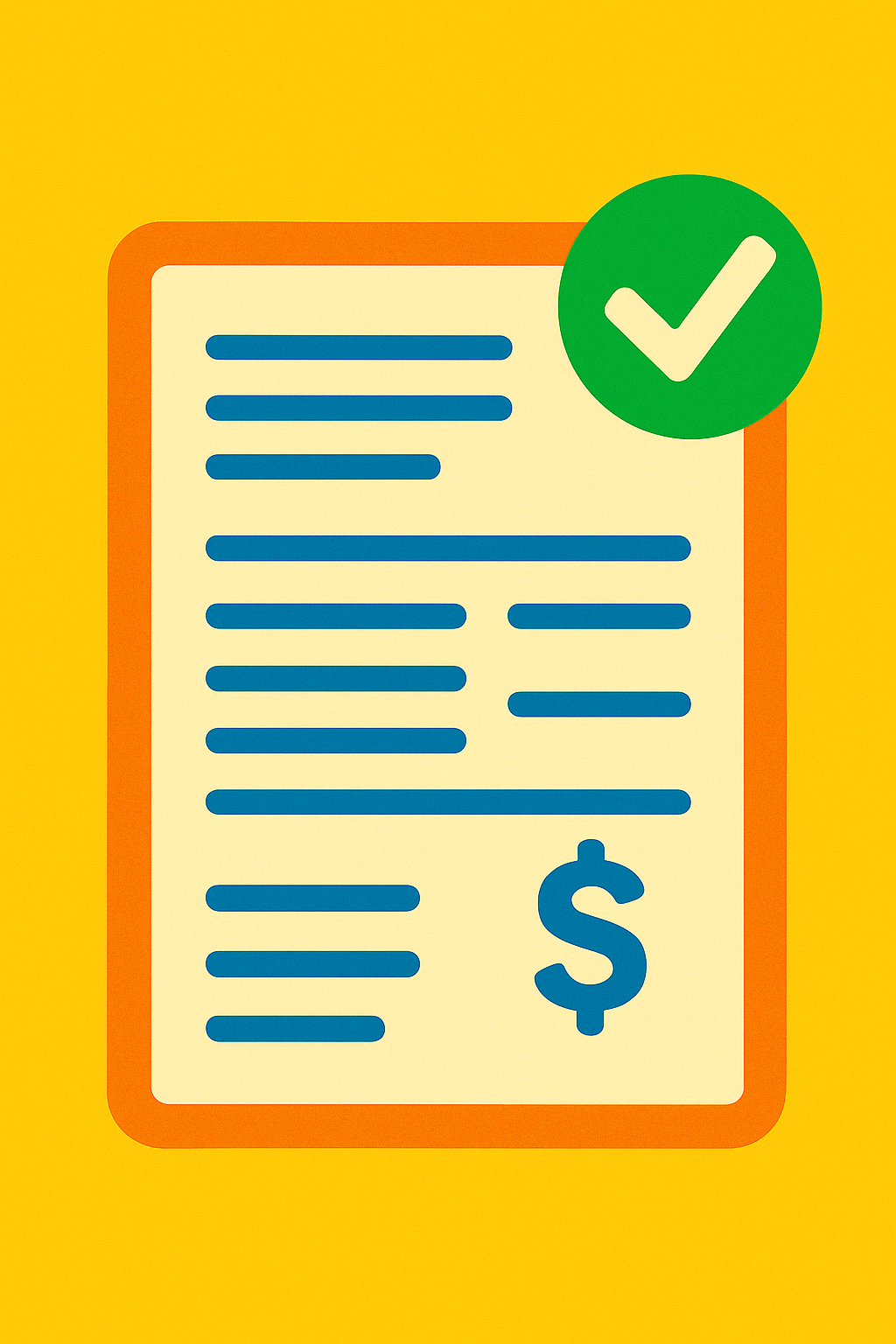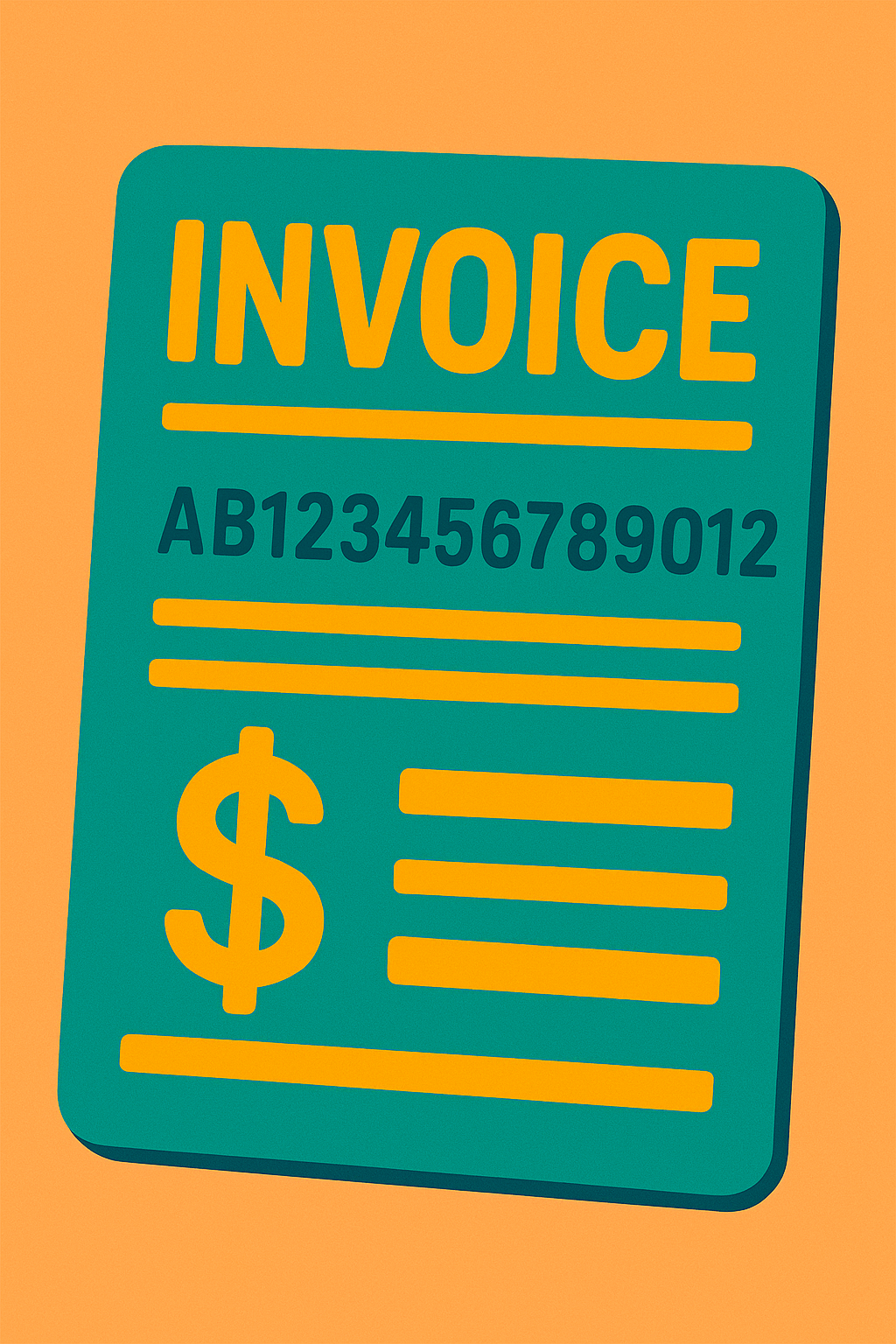目次 1 媒介者交付特例とは?基本の仕組み 2 媒介者交付特例の適用要件 3 複数の委託者がいる場合の実務対応 4 買手が委託者にインボイスを求めたら? まとめ|媒介者交付特例を活用して、三者間取引もスムーズに対応 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 インボイス制度が始まり、適格請求書の交付・保存が税務処理の基本となりました。しかし、商品の販売形態が「委託販売」や「代理販売」のような三者間取引の場合、 ■「誰が誰に対してインボイスを交付すべきか?」 ■「委託者が適格請求書を交付しないといけないの?」 といった疑問をお持ちの事業者様も多いのではないでしょうか。 実は、そうしたケースでは「媒介者交付特例」を利用することで、受託者(仲介者)側がインボイスを交付することが可能です。 今回はこの媒介者交付特例について、実務対応を交えながら解説します。 1 媒介者交付特例とは?代理交付との違いと基本の仕組み 通常、商品の販売者=課税資産の譲渡者である委託者が、購入者に対してインボイスを交付する義務があります。…