はじめに
退職金は、長年の努力と貢献に対する報酬であり、老後の生活資金として重要な位置を占めます。そのため、税務上の取り扱いについて正しく理解しておくことが、資金計画を立てるうえで非常に重要です。
今回は、生前に受け取る退職金と死亡退職金にかかる税金の違いや、優遇されている税制の仕組み、申告の必要性、そして将来的な税制改正の見通しについて解説します。
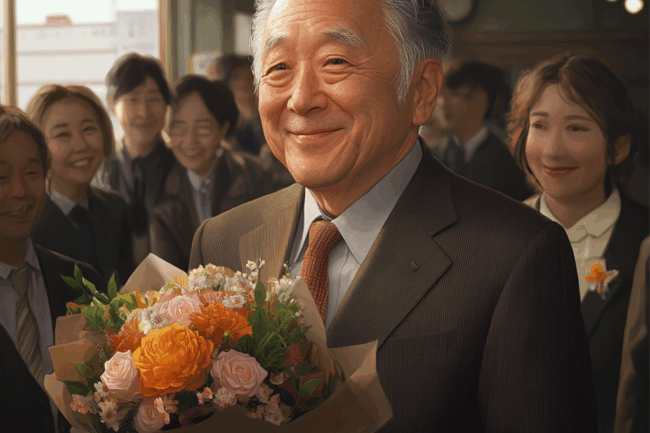
1 生前に受け取る退職金の税金とは?
1-1. 所得税と住民税の課税
退職金には所得税と住民税が課税されます。ただし、給与所得とは異なり、優遇措置が多く設けられています。
課税方法は以下の通りです:
- ■退職所得控除の適用
- ■分離課税方式(他の所得と合算しない)
- ■所得金額の1/2が課税対象(一定条件を満たす場合)
1-2. 原則、退職所得の計算式
退職所得の金額 = (退職金額 − 退職所得控除額) × 1/2
※特定のケース(特定役員退職手当等や短期退職手当等)では1/2の軽減が適用されません。
1-3. 退職所得控除の計算方法
- ■勤続年数が20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- ■勤続年数が20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)
※1年未満の端数は切り上げます。
1-4. 計算例(勤続年数26年・退職金1,500万円)
- ■控除額:800万円 + 70万円 × (26−20) = 1,220万円
- ■退職所得: (1,500万円 − 1,220万円) × 1/2 = 140万円
- ■所得税・住民税: 140万円 × 5.105% = 約71,470円
- ■手取額:1,500万円 − 71,470円 = 約1,492万8,530円
2 例外、1/2計算の適用がないケース
2-1. 特定役員退職手当等
- ■勤続年数5年以下の役員に支給される退職金は1/2の軽減なし。
2-2. 短期退職手当等
- ■勤続年数5年以下かつ役員でない人が受ける退職金のうち、300万円を超える部分には1/2計算が適用されません。
2-3. 勤続期間の重複調整
- ■前4年以内(確定拠出年金は19年)に退職金を受給していた場合には、勤続期間の重複排除の調整計算が必要です。
3 退職金の確定申告は必要?
3-1. 基本的には申告不要
- ■退職金の支払時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収により課税関係は完結。
3-2. 申告が必要なケース
- ■医療費控除や寄附金控除など、他の理由で確定申告する場合は退職所得も記載。
3-3. 手続きの概要
- ■退職金支払者が申告書を保管
- ■税務署・市区町村へ提出が必要なのは役員分のみ
- ■源泉徴収分は翌月10日までに納付
4 死亡退職金の課税と非課税枠
4-1. 相続税の対象
- ■被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の対象となる
4-2. 非課税枠
- ■非課税金額:500万円 × 法定相続人の数
4-3. 法定相続人の数の数え方
- ■相続放棄者も含めた本来の相続人の数で計算
- ■養子は制限あり(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)
4-4. 所得税課税になる場合
- ■死亡後3年を経過して支給が確定したものは、一時所得として所得税の課税対象に
おわりに
退職金に関する税制は、税負担の軽減措置がある一方で、例外的な取り扱いや複雑な計算も含まれます。特に、今後の税制改正で取り扱いが変わる可能性もあるため、常に最新の情報に注意を払うことが重要です。
退職金に関して不安がある方は、早めに税理士などの専門家へ相談し、正しい納税と資金計画を立てましょう。




