こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
令和5年10月1日よりスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の実務に大きな影響を与える制度です。
当事務所でも、制度開始時にインボイス制度の基本的な解説をリリースいたしましたが、
令和7年4月に国税庁がインボイス制度に関する「Q&A(よくある質問)」を改訂したことを受け、改めて制度の基本概要を整理し直すことにいたしました。
本記事では、最新の国税庁Q&Aの内容も踏まえたインボイス制度の基本解説を、改めて分かりやすくお届けいたします。
1 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
正式名称と導入の背景
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。
複数税率(8%・10%)への対応と、消費税の仕入税額控除の適正化を目的に導入されました。
これにより、買手が消費税の控除を受けるには、従来の請求書ではなく「適格請求書」の保存が必須となったのです。
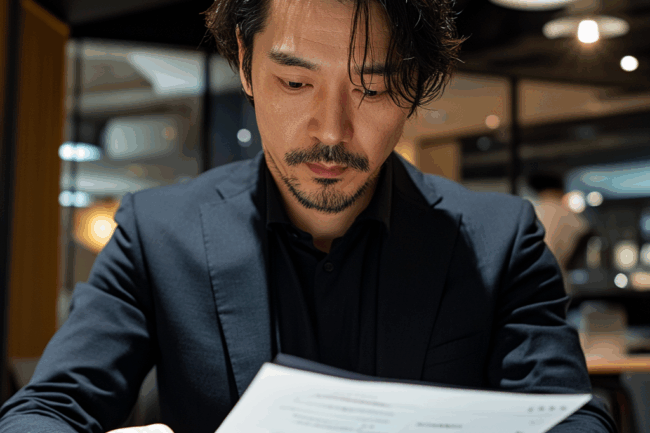
2 仕入税額控除の要件がこう変わった!
インボイス制度導入により、仕入税額控除を受けるための要件が以下のように変わりました。
必要な書類等の保存
■適格請求書(インボイス)
■適格簡易請求書
■上記の記載事項を含む電子データ
■相手先の確認を受けた仕入明細書や仕入計算書
■媒介・取次に関する特定書類
適格請求書に必要な記載項目
| 必須記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 登録番号 | 発行者の登録番号(T+13桁) |
| 税率区分 | 税率ごとの消費税額等を区分して記載 |
| 書類発行者 | 氏名または名称、取引年月日など |
従来の請求書に比べて、より詳細な記載が求められるようになった点にご注意ください。
3 制度はいつから始まっているの?
インボイス制度は、令和5年10月1日から施行されました。
以下のように、制度の対象となるのはこの日以降の取引です。
■売手における課税資産の譲渡日が10月1日以後の取引から
■買手が控除を受けるには、その取引に関する「適格請求書」の保存が必要
4 適格請求書の交付が必要なケース・不要なケース
請求書の交付が【必要】となる場合
■売手が「適格請求書発行事業者」であり
■相手が課税事業者で、請求書の交付を求めた場合
このとき、発行義務があるため、適格請求書を交付しなければなりません。
【免除】されるケース(例)
以下のような取引では、適格請求書の交付義務がありません。
■3万円未満の公共交通機関(電車・バスなど)の利用
■卸売市場での生鮮食料品販売
■農協・漁協等による農林水産物の販売
■3万円未満の自動販売機での商品購入
■郵便ポスト差出しの郵便サービス
■1万円未満の返品・値引きなどの返還等
また、非課税取引・免税取引・不課税取引のみを行う事業者についても、インボイスの交付義務はありません。
5 インボイス対応のチェックポイント
インボイス制度の導入に伴い、事業者が確認すべきことは次の通りです。
適格請求書発行事業者への登録は済んでいるか?
未登録のままでは、取引先が仕入税額控除を受けられず、ビジネス上の支障になる可能性があります。
請求書に必要事項を記載しているか?
従来の書式に比べて記載項目が増えているため、請求書フォーマットの見直しが必要です。
電子保存への対応はできているか?
電子インボイス(PDFやクラウド等)にも対応する体制が求められています。
まとめ インボイス制度は“実務対応”がカギ!
インボイス制度は、仕入税額控除の実務を根本から変える制度です。特に、記載内容のチェック・登録手続・社内対応体制の整備が必要です。
富士市・富士宮市の事業者の皆さま、制度開始から半年以上が経ちましたが、まだ不安を感じている方も多いかと思います。
私たち税理士事務所では、
■インボイス登録手続き
■請求書の記載内容の確認
■会計ソフト対応のアドバイス
などを含めた総合サポートを行っております。お気軽にご相談ください。




