1 税務調査とは何か?その本質と種類を知る
こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。
税務調査とは、税務署が申告された税額の適正性を確認するために実施する調査のことです。税目は法人税、所得税、消費税、そして相続税など多岐にわたります。
通常は任意調査であり、きちんと申告していても対象になることがあります。
1-1. 税務調査の種類と特徴
税務調査には大きく分けて「実地調査」と「書面調査」があります。実地調査は税務署の調査官が実際に会社を訪問して行う調査で、通常2~3日間かけて帳簿や書類を詳しく確認します。一方、書面調査は郵送で資料提出を求められる調査で、比較的軽微な確認事項がある場合に実施されます。
1-2. 調査の流れ
税務調査は以下の流れで進行します:
①事前通知(調査日程の連絡)→②実地調査(帳簿・書類の確認)→③調査結果の説明→④修正申告または更正処分
事前通知から実際の調査まで、通常1~2週間の準備期間があります。
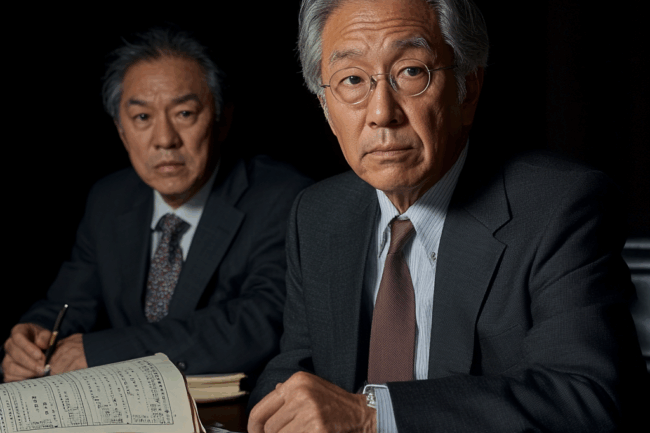
2 法人税における税務調査の実態とポイント
法人税の税務調査は、企業が適切に所得を計算し、税金を正しく納めているかを確認するために実施されます。調査の対象となる法人は、売上規模や業種にかかわらず広範囲に及びます。
2-1. 調査件数と調査率
国税庁のデータによると、令和5事務年度の法人税の申告件数は約296万件、そのうち実地調査が行われたのは約5.9万件で、調査率は約2.0%です。令和元年度の3.1%と比較すると低下していますが、これはAIを活用した効率的な選定により調査の質が向上し、より精度の高い「選定された法人」に集中して行われているのが特徴です。
2-2. 調査されやすい項目
- ■売上の除外や先送り:現金売上の除外や期ズレ計上がないか
- ■架空経費・水増し経費:外注費、広告費、福利厚生費などの内容確認
- ■交際費や寄付金の処理:損金不算入の判断が適切か
- ■役員報酬や退職金:定期同額でない、または過大でないか
2-3. 調査の周期と傾向
税務調査は一度入れば終わりではなく、3~5年に一度の頻度で繰り返し実施されることもあります。また、税理士の申告内容や企業の税務姿勢によって、選定から外れることもあれば、反対に継続的に目をつけられることもあります。
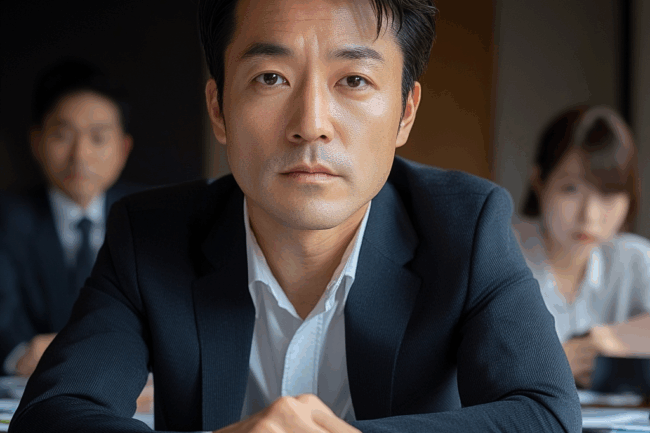
3 税務調査が来る前にできる事前準備
税務調査は突然やってくるようで、実は準備できるタイミングがあります。
3-1. 調査対象になりやすいパターン
■現金取引が多い業種
■売上や経費の変動が大きい事業年度
■関連会社との取引や役員間取引が多い法人
3-2. 帳簿書類の整理と保管
税務調査に備えて、以下の書類を整理しておきましょう:
- ■総勘定元帳、仕訳帳
- ■請求書、領収書、契約書
- ■銀行通帳、現金出納帳
- ■役員会議事録、株主総会議事録
- ■給与台帳、源泉徴収簿
3-3. 経理処理の見直しポイント
調査前に以下の項目を自主的にチェックしておくことが重要です:
- ■売上計上時期の適正性
- ■経費の事業関連性
- ■消費税の課税区分
- ■減価償却の計算方法
- ■引当金の計上根拠
4 税務調査を受けたときの対応のコツ
4-1. 税理士の立会いは必須
調査官とのやりとりは税理士を通じて行うことがトラブル防止の鉄則です。
4-2. 調査当日の心構え
税務調査当日は以下の点に注意しましょう:
- ■調査官への丁寧な対応を心がける
- ■質問には正確に答え、推測での回答は避ける
- ■書類の提出は税理士を通じて行う
- ■調査官の発言内容はメモを取る
- ■不明な点はその場で税理士に確認する
4-3. 素直な対応+証拠書類の整理
質問に対しては事実を簡潔に答えることが重要です。書類は調査官がスムーズに確認できるように分類しておきましょう。
4-4. 指摘内容に納得がいかない場合
税務署から更正処分を受けた場合、不服申立(異議申立・審査請求)も可能です。税理士とよく相談し、方針を決定しましょう。
4-5. 修正申告と加算税
調査の結果、申告漏れが発見された場合は修正申告が必要になります。この際、以下の加算税が課される可能性があります:
- ■過少申告加算税:原則10%(期限内申告税額を超える部分は15%)
- ■無申告加算税:15%(50万円を超える部分は20%)
- ■重加算税:35%(無申告の場合は40%)
ただし、調査前に自主的に修正申告を行えば、加算税は軽減されます。
4-6. 調査終了後の対応
税務調査終了後も以下の点に注意が必要です:
- ■指摘事項の改善策を検討・実施する
- ■同様の問題が他の期にないか確認する
- ■経理体制の見直しを行う
- ■税理士と定期的な打ち合わせを継続する
5 まとめ|法人税の税務調査は準備と対応がカギ
税務調査は「罰するため」のものではなく、「正しい納税を促す」ための制度です。調査をきっかけに、記帳や管理体制を見直すことができれば、経営の健全性を高めるきっかけになります。
法人税の調査対策では、「継続的な会計整備」と「専門家との協力体制」が大きな防御力となります。






