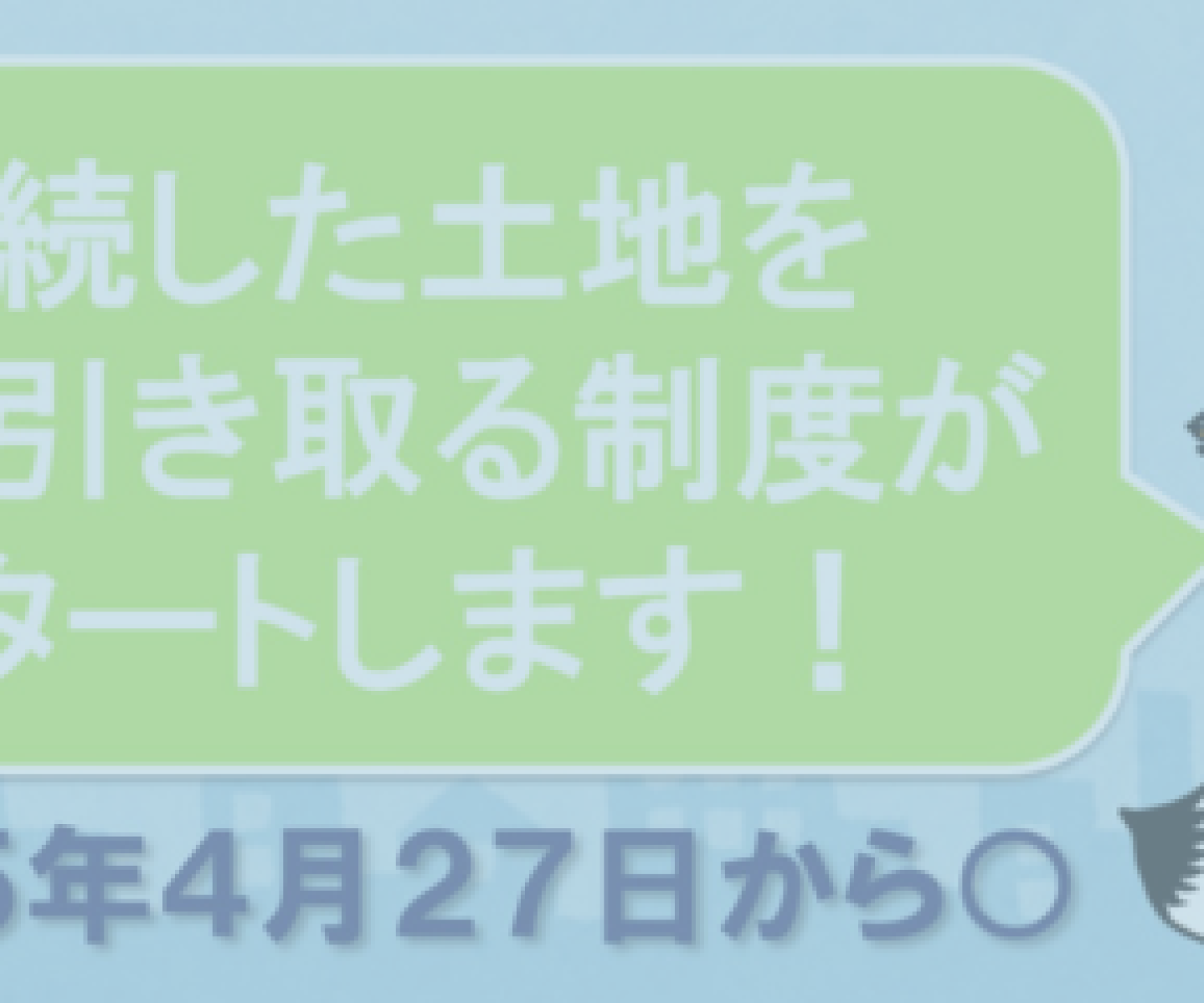目次 1 代償分割とは?相続実務での基本的な位置づけ 2 代償分割が選ばれる理由とは? 3 代償分割の具体例:よくある実務パターン 4 他の遺産分割方法との違い まとめ 代償分割は「実務と公平」を両立させる相続方法 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 今回は、遺産の中に「不動産」が含まれる場合に、特に活用される代償分割(だいしょうぶんかつ)について、実務上のポイントや他の分割方法との違いを含めて解説します。 1 代償分割とは?相続実務での基本的な位置づけ 相続では、現金や不動産、預貯金などの財産をどう分けるかが大きな問題になります。 とくに、遺産の多くが不動産で占められているケースでは、現物での分割が困難なためトラブルの原因になりがちです。こうした状況でよく利用される方法が「代償分割」です。 代償分割の定義 代償分割とは、ある相続人が特定の財産(たとえば不動産)を取得し、他の相続人には代わりに現金などで“代償”を支払う遺産分割方法です。 現物で分けられない財産を、金銭による調整で公平に分け合う点が特徴です。…