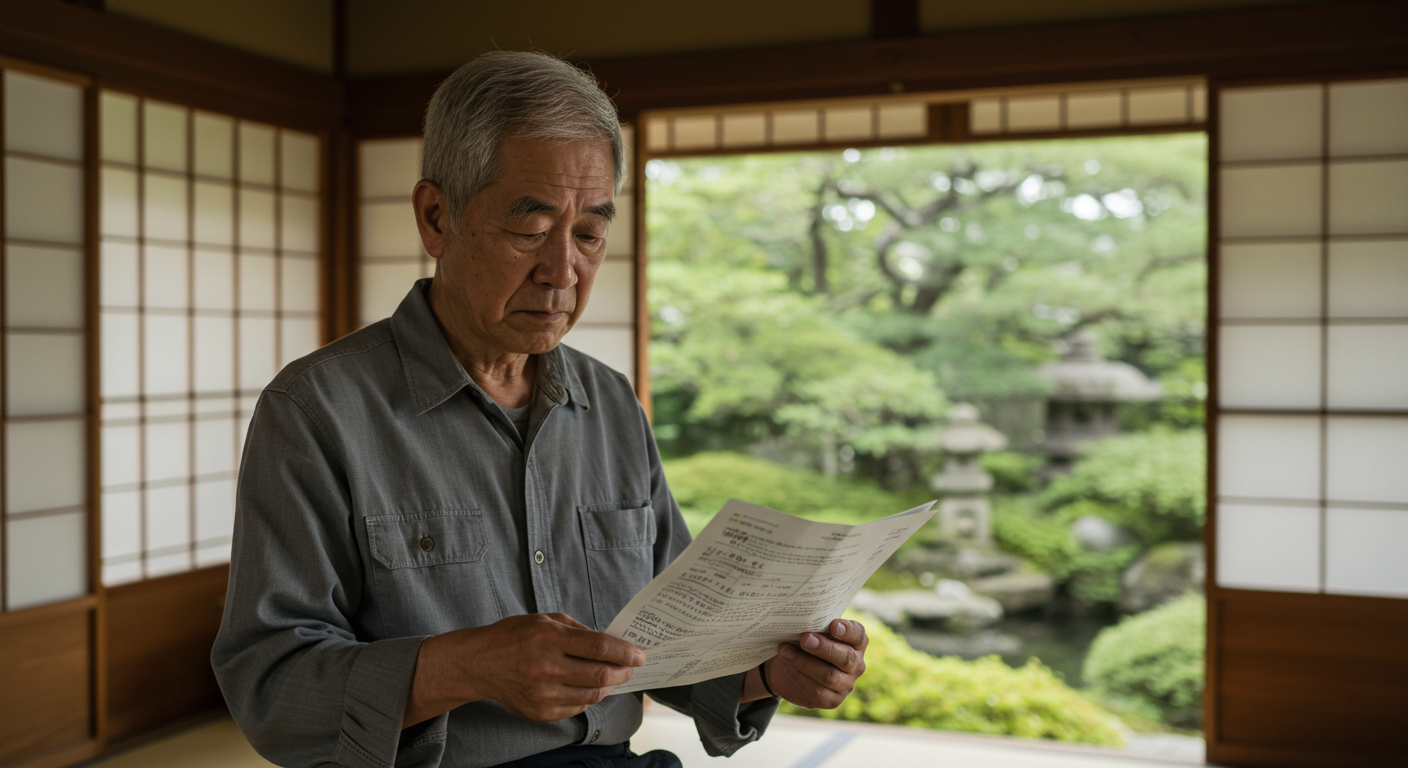目次 1 医療費控除とは?制度の概要 2 医療費控除の対象となる費用 3 医療費控除額の計算方法 4 申告手続きと必要書類 5 申告期限と注意点 6 セルフメディケーション税制について 1 医療費控除とは?制度の概要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 医療費控除は、ご自身や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。年末調整では適用されず、確定申告が必要となります。 2 医療費控除の対象となる費用 医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。対象となるのは次のような費用です:…