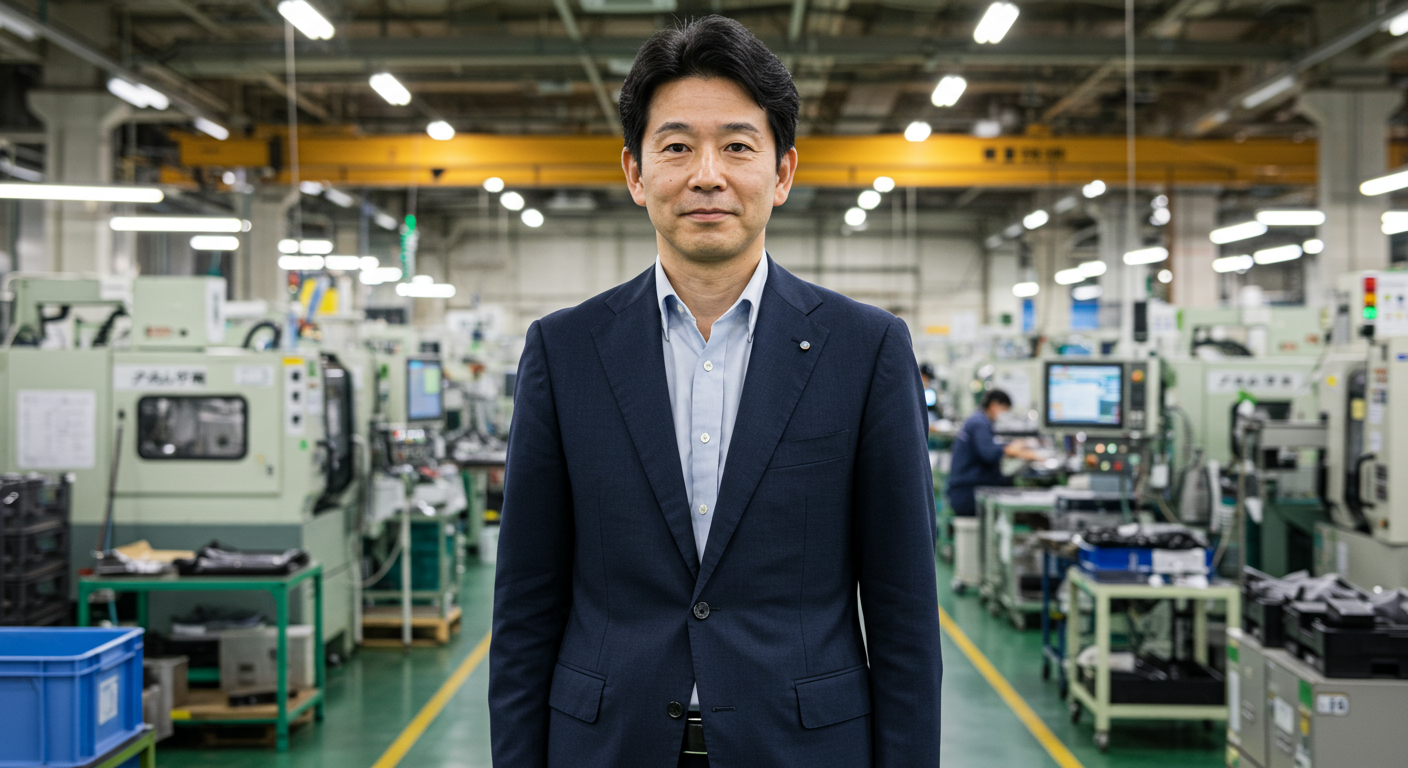目次 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 2 損金算入のために必要な3つの条件 3 注意!「招待」による利用は福利厚生にはならない 4 賃料の「相当性」も忘れずに 5 まとめ:自由な利用・記録の整備・賃料の相当性がカギ こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。「社長が所有するクルーザーを、社員の福利厚生の一環として会社が借り上げたい。このときの賃料は経費(損金)になるのでしょうか?」 福利厚生を重視する企業が増える中、本記事では、税務上のポイントや判断基準について解説します。 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 法人が資産や設備を借りて、その賃料を支払うこと自体は、原則として法人の経費として処理可能です。しかし、貸主が社長本人であり、その資産がクルーザーなど私的利用が疑われやすいものの場合は、より厳密な条件が求められます。 クルーザーのような高額な娯楽資産を福利厚生として認めてもらうことは、税務上極めて困難です。 現実的なリスク: ■税務調査で厳しく否認されるリスクが非常に高い ■社会通念上、クルーザーは「贅沢品」とみなされやすい…