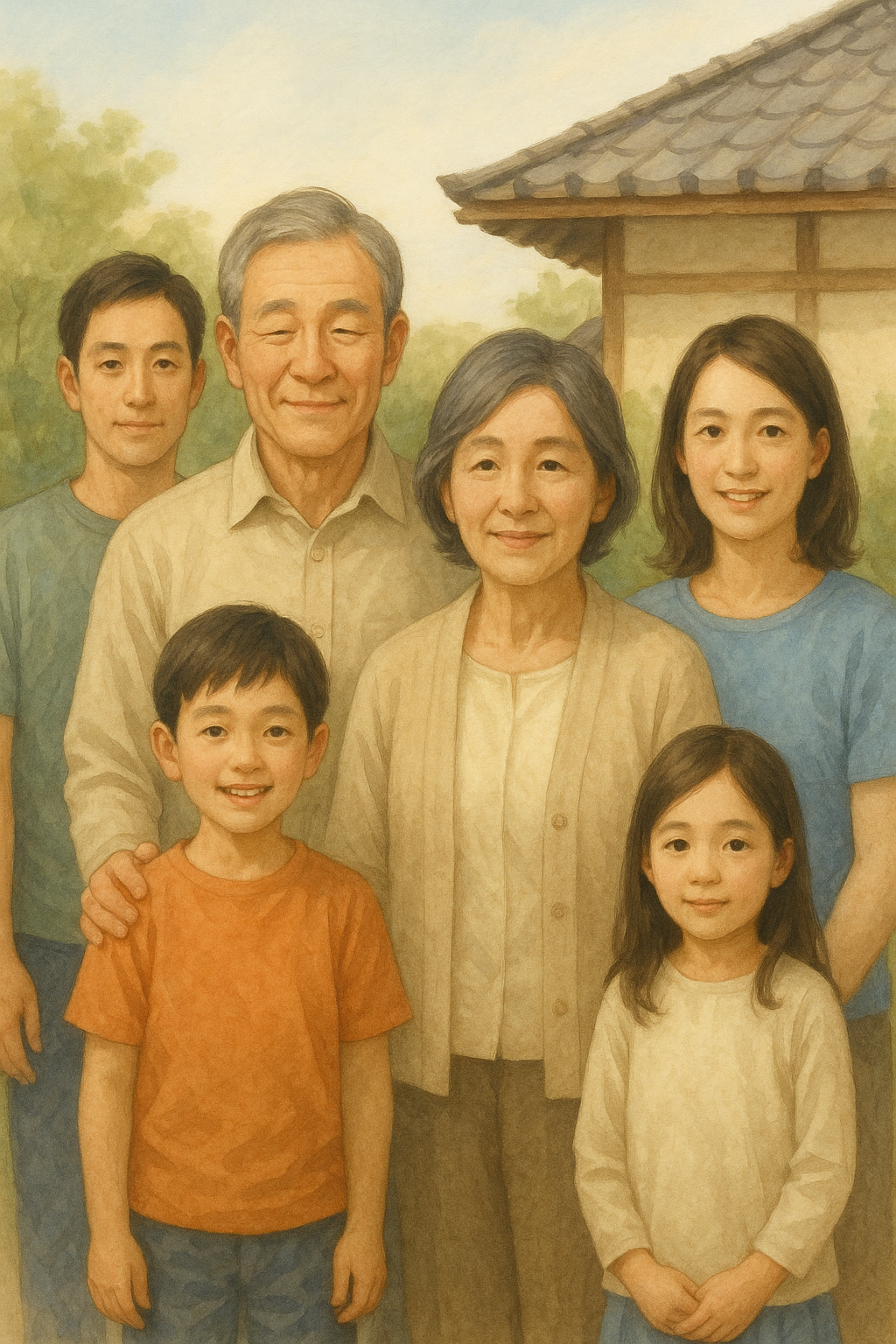目次 1. 配偶者の相続税は最大1億6,000万円まで非課税 2. 配偶者控除を受けるための3つの条件 3. 二次相続を見据えた相続税対策が重要 4. まとめ:配偶者控除は"バランス"がカギ こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「配偶者には相続税がかからないって本当?」「1億6千万円までは非課税って聞いたけど、うちは大丈夫?」このような疑問があるかと思います。 一定の条件を満たすと、配偶者は相続税を最大1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税にできる制度があります。「配偶者控除」と呼ばれる制度です。 この制度をうまく活用すれば相続税の負担を大幅に軽減できる一方で、使い方を間違えると、かえって家族全体の税負担が重くなってしまうこともあります。今回は、この配偶者控除について、基本的な仕組みから注意点までを解説します。 情報元:国税庁 配偶者の税額の軽減 1. 配偶者の相続税は最大1億6,000万円まで非課税 相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産に対する相続税を大幅に軽減してくれる制度です。これは、残された配偶者の生活を守るために設けられている優遇制度です。 よく混同されがちですが、これは所得税の配偶者控除とは全く別の制度です。所得税の配偶者控除は毎年の所得に関するものですが、相続税の配偶者控除は相続時の一回限りの制度となります。 配偶者が受け取る財産のうち、次のいずれか多い金額までは相続税がかかりません ■1億6,000万円…