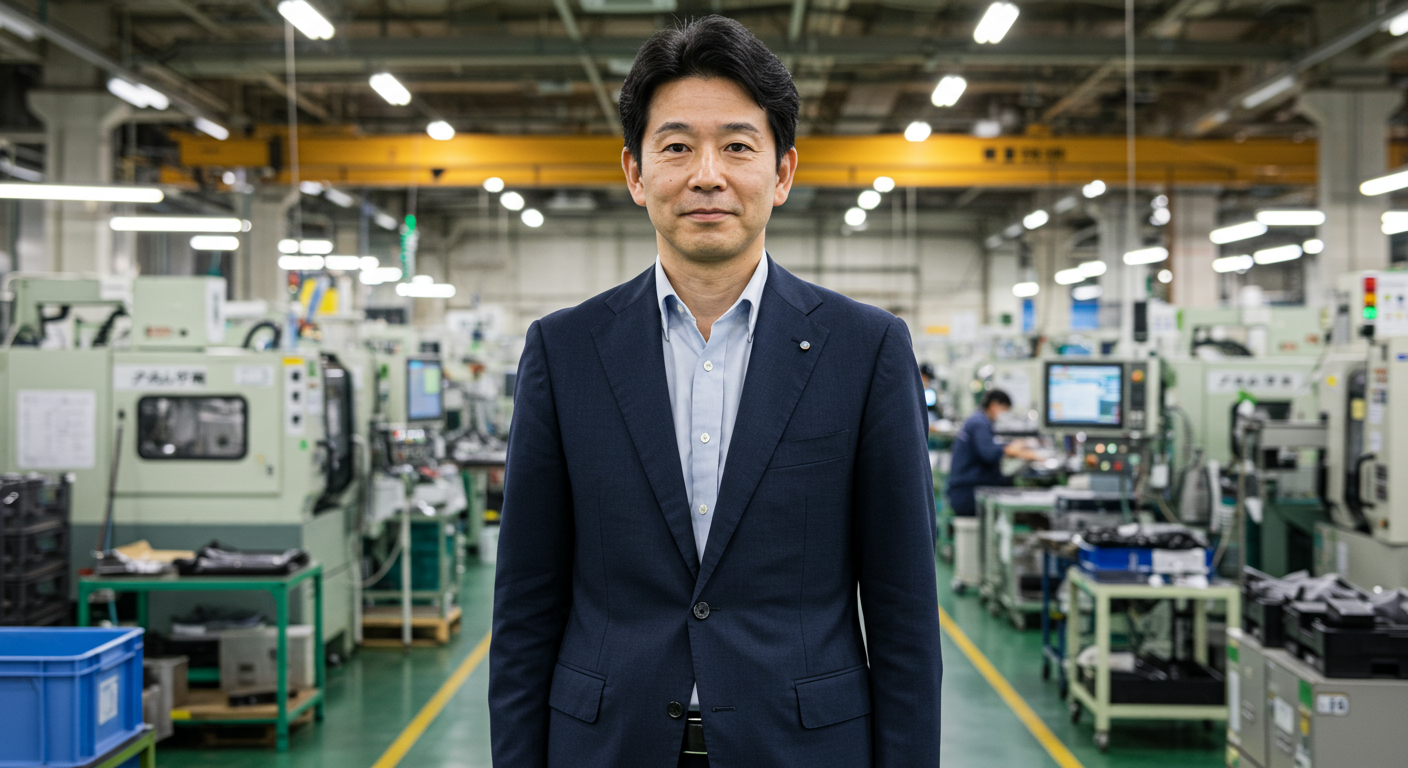こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「住んでいる自治体にふるさと納税はできるの?」「損だって聞くけど本当?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は住民票のある自治体にふるさと納税をした場合のメリット・デメリットを、制度の背景とあわせて詳しく解説します。 1 住んでいる自治体にふるさと納税はできる? まず結論からお伝えすると、居住している自治体にふるさと納税することは可能です。 ふるさと納税は、「応援したい自治体に寄付をする」という仕組みであり、寄付先の制限はありません。現在住んでいる都道府県や市区町村も、寄付対象の自治体に含まれます。 ただし、注意点として、その自治体が“住民票のある自治体”だった場合、返礼品を受け取ることはできません。 2 なぜ「損」と言われるのか?2つの理由 ① 返礼品がもらえない ふるさと納税の大きな魅力の一つが、地域の特産品やサービスなどの返礼品です。しかし、住民票登録のある自治体に対する寄付では返礼品が交付されません。 これは総務省の通知および地方税法により、 「当該地方団体の住民に対して返礼品を送付しないようにすること」と明記されているためです。 ※感謝状など金銭的価値のない返礼は例外的に認められています。 ② 実質的に2,000円の負担だけが残る ふるさと納税は自己負担2,000円を除いた金額が控除される制度です。つまり、返礼品がもらえない場合、2,000円を払って何も得られないという形になるため「損」と感じやすいのです。 3 それでも地元にふるさと納税をする意義とは?…