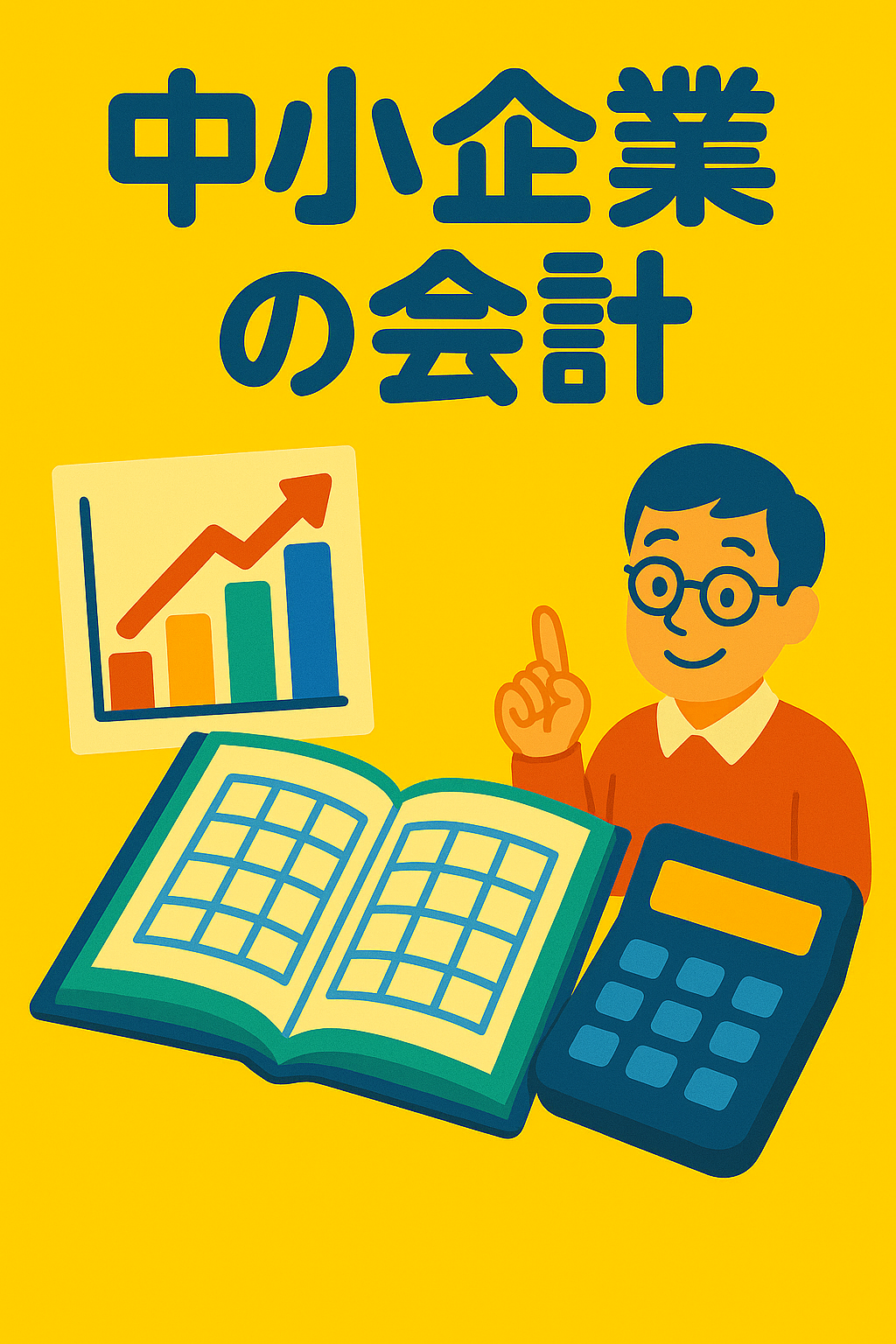目次 はじめに|本要領の目的と学び方 1 適切な記帳の重要性 2 企業会計原則との関係と留意点 3 継続性の原則:処理方法は一貫して 4 本要領で扱われていない処理への対応 まとめ|本要領を活用するための基本姿勢 はじめに|本要領の目的と学び方 「中小企業の会計に関する基本要領」(本要領)は、中小企業が計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等を示すものです。本要領を利用するにあたっては、単に個別の処理方法を知るだけでなく、その根底にある基本的な考え方を理解することが重要です。 今回は、本要領の「総論」で示されている、会計の基本的な考え方や利用上の留意事項をご紹介します。 1 適切な記帳の重要性 本要領を利用するにあたっては、適切な記帳が前提とされています。経営者が自社の経営状況を適切に把握するためにも、記帳は非常に重要です。 記帳はすべての取引について、次の原則に従って行う必要があります。 正規の簿記の原則に則ること。 適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成すること。…