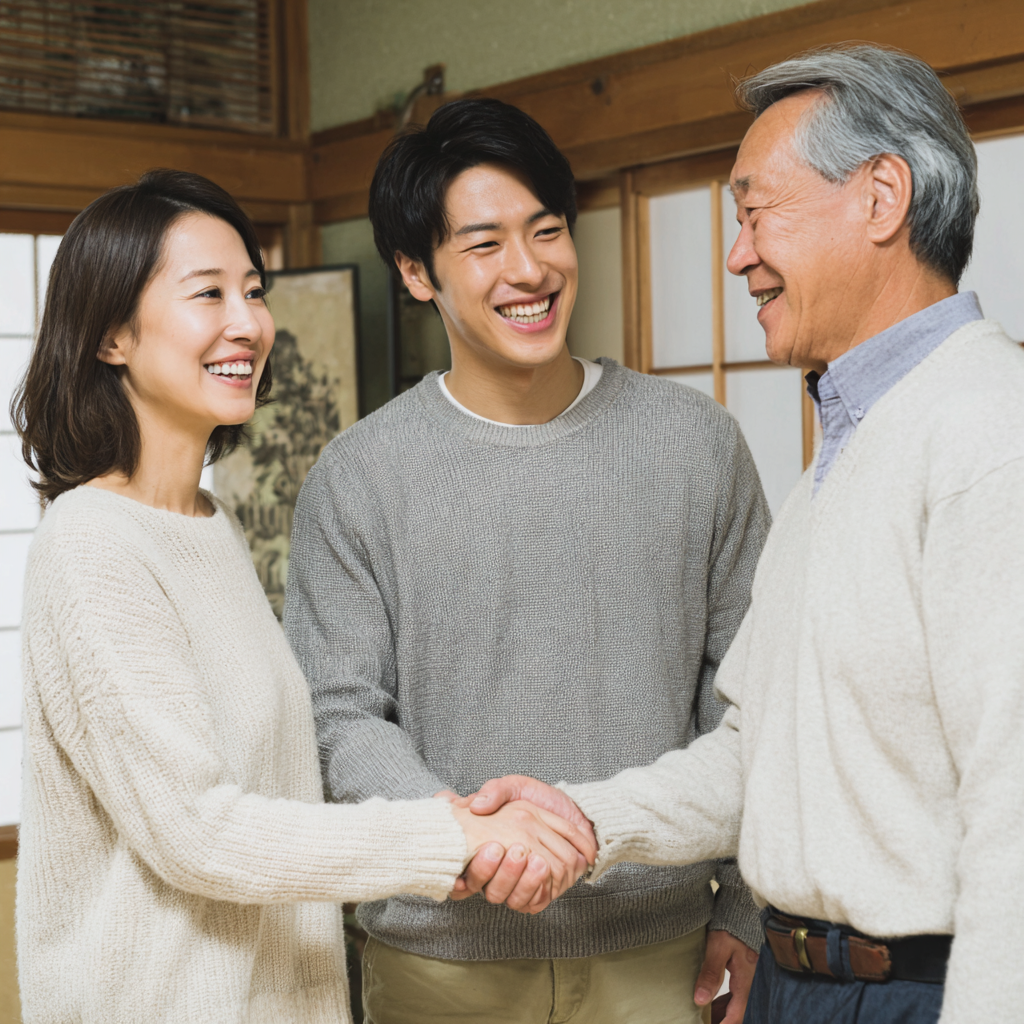目次 1 成年後見制度とは?基本の仕組み 2 成年後見制度のメリット 3 制度のデメリットと注意点 4 親族が後見人になる場合の現実と課題 5 親族が後見人になれない場合とは? 6 成年後見制度以外の選択肢|家族信託と遺言の活用 まとめ 後見制度は「本人の利益最優先」、家族の理解と準備が不可欠 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 高齢化が進む日本社会では、認知症などにより判断能力が低下した方が家族に現れることは決して珍しくありません。こうした場合に重要になるのが「成年後見制度」です。本記事では、制度の基本的な仕組みから、親族が後見人になる場合のメリット・デメリット、そして利用前に考えておきたいポイントについて、解説します。 1 成年後見制度とは?基本の仕組み 成年後見制度とは、認知症・精神障害などにより判断能力が十分でない人(被後見人)の生活や財産を守るため、家庭裁判所が「成年後見人」を選任し、その人が代わって法律行為を行う制度です。…