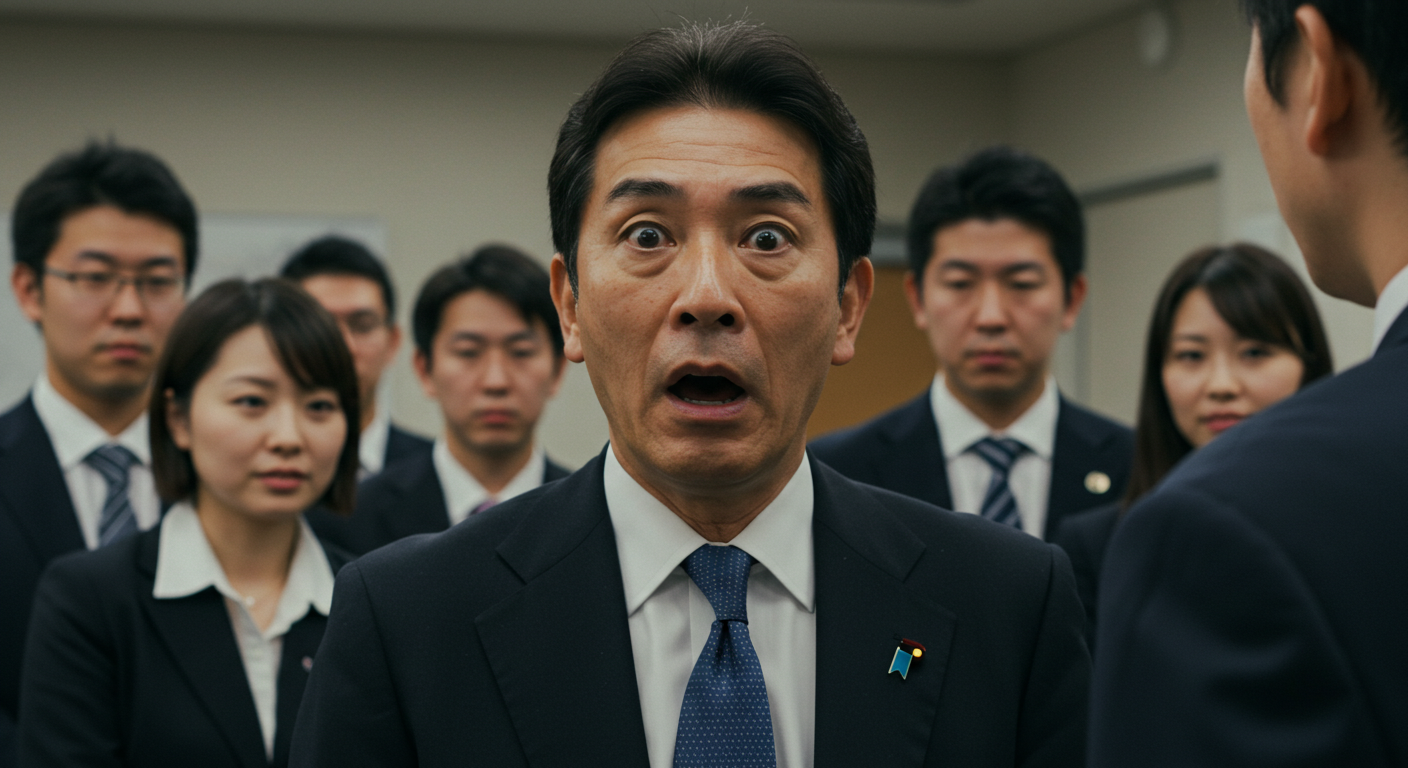目次 1 短期前払費用の特例とは? 2 特例の適用要件 3 該当する費用・該当しない費用の具体例 4 特例を使う際の注意点とリスク 5 実務での適用例と否認事例 6 まとめ:活用には専門的判断が不可欠 こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 会社の経費処理のなかでよく出てくる「前払費用」。これは、サービスの提供を受ける前に支払った費用であり、原則として、その役務の提供期間に応じて費用配分すべきものです。 ただし、「短期前払費用の特例」という例外的な取り扱いが法人税法上に認められており、要件を満たせば、支払時に一括で損金算入できる可能性があります。この特例を適用すれば、特に適用初年度において税金面で大きな効果を得ることが期待できます。 情報元:国税庁 短期前払費用として損金算入ができる場合 1 短期前払費用の特例とは? 短期前払費用の特例とは、法人が支払った前払費用のうち、「支払日から1年以内に提供を受ける役務」に係るものについては、支払時に全額をその年度の損金に算入することが認められる制度です。…