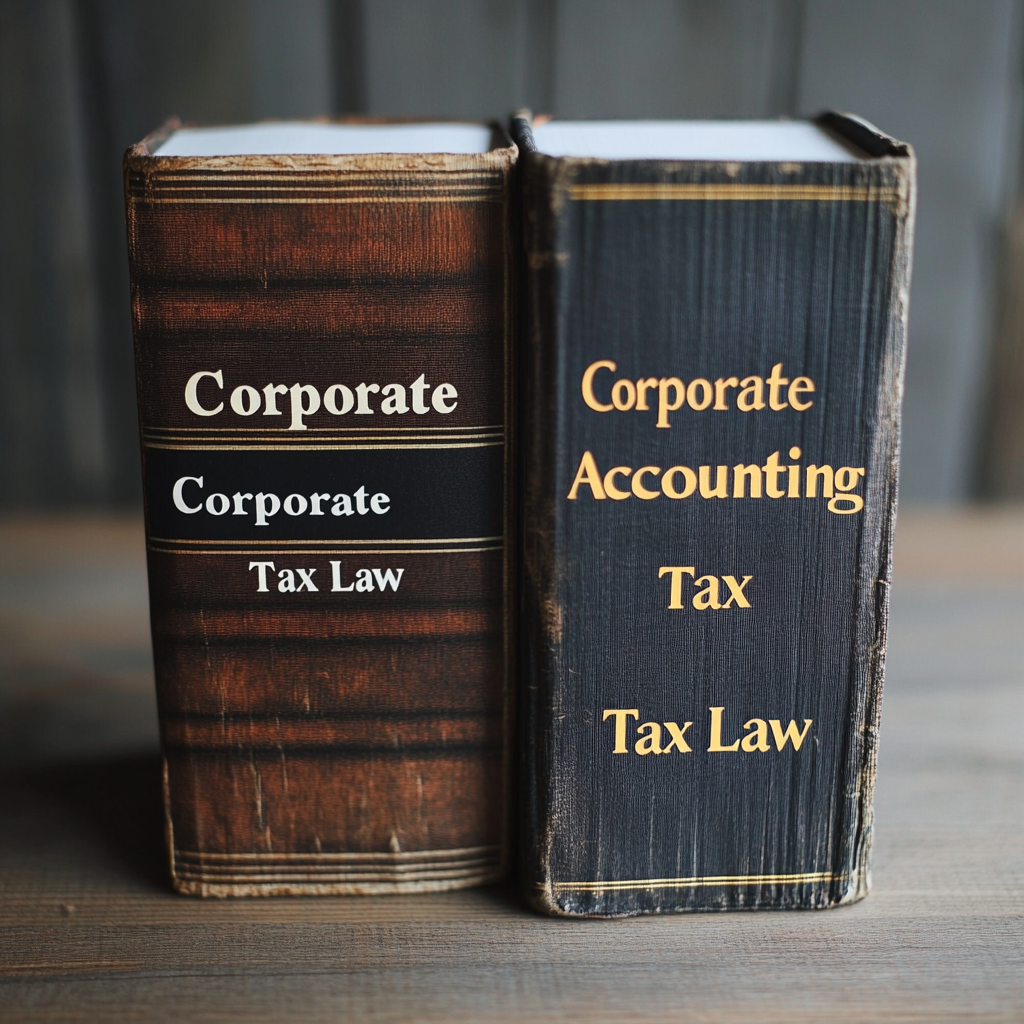目次 1. 消費税の納税義務はすべての事業者にある? 2. 免税点制度とは? 基準期間で判断されます 3. 課税売上高とは?免税売上も含まれる 4. 特定期間による例外:急成長した事業は要注意! 5. 売上だけでなく「給与支払額」でも判定できる 6. 事業の成長とともに「免税→課税」へ切り替えが発生 まとめ|「納税義務があるか?」を正しく判定しよう 事業者が確認すべき「免税点」と「特定期間」 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 事業を始めてしばらく経つと、「そろそろ消費税の納税義務があるかも?」と気になるタイミングがやってきます。今回は、消費税の納税義務が発生するかどうかの判定基準である「免税点制度」と「特定期間」について解説します。 1 消費税の納税義務はすべての事業者にある?…