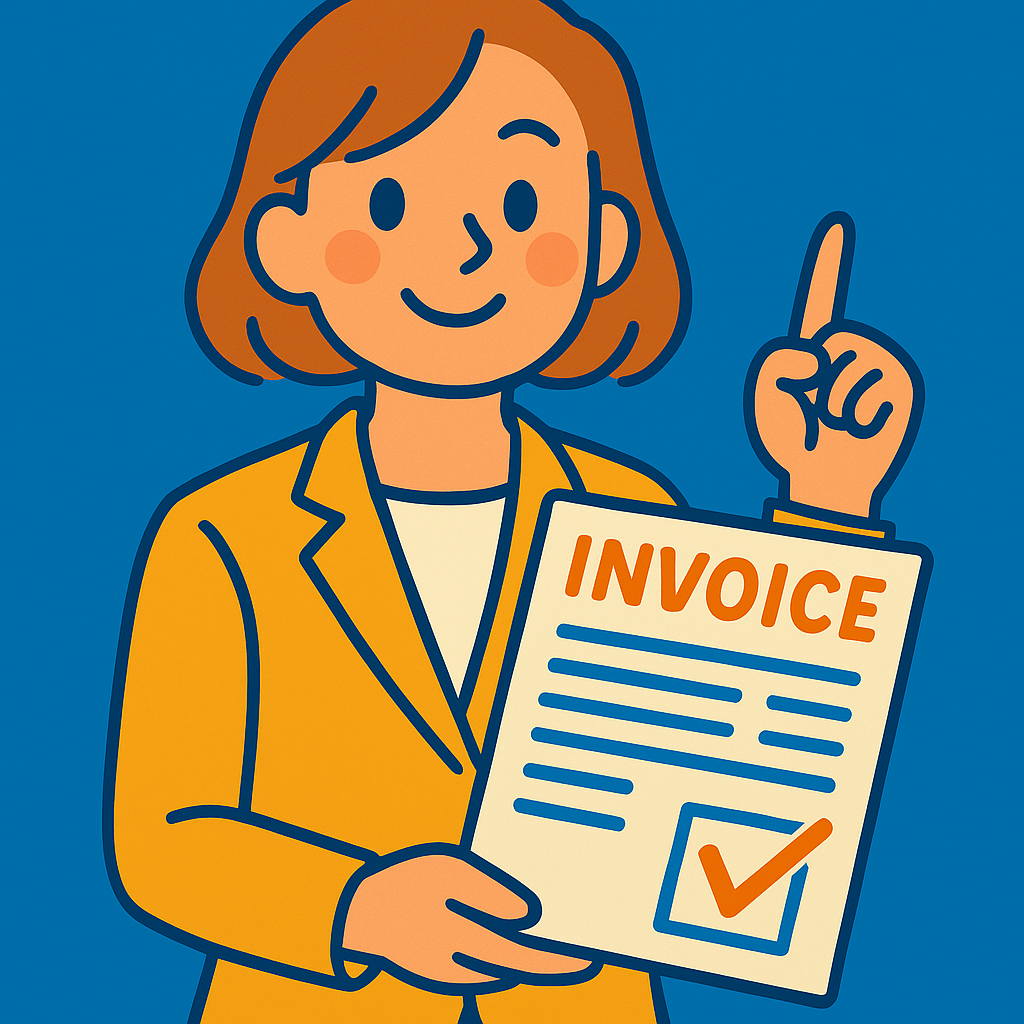目次 1 免税事業者がインボイス発行事業者になるには? 2 特別な経過措置とは? 3 課税事業者となるタイミングと消費税申告 4 小規模事業者向け「2割特例」とは? 5 「少額特例」との違いも知っておこう 6 課税選択届出書の提出には注意! 7 間違えた場合の対処法:「不適用届出書」の活用 まとめ 免税事業者のインボイス登録は慎重に こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 令和5年10月に導入された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、すべての事業者に大きな影響を及ぼしています。特に、これまで消費税の申告・納税義務がなかった免税事業者の皆さまにとっては、「インボイス発行事業者になるかどうか」は重要な判断事項です。 当事務所でも制度導入時にインボイス制度の基礎を解説してきましたが、令和7年4月に国税庁が「インボイス制度に関するQ&A」を改訂したことを受け、今回はあらためて免税事業者がインボイス発行事業者になる手続きと注意点をまとめ直しました。…