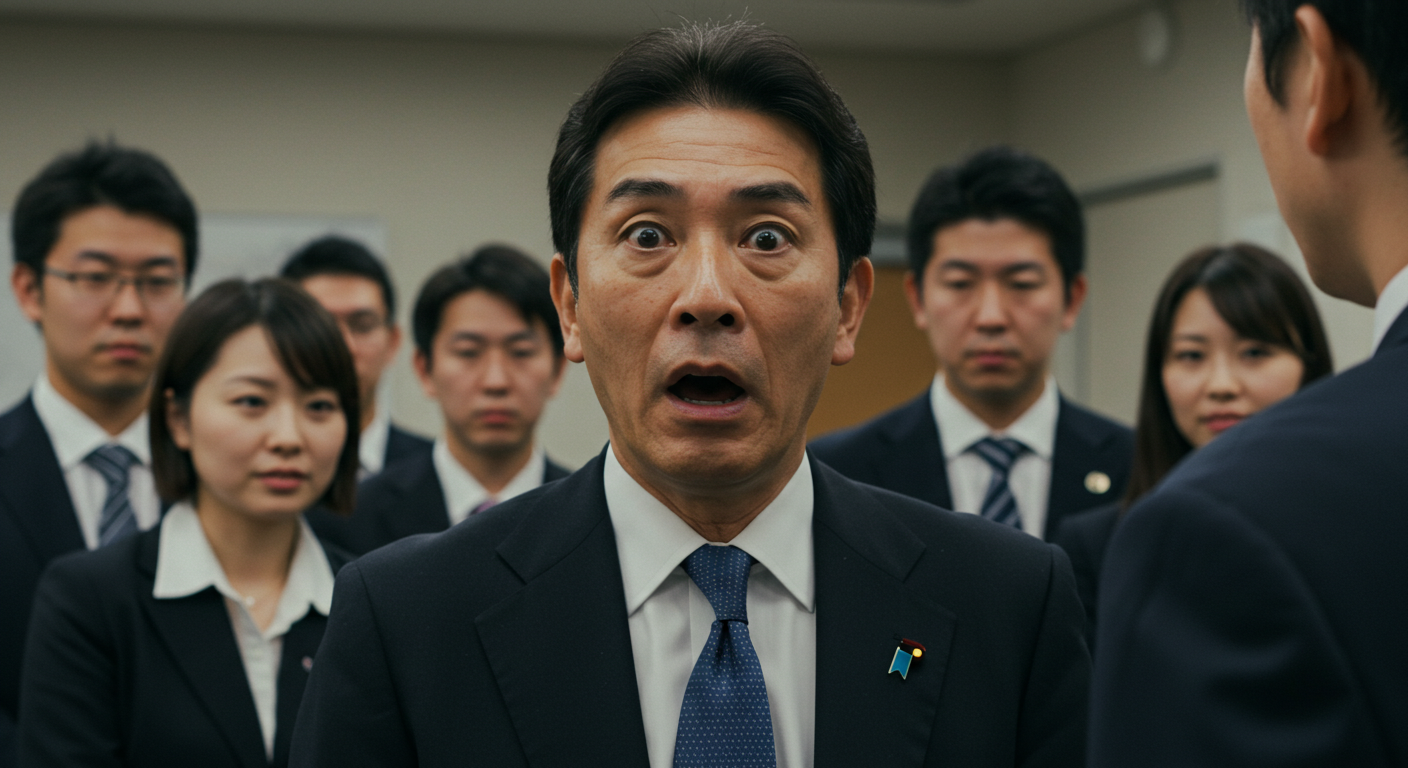目次 1. 生前贈与の基本:口約束でも成立するって本当? 2. ケース別対処法:あなたの状況はどれに当てはまる? 3. なぜ贈与契約書を作成すべきなのか? 4. 贈与契約書の正しい書き方 5. 生前贈与と税金の注意点 6. 生前贈与で注意すべきその他のポイント まとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 生前贈与「口約束でも大丈夫」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、大きな問題がひそんでいます。 今回は、口頭での生前贈与の有効性とそのリスク、そして安全に進めるための対策についてお話します。 1 生前贈与の基本:口約束でも成立するって本当? 結論から言うと、生前贈与は口約束でも法的には有効です。…