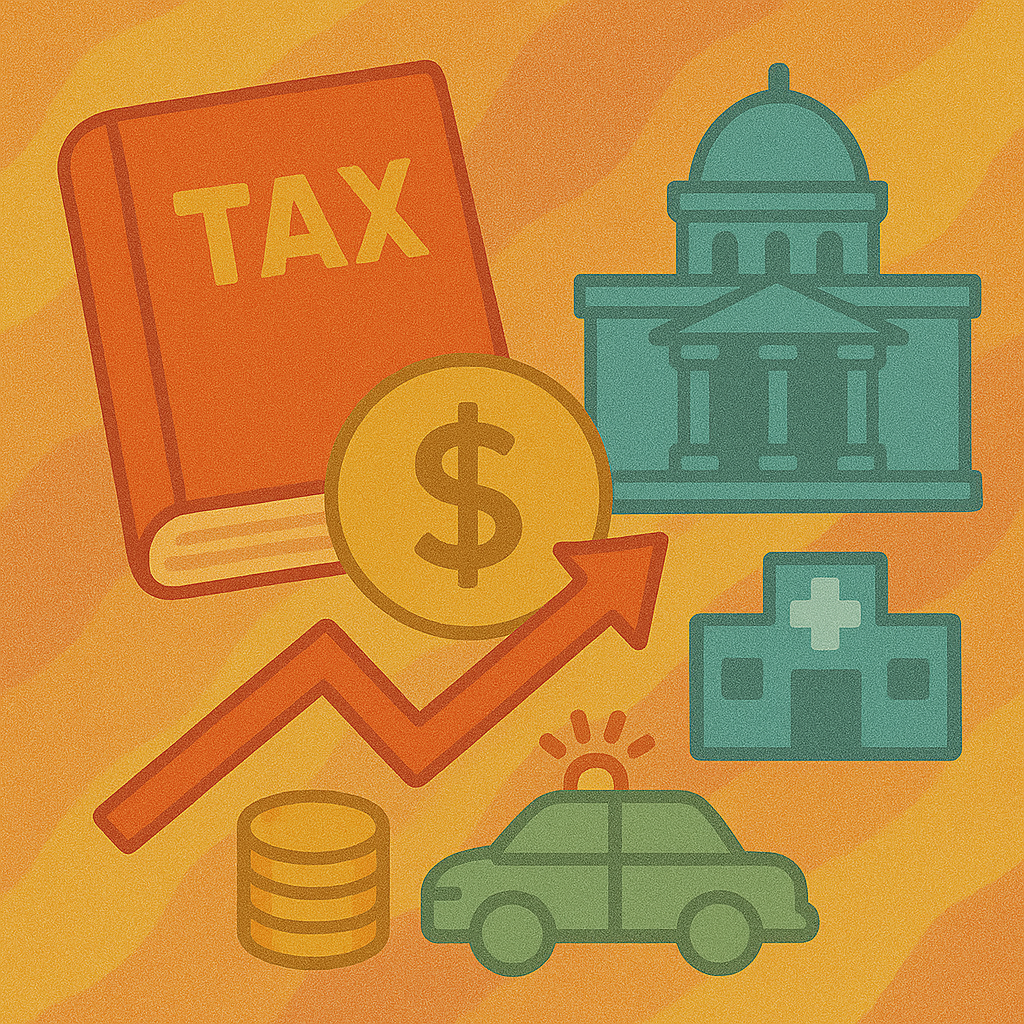目次 1 胎児の相続権とは?民法第886条の規定 2 胎児がいる場合の遺産分割と実務上の注意点 3 胎児と相続税申告|申告期限と基礎控除の関係 4 胎児が代襲相続人になることもある 5 まとめ|胎児の相続は“出生”がカギ。正確な判断と慎重な対応を こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「まだ生まれていない子ども=胎児には相続権があるのか?」 胎児にも相続人としての権利が認められるケースがあります。本記事では、胎児の相続権について、実務上の注意点や税務処理も交えながらわかりやすく解説します。 1 民法第886条が定める胎児の相続権とは? 民法には以下のように定められています。 第一項:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。第二項:前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 胎児は生まれた場合に限り、相続開始時に「既に生まれていた」とみなされて、相続人として取り扱われます。出生が条件となるため、「停止条件付き相続権」とも呼ばれます。…