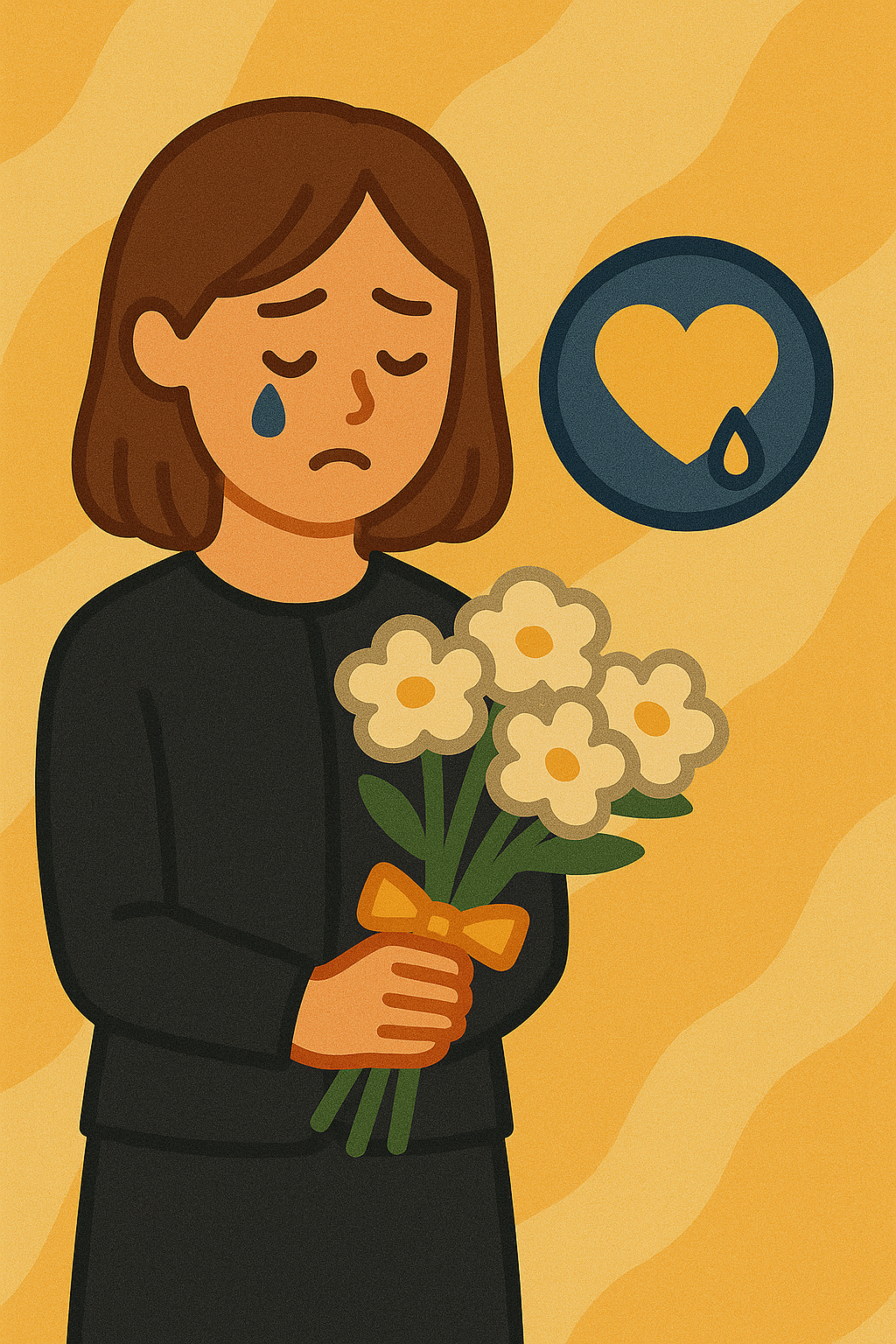目次 1 老人ホームの入居一時金とは? 2 入居時の課税関係にも注意 3 返還金は誰のもの?トラブルになりやすい相続上の注意点 4 その他の関連論点 5 まとめ|返還金の税務判断は専門家に相談を こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。 高齢の方が老人ホームに入居する際、多くの場合「入居一時金」というまとまった費用を支払います。この入居一時金、被相続人が亡くなった後に一部返還されることがありますが、この返還金は相続税の対象になるのでしょうか? 今回は、老人ホームの入居一時金の返還金が「相続財産」にあたるのか、また課税関係や注意点について詳しく解説いたします。 1 老人ホームの入居一時金とは? 老人ホームに入居する際に支払う「入居一時金」は、居住費やサービス提供に対する前払い金として扱われ、入居者が退去または死亡した際に、一定期間分の未償却分が返還される仕組みです。 返還金は契約内容により異なり、償却期間の途中で亡くなった場合、その未償却分が一定の計算式に基づいて戻ってくることがあります。 返還金の相続税上の取扱い 入居一時金の返還金は、原則として相続税の課税対象となる相続財産です。被相続人の死亡時点で、契約に基づき返還される権利(債権)として相続財産を構成します。…