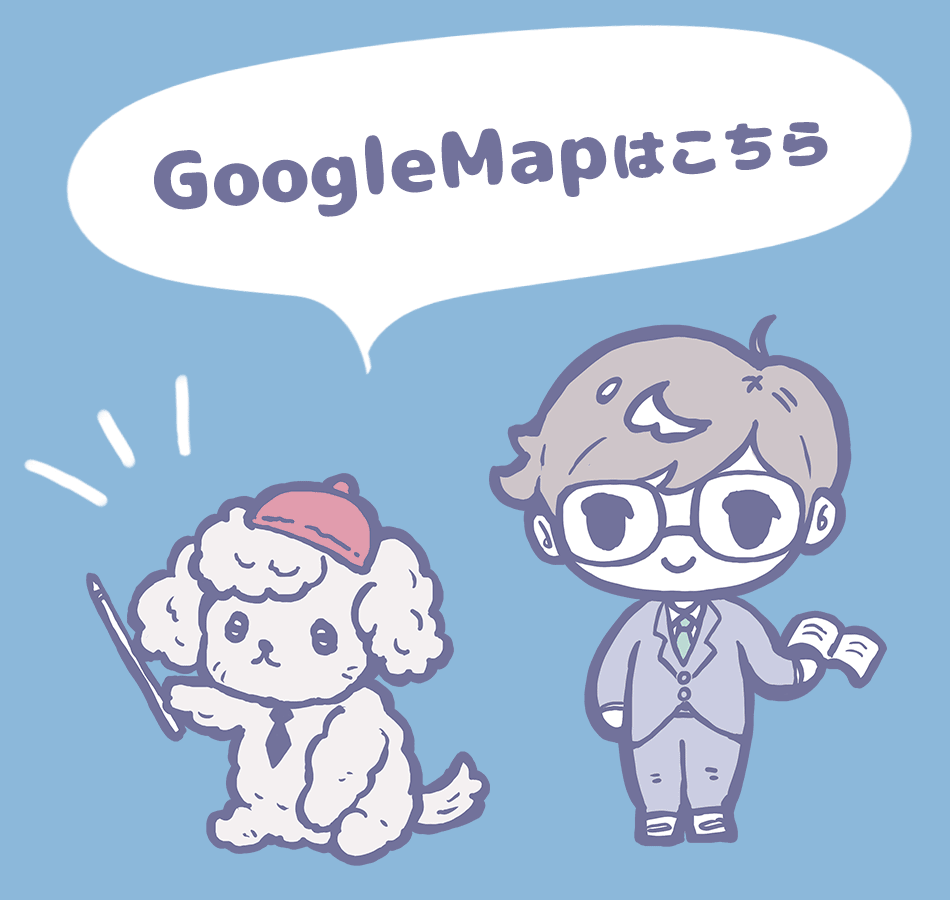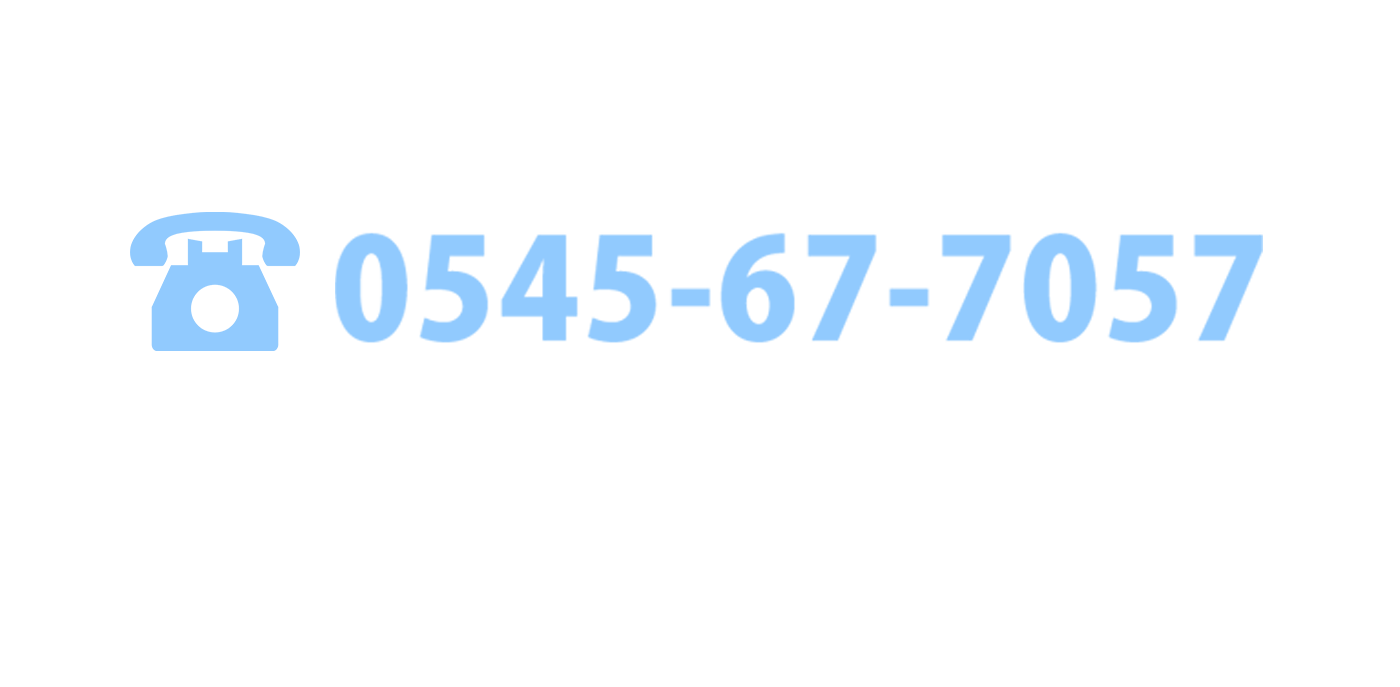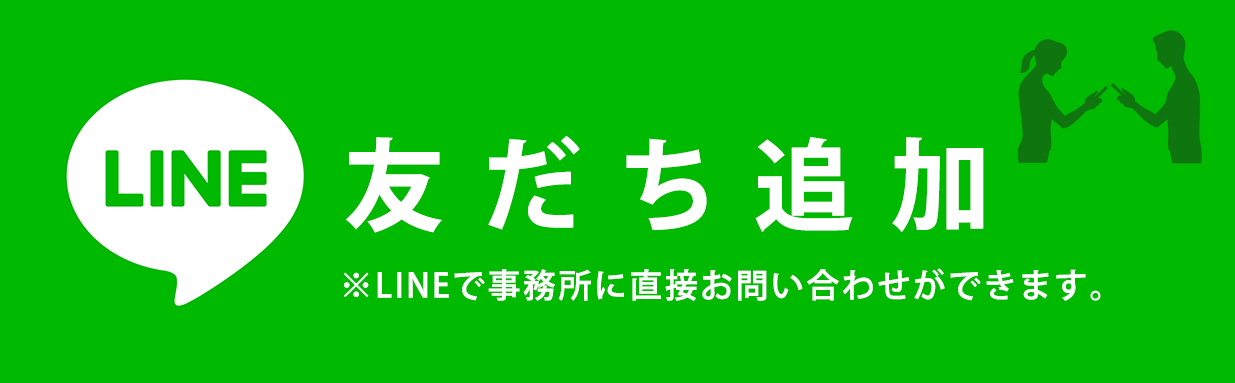目次 1. 役員報酬の基本と税務上の制限 2. 定期同額給与とは? 3. 事前確定届出給与とは? 4. その他の注意すべきポイント 5. まとめ:専門家への相談を こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 今回は、会社の「顔」とも言える役員の皆さんの報酬について、法人税法上で特に気を付けていただきたいポイントを解説します。従業員への給与とは異なる、役員報酬の税務上のルールを正しく理解しましょう。 1 役員報酬の基本と税務上の制限 会社は通常、「経営者(役員)」と「従業員」で構成されます。従業員と会社が「雇用」の関係にあるのに対し、役員と会社は「委任」の関係にあります。従業員への給与は、役員と従業員の合意に基づき、会社の費用(損金)として認められます。 ところが、役員報酬には税務上の厳しい制限があります。これは、特に中小企業に多い「オーナー会社」の場合、社長自身が株主であるため、会社の業績に応じて報酬額を自由に増減させることで、利益操作が可能となり、課税の公平が損なわれる可能性があるためです。 法人税法上、役員に支給する給与のうち、以下のいずれにも該当しない金額は損金に算入されません。また、事実を隠蔽・仮装して経理したり、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。 なお、役員報酬が損金不算入となった場合、法人税法上は会社の経費として認められないため、会社側では法人税等の負担が増加し、同時に役員個人では所得税・住民税が課税されるという二重課税の状態となります。このため、役員報酬の設定は慎重に行う必要があります。 【具体例】資本金1,000万円の会社で、社長が期中に月額報酬を100万円増額した場合 ・年間増額:100万円 × 12か月 = 1,200万円 ・会社の追加法人税(実効税率30%):360万円 ・社長個人の所得税・住民税(税率33%):396万円 ・合計税負担:756万円(増額分の63%が税金) このように、二重課税により非常に大きな負担となります。 損金算入が認められる役員給与の3種類 損金算入が認められる役員給与は、主に以下の3種類です。 定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ) 事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ) 業績連動給与(ぎょうせきれんどうきゅうよ) このうち「業績連動給与」は、その算定方法が有価証券報告書に記載されるなど、上場企業などに限定された要件が多いため、多くの中小企業には適用が難しいのが現状です。そのため、中小企業では「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の理解が非常に重要になります。 2 定期同額給与とは? 定期同額給与とは、「支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」を指します。簡単に言えば、「毎月、同じ日に同じ金額を支払う役員報酬」のことです。 この「同額」には、源泉徴収される所得税や地方税、社会保険料などが控除された後の「手取り額」が同額であるものも含まれます。 ただし、支給日が土日祝日にあたる場合の前後への変更や、うるう年による日数の違いは「同額」の判定に影響しません。また、社会保険料率の変更などによる手取額の変動も、報酬額自体が同額であれば問題ありません。 原則として、事業年度の途中で役員報酬の金額を増減することは認められません。しかし、例外的に損金算入が認められる改定パターンがあります。 損金算入が認められる改定パターン 1. 事業年度開始の日から3か月以内に行われる定期給与の改定 これは通常、定時株主総会の開催時期に合わせて行われる改定を指します。役員の選任機関である株主総会で報酬額を決議し、その決議に基づいて新しい事業年度の報酬額を決定します。 例えば、3月決算の会社であれば、6月の定時株主総会で役員報酬の改定を決議し、7月支給分から新しい報酬額を適用する、といったケースがこれに該当します。 注意点として、3か月以内であれば何度でも改定できるわけではありません。合理的な理由のない頻繁な改定は、税務調査で否認される可能性があります。 2. 臨時改定事由による改定 これは、役員の職制上の地位の変更や、職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情によって行われる改定です。 例えば、社長が体調を崩して引退し、息子が新社長に就任する場合、新しい社長の職務内容の重大な変更にあたるため、臨時株主総会で報酬を決議し改定することが認められます。 また、役員が病気で入院し、一時的に職務の執行が困難になったために役員給与を減額する場合も、職務内容の重大な変更に該当し、臨時改定事由による改定として認められます。その後、職務が通常通りに戻った際の再改定も同様に認められます。 3. 業績悪化改定事由による改定 これは、法人の経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合に行われる改定です。 単に業績目標に達しなかった場合や、一時的な資金繰りの都合は含まれません。 具体的には、株主や債権者、取引先などの第三者の利害関係者との関係上、役員給与の減額が避けられない状況であると客観的に判断される必要があります。 例えば、売上の大半を占める主要な取引先が倒産し、今後売上が激減することが不可避と認められる場合、あるいは取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で役員給与の減額が求められた場合などが該当します。 重要なのは、「客観的な事情」があるかどうかであり、利益調整のみを目的とした減額改定は認められません。 認められない改定の注意点 上記以外の理由で事業年度の途中で役員報酬を増額または減額した場合、同額でない期間の役員報酬は、原則として損金に算入されません。 例えば、期の途中で何の理由もなく報酬を増額した場合、増額された部分だけでなく、増額後の期間の報酬全体が損金不算入となる可能性があります。これは、法人税と個人の所得税が二重に課税されることになり、非常に大きな税負担となるため、十分に注意が必要です。 【損金不算入の計算例】 月額報酬60万円の社長が、10月に80万円に増額した場合: ・10月~3月(6か月間)の報酬:80万円 × 6か月 = 480万円 ・この480万円全額が損金不算入の可能性 ・会社の追加法人税:480万円 × 30% = 144万円 ・個人の税負担:480万円 × 30% = 144万円 ・合計:288万円の追加税負担 3 事前確定届出給与とは? 事前確定届出給与とは、平たく言えば役員に支給するボーナス(賞与)の確定した額の金銭、または確定した数の株式や新株予約権などを交付する旨をあらかじめ定め、税務署に届け出ることで、その給与を損金に算入できる制度です。 【活用例】3月決算会社の社長賞与 ・支給日:令和6年12月25日 ・支給額:500万円 ・損金算入による法人税軽減:500万円 × 30% = 150万円 ・個人の所得税負担:500万円 × 20% = 100万円 ・実質的な資金効果:手取り350万円、法人税軽減150万円 重要なポイント 1.…






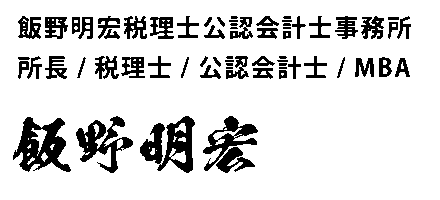





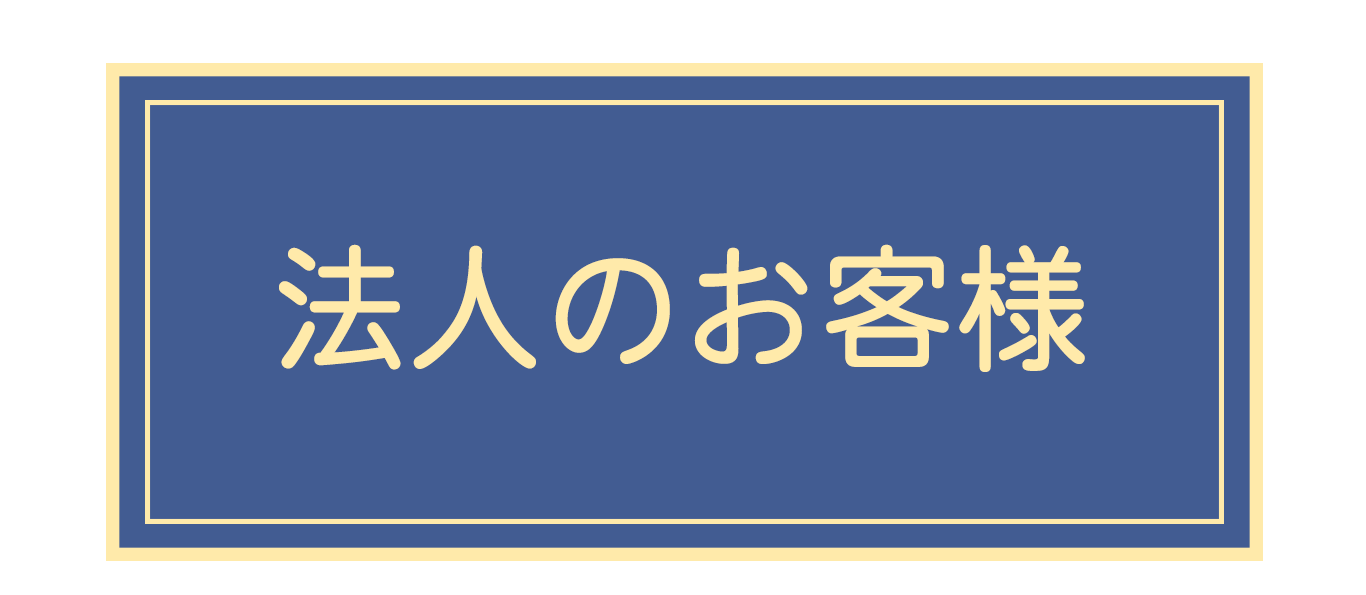
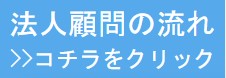
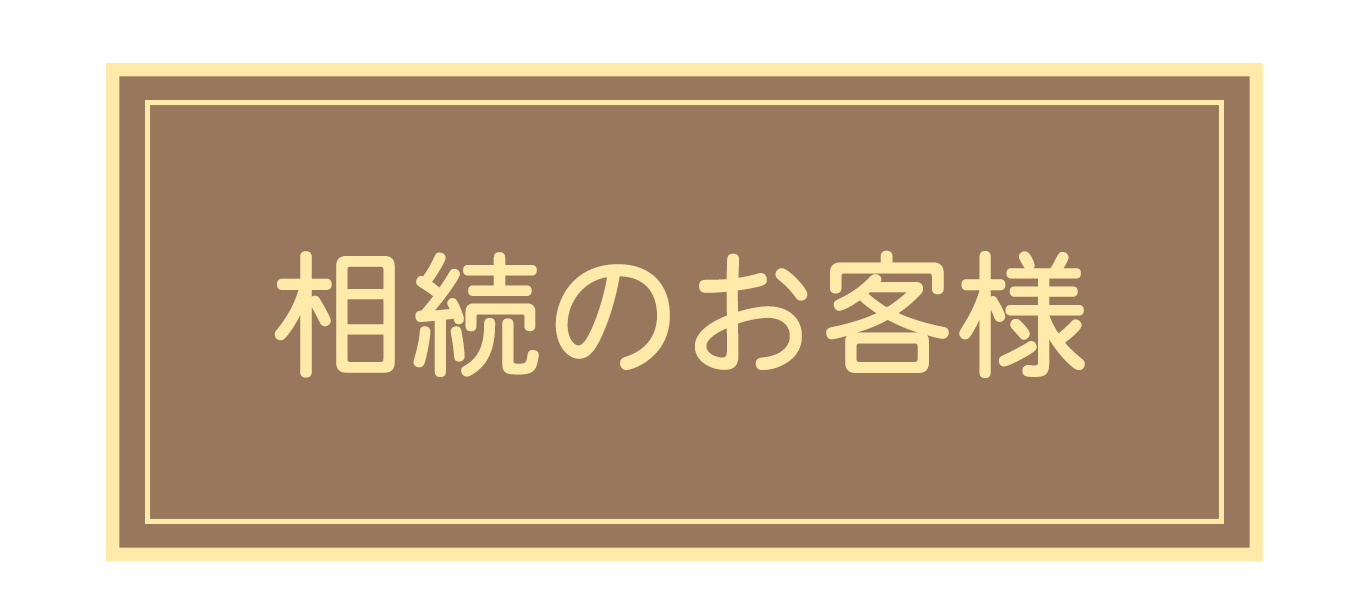
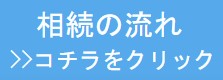


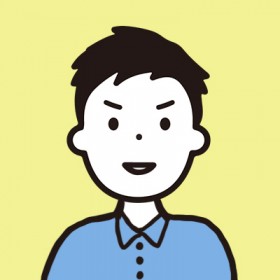

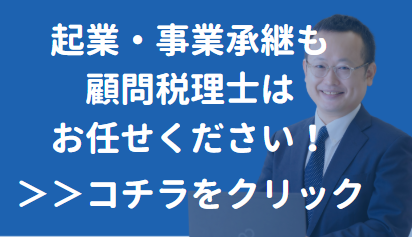
.png)